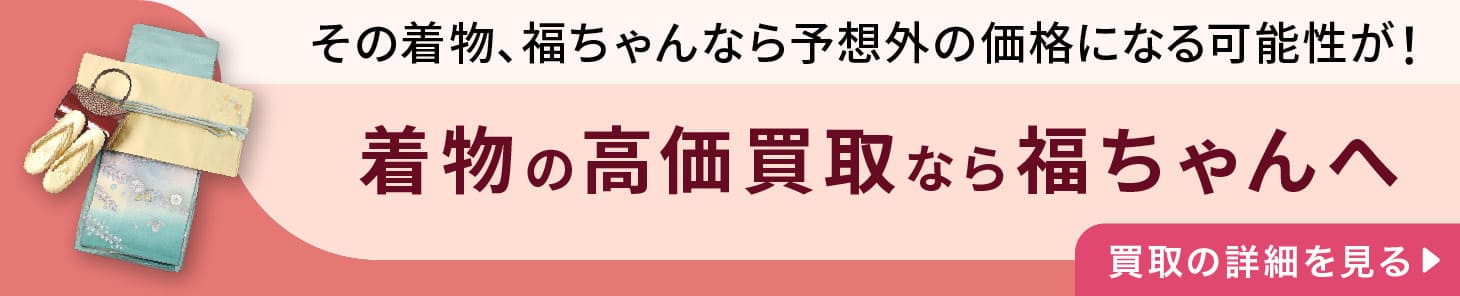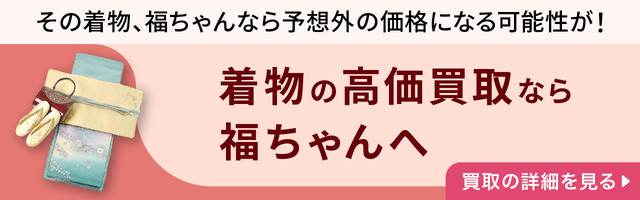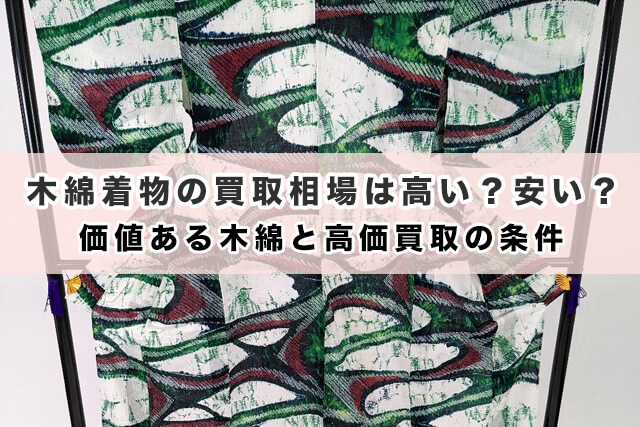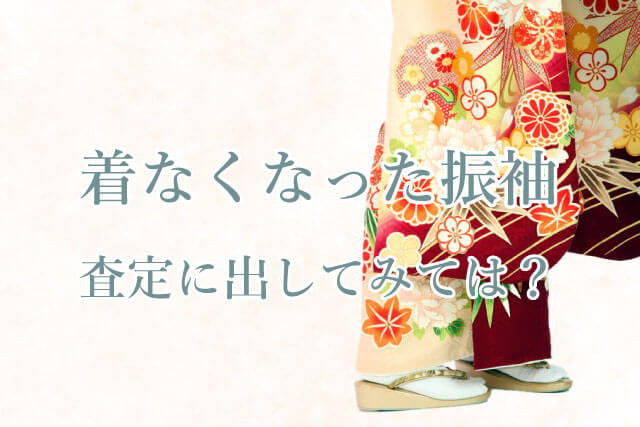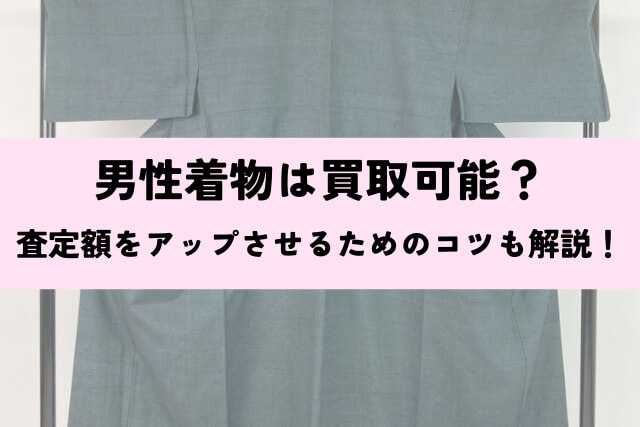- 着物
- 2025.05.17
袴の買取にはコツがある!査定の注意点や買取相場も押さえておこう

成人式、卒業式、結婚式といった特別な日に着用される袴(はかま)は、大切な思い出とともに保管されているのではないでしょうか。
役目を終えた袴に対し、「どのように今後は活用すればよいのか」「できれば価値を理解してくれる方に買い取ってもらいたい」とお考えの方も多いでしょう。
袴は、振袖や訪問着といった他の着物と比較すると着用シーンが限られます。そのため、いざ手放そうと思ったときに「本当に袴は売れるのか」「袴を少しでも高く売るにはどうすればよいのか」といった疑問や不安が生じるのは当然です。
袴の買取には、知っておきたいいくつかのコツと注意点があります。
この記事では、袴の買取をスムーズに進め、満足のいく結果につなげるために必要不可欠な情報を網羅。高価買取されやすい袴の特徴・査定額アップのポイント・信頼できる業者の選び方など、わかりやすく解説いたします。
ぜひ最後までお読みいただき、後悔のない袴買取のためにお役立てください。
袴は買い取ってもらえるのか?

「もう着用しない袴の買取は可能なのか」
という疑問は、多くの方が抱えていらっしゃるでしょう。
結論としましては、袴の買取は、業者によって対応が変わるのが現状です。
その背景には、袴が卒業式や結婚式といった、特定の行事で主に着用される点が挙げられます。振袖や訪問着などの着物と比較すると、日常的な需要や再販市場でのニーズが常に高いとはいえない状況です。
さらに、ウールやポリエステルといった化学繊維で作られた袴に加え、状態によっては、買取が難しいケースもございます。
しかし、だからといって、袴の買取をあきらめる必要はございません。
袴にも確かな需要があり、とくに質の高いものや、デザイン性の高いものは価値が見出されます。
たとえば、独自の販売ルートを国内外にもっていたり、リメイク素材としての活用法を熟知していたりする専門業者であれば、買取の対象となる可能性がアップするでしょう。さらに、所有される袴の素材や状態、希少性などを的確に評価し、ときには予想以上の高価買取となることも十分にあり得るのです。
重要なのは、まずお手持ちの袴の価値をしっかりと見極め、適正な価格で買い取ってくれる信頼できる業者を見つけることです。
そこから、納得のいく買取への第一歩が始まります。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

袴とは?

袴とは、日本の伝統的な和装において、着物の上から腰より下を覆うようにして着用する衣服の一種です。
一般的には、着物をやや短めに着付けた上から、ズボンのように履いたり、巻きスカートのように腰にまとったりして身に付けます。
主な種類としては、股の部分に仕切りがあるズボン状の「馬乗り袴(うまのりばかま)」と、仕切りのないスカート状の「行灯袴(あんどんばかま)」の2つに大別されます。
これらの袴は「性別」や「用途」によって、使い分けられることも。
袴の歴史は非常に古く、古墳時代にはすでにその原型が見られ、主に男性の衣服として用いられてきました。女性においては、古代では下衣(したごろも)として身体を覆う役割もありましたが、時代が下るにつれて公の場での装束の重要な構成要素として発展。とくに平安時代の宮中などでは、身分や儀式、場面に応じて、多種多様な色や形の袴が着用されるようになりました。
近代に入り、明治時代になると、教育の普及と共に女学生の制服として行灯袴が採用されたことは、袴の歴史における大きな転換点になりました。女性にとって、袴がより身近なものとなるきっかけとなったのです。
現代においては、男性の場合、最も格式の高い礼装である紋付き羽織袴(もんつきはおりはかま)が代表的です。また、神職や剣道・弓道といった武道の稽古着としても、広く用いられています。
女性の場合は、大学など卒業式での華やかな装いとして定番です。その他にも、神社の巫女(みこ)装束・武道・茶道のお点前などで、その美しい姿を見られます。
女性用袴の種類

ひとくちに女性用の袴といっても、歴史的背景や用途、形状によって、実はさまざまな種類が存在します。
現代の私たちにとって馴染み深いものから、特定の場面や装束でのみ見られる伝統的なものまで、そのバリエーションは豊かです。
代表的なものとしては、主に以下の4つが挙げられます。
● 女袴(おんなばかま)
● 巫女袴(みこばかま)
● 捻襠切袴(ねじまちきりばかま/ねじまちはかま)
● 切袴(きりばかま)
上記のうち、とくに現代の卒業式などで華やかな装いとして広く親しまれているのが「女袴」でしょう。
多彩な色や柄が揃い、晴れの日の定番となっています。
これら4種類の袴は、それぞれどのような特徴をもち、どのような歴史を背景に、どのような場面で用いられてきたのでしょうか。
一つひとつの袴の個性と、その奥深い世界を詳しく見ていきましょう。
女袴(おんなばかま)
女袴は、現代の女性が着用する袴の代表的なスタイル。股の部分に仕切りがないスカート状の「行灯袴(あんどんばかま)」の一種です。その優雅で凛としたシルエットが大きな魅力となっています。
明治時代に、学問の場で女性が活動しやすくなるよう考案されたのが始まりとされ、当時の女学生の象徴的な装いでした。行灯袴であるため動きやすく、お手洗いなどの際にも配慮された、実用的な作りも特徴です。現代では大学や小学校の卒業式で定番の華やかな衣装として、広く親しまれています。
着付けの際は、胸の高い位置で紐を結び、足が長くすっきりと見えるように調整するのが一般的です。また、男性用の袴にはある、腰を支える硬い「腰板(こしいた)」が付いていない点も、女性用袴の大きな違いといえるでしょう。
巫女袴(みこばかま)
巫女袴は、神社の祭祀(さいし)で神に仕える巫女が着用する、清らかさと格式を象徴する特別な袴です。神職が用いる差袴(さしこ)の一種とされます。
最も代表的な色は、鮮やかながらも深みのある緋色(ひいろ)で、古くより魔除けや生命力を象徴するともいわれ、神聖な儀式に用いられます。ただし、神社や役職によっては、濃紫色(こきむらさき)など、他の色が使われることも。
着用する際は、清浄を表す白無地の白衣(びゃくえ/はくい)の上からこの巫女袴を履き、袴の紐は体の正面でリボン結びにするのが一般的な着装法です。
捻襠切袴(ねじまちきりばかま/ねじまちはかま)
捻襠切袴は、主に位の高い女性神職などが正装として着用する、特殊な形状の袴です。その名は、腰から股にかけて付けられる「襠(まち)」という布の処理方法に由来するともいわれます。
一般的な巫女袴の多くが、スカート状の行灯袴であるのに対し、こちらは股が分かれたズボン状の構造です。最大の特徴は、腰回りに設けられた「襠」で、これがゆとりと活動性に加え、独特のシルエットを生み出します。
この襠の構造により、優雅さを保ちつつ非常に動きやすく、巫女袴とは異なる活動的で威儀(いぎ)を正した立ち姿となるのが特徴。複雑な儀式での動きにも対応しやすいとされています。
切袴(きりばかま)
切袴は、主に明治時代以降、宮中の女官たちが日常の正装として着用した「袿袴(うちきばかま)装束」に用いられた袴の一種です。この袿袴装束は、平安時代以来の伝統を受け継ぐ女性の公的な服装であり、切袴はその中で活動性を高めるために生まれた重要な役割を担いました。
切袴の最大の特徴は、従来の袿袴装束で用いられていた、床に長く引きずるほどの裾をもつ「長袴(ながばかま)」を改良した点にあります。明治時代の生活様式の変化や、女性の活動範囲の広がりに対応できるよう、裾を短く切り詰めたのです。この実用的な改良により、活動性が大幅に向上し、宮中での勤めにおける利便性が向上しました。
さらに、当時の近代化の流れを反映し、ときには伝統的な草履ではなく洋靴と合わせて着用されることもあり、和洋折衷の過渡期ならではの装いとして記録に残されています。
男性用袴の種類

ひとくちに男性用の袴(はかま)といっても、その形状や用途によっていくつかの種類に分けられます。
代表的なものとしては、主に以下の3つが挙げられます。
● 行灯袴(あんどんばかま)
● 馬乗り袴(うまのりばかま)
● 野袴(のばかま)
男性用袴の多くに共通する特徴として、後ろ腰部分に付けられる「腰板(こしいた)」があります。
腰板は硬い台形の板で、腰を安定させ、凛(りん)とした美しい立ち姿を保つ重要な役割を担っています。
では、それぞれの袴がもつ特徴を詳しく見ていきましょう。
行灯袴(あんどんばかま)
行灯袴は、スカートのように股が分かれていない筒状の袴で、女性用だけでなく男性用も存在します。男性用の行灯袴は、女性用には通常見られない「腰板」が付いている点が大きな違いです。着付けの際は、腰骨の位置でしっかりと締めることで、すっきりとした立ち姿を作ります。
そのゆったりとした形状から、一般的には正装というよりは、お茶席や書道といった習い事の稽古着として、あるいはリラックスしたいときの和の普段着として好まれるのです。
現代では、一部の男性がお洒落なファッションの1つとして、袴を個性的に着こなす姿も見られます。たとえば、普段の街着として楽しんだり、和装でのパーティーシーンで注目を集めたりするケースも。
馬乗り袴(うまのりばかま)
馬乗り袴は、その名の通り、馬に乗りやすいようにと考案された袴です。ズボンのように股が左右に完全に分かれているのが最大の特徴で、これにより非常に足さばきがよいという実用的な利点があります。
かつては武士の日常的な袴であり、女性が着用した時代もありましたが、次第に男性の活動的な袴として定着しました。現代においては、その動きやすさから剣道・弓道・居合道といった、各種武道の稽古着や試合着として広く用いられています。
その他、神職の日常の袴や、能楽・狂言などの伝統芸能の舞台衣装、あるいは活動的な仕事着として活用されることもあります。
野袴(のばかま)
野袴は、馬乗り袴の裾を足首の動きに合わせて細く仕立て、よりズボンに近い形状にした、非常に活動的な袴です。その姿は、時代劇『水戸黄門』一行の旅装束などでご覧になった方も多く、馴染み深いかもしれません。
元々は江戸時代に、武士や庶民が長距離の道中や野良仕事、山仕事といった屋外での活動の際に着用したものです。動きやすさと裾の汚れにくさ、そして防寒などの実用性が重視されていました。
現代でも、作務衣(さむえ)と合わせて気軽に着用されています。実用性をさらに高めたポケット付きのものや、洋服の生地で作られたものなど、日常に取り入れやすい工夫が凝らされた野袴も人気を集めています。
袴の買取相場は高い?低い?

「手持ちの袴、実際のところ買取相場は高いの?それとも低いの?」
袴の買取相場について、多くの方が気になる点でしょう。
結論から申し上げますと、袴の買取相場は、素材(正絹・化学繊維など)や袴の種類(礼装用・普段用など)、保存状態などによって大きく異なります。
有名作家の作品であるか、さらには人気の柄や色合いや証紙の有無など、多岐にわたる要因によって大きく変動するため、一概に相場の高低を断言するのは非常に難しいのが現状です。
たとえば、男性の第一礼装とされる上質な絹で作られた黒紋付羽織袴、状態のよい有名作家の作品や希少価値の高いアンティーク袴などは安定した需要が見込めるため、高価買取となる可能性を十分に秘めています。
一方、買取価格が低くなりがちな袴や、買取自体が難しいケースも。
たとえば、普段使いを目的とした化学繊維(ポリエステルなど)で作られた袴や、大量生産により希少価値が低い袴が該当します。さらに、生地にシミ・カビ・破れといった著しい損傷が見られる場合も同様です。これらのケースでは、残念ながら買取価格が大幅に下がったり、買取自体をお断りしたりすることも少なくありません。
あくまで一般的な目安としましては、袴の買取価格は数千円程度から、希少価値の高いものや保存状態が極めてよいものでは数万円、場合によってはそれ以上の評価が付くこともあります。しかしながら、これは非常に大まかな範囲であり、袴は着物の中でも個々のお品物の状態や特性による価格差が大きいため、専門の査定士が現物を拝見しなければ正確な価値判断は困難といわざるを得ません。
ご自身の袴の適正な価値を知り、納得のいく取引をするためには、まず複数の信頼できる着物買取業者に査定を依頼し、提示された金額や説明を比較検討することが賢明です。査定により、お手持ちの袴に対するおおよその相場観を掴むとともに、最もよい条件で買い取ってもらえる可能性が高まります。
その大切な比較検討の選択肢の1つとして、ぜひ「福ちゃん」をお加えいただければ幸いです。
経験豊富な査定士が、お客様の袴に込められた想いと価値をしっかりと拝見し、ご満足いただける買取価格をご提示いたします。
ぜひお気軽に、ご相談ください。
高価買取になりやすい袴とは

前述のとおり、黒紋付羽織袴のように特定の種類の袴は高価買取が期待できますが、それ以外にも高価買取となる可能性を秘めた袴はございます。
「もしかしたら私の袴も?」と、お考えの方もいらっしゃるかもしれません。
実は、いくつかの重要なポイントを押さえた袴は、高価買取となる可能性を十分に秘めているのです。
● 素材の質
● 保存状態
● デザインと希少性
● サイズの汎用性
これらの特徴が、なぜ高価買取につながるのでしょうか。
ここからは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。ぜひお手持ちの袴と照らし合わせながら、その価値を見極めるための参考にしてください。
素材の質
袴の素材として最高級と評価されるのは、正絹(しょうけん:絹100%)です。
天然素材である絹ならではの美しい光沢、しっとりとした滑らかな肌触りはもちろん、優れた通気性や保湿性も兼ね備えています。米沢の「神代平(じんだいひら)」や、仙台の「仙台平(せんだいひら)」といった、伝統的な織物で知られる有名産地の正絹袴は、素材の質の高さでも知られています。
多くが熟練の職人による手仕事で丁寧に作られるため、希少価値が非常に高く、高額査定が期待できる代表例といえるでしょう。
このように、上質な素材は袴そのものの品格を大きく高め、買取価格にも重要な影響を与えます。
保存状態
お持ちの袴の保存状態は、査定額を左右する非常に重要な要素の1つです。
虫食いやシミ・カビ・生地の破れや擦れといった目立つ損傷がなく、全体的に清潔で美しい状態であれば、高価買取につながりやすくなります。保存状態が査定額に影響を与えるのは、次に袴をご利用になる方が快適に着用できる状態であることと、専門業者による修繕の必要がないため、再販時の価値が高いと判断されるためです。
年に数回の虫干しや適切な防虫剤の使用、さらに1枚ずつたとう紙に包んで湿気を避けて丁寧に保管するといった、日頃の適切なお手入れが高価買取の鍵を握ります。
デザインと希少性
袴の買取価格を決定づける重要な要素として、織りの種類や柄の希少性も挙げられます。
たとえば、「神代平(じんだいひら)」や「仙台平(せんだいひら)」といった特定の産地の伝統的な織物は、その卓越した技術と格式の高さから安定した人気を誇ります。とくに精緻な縞柄などは、需要が高い傾向です。また、柄のデザインは流行に影響を受けることもあり、縁起のよい古典柄や、時代を象徴する人気の柄などは評価が高まることも。
ただし、一時的なトレンドに偏ったデザインは、時期を逃すと価値が変動する可能性もあるため、早めの査定が有利な場合もあります。たとえば、夏用の「絽(ろ)」の袴であれば、需要が高まる春先から初夏にかけて査定に出されるのがオススメです。
サイズの汎用性
袴の丈も買取価格に影響するポイントで、一般的には短いものよりも、ある程度長さのある方が高価買取になりやすい傾向です。
その主な理由は、丈の調整のしやすさと、「汎用性の高さ」にあります。具体的には、短い袴は後から丈を出すのが難しいのに対し、長い袴は長身の方だけでなく、仕立て直しをすることで小柄な方にも合わせることが可能です。近年、国内外で着物や袴のレンタル需要が増えていることも、サイズ調整のしやすい長めの袴の価値を高めている一因といえるでしょう。
一般的に、袴の丈の長さが95cm以上あると、幅広い需要に応えられるサイズとして評価されやすくなります。
袴の買取方法は3種類

袴の買取には、どのような方法があるのでしょうか?
● インターネット
● リサイクルショップ
● 着物の買取業者
袴を買い取ってもらう場合、これら3種類の買取方法が考えられます。
査定額は、どれも同じではありませんので、どの買取方法を選ぶかがポイントです。
ベストな買取方法を選ぶために、それぞれのメリットとデメリットも含めた特徴を解説していきます。
インターネット
インターネットの買取とは、フリマアプリやネットオークションのことです。
インターネットを介した買取の場合、手軽に始められ、袴の値段をご自身で決められるのがメリットといえます。
デメリットは、売れるのに時間がかかったり、買い手が付かなかったりすること。そのほか、出品から発送までのすべてをご自身で行う必要があり、時間と労力の消費も覚悟しておかねばなりません。
売れた際も、売り上げから数パーセントの手数料が引かれるのが一般的です。
リサイクルショップ
手軽に利用できるリサイクルショップですが、袴を売る際には少し注意が必要です。多くの品目を扱うため、着物や袴の専門知識をもつ査定士が常に在籍しているとは限りません。
着物専門の査定士がいない場合、袴の価値が見落とされる可能性も。袴の価値を正しく判断するには、素材や状態、市場の需要などを見極める、専門的な知識が必要不可欠です。
リサイクルショップに袴の買取を依頼するなら、事前に「着物や袴の買取実績が豊富か」「和装の専門知識をもつ査定士が在籍しているか」といった点を確認しておきましょう。
着物の買取業者
着物の買取業者は、3つの買取方法の中で、最も袴の買取に最適といえます。
着物専門の査定士が査定を行うため、価値のある袴であれば、高価買取につながるからです。リサイクルショップで重量査定された袴でも、着物の買取業者で査定すると、高値が付く可能性も考えられます。
持ち込み・出張・宅配など、買取方法も複数あり、ご自身に合った方法を選択できるのも強みです。
ただし、袴の買取を受け付けていない業者もあるため、確認してから査定を依頼するようにしましょう。
袴の買取で知っておきたい注意点

袴の買取を検討中なら、次の注意点は必ずチェックするようにしてください。
● ポリエステルの袴に注意
● 丈の短い袴に注意
これらは、袴の買取における落とし穴であり、袴の買取の難しさでもあります。
再度、お手持ちの袴に当てはまらないか、しっかりと確認してみましょう。
ポリエステルの袴に注意
袴の素材がポリエステルの場合、買い取ってもらえたとしても、買取額が低いのが一般的です。
ポリエステルは大量生産が可能な素材でもあり、価値が低いとみなされています。新品でさえ値段が安いため、買取となれば、さらに安くなるのは避けられません。
また、ポリエステルの袴は、買い取ってもらえない可能性が高いため、注意が必要です。査定を依頼する前に、袴の買取が可能かどうか、確認しておくようにしましょう。
丈の短い袴に注意
丈が短い袴の買取を検討される際も、要注意です。
丈が短いと身長の高い方に対応できないため、汎用性が低く、買取額が下がってしまいます。袴は丈が短いよりも、長い方が需要があるのです。
丈の短い袴を買取に出す場合、羽織や草履などと一緒にセットで査定してもらうなど、高価買取のために工夫してみるのもよいでしょう。
また、短い丈の基準は、一般的に95cm未満です。
袴の買取は「福ちゃん」にご相談ください
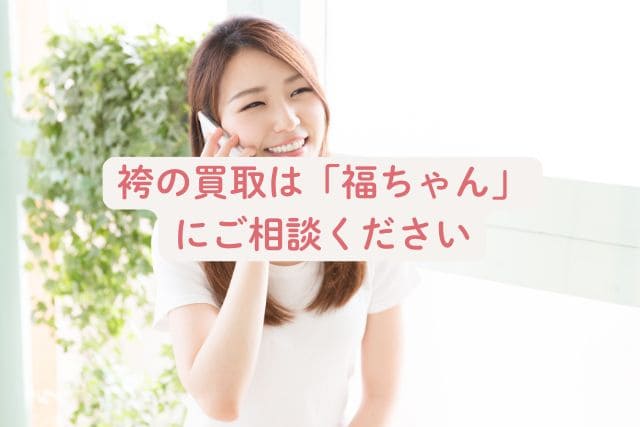
袴の買取をご検討の際は、着物の専門知識と豊富な買取実績をもつ福ちゃんに、ぜひご相談ください。
福ちゃんでは、着物全般に加え、袴に精通した査定士がお客様の大切な袴の価値を一点一点丁寧に見出し、ご納得いただける価格をご提示いたします。
お客様の大切にされてきたお気持ちを尊重し、その思い出と共に次の方へと大切に橋渡しすることが、私たち「福ちゃん」の使命です。
ご提示した査定額にご満足いただけない場合でも、キャンセル料や手数料は発生いたしません。どうぞご安心して、まずは無料査定をご利用ください。
福ちゃんでは、2つの買取方法をご用意しております。お客様自身で店舗までお持ち込みいただく「店頭買取」と、専門の査定士が無料でご自宅までお伺いする「出張買取」です。
お客様のライフスタイルやご希望に合わせて、最も便利な方法をお選びいただけます。
まとめ
この記事では、袴の買取を成功に導くための、さまざまな情報について詳細に解説いたしました。
袴は一般的な着物と比較して着用シーンが限られるため、その価値を正しく評価してもらい、納得のいく買取を実現するには、いくつかの重要なポイントが存在することをご理解いただけたかと存じます。
「この袴にはもう価値がないかも」
「他店では袴の買取を断られた」
そのようにお悩みのある袴がもしお手元にございましたら、どうかそのままにせず、ぜひ一度福ちゃんにご相談ください。福ちゃんでは、豊富な知識を有する専門の査定士が、どのような袴であっても丁寧に拝見し、その可能性を最大限に引き出すお手伝いをいたします。
たとえ古いお品物や、多少の傷みが見られるものであっても、思わぬ価値が見つかることも決して珍しくありません。
お客様のご都合に合わせて選択可能な「出張買取」と「店頭買取」は、いずれも査定料やキャンセル料などは一切無料です。
大切な袴の価値を確かめたい、安心して依頼できる買取業者を探している、そのようなときはぜひ、お気軽に福ちゃんまでお問い合わせください。
専門のスタッフが、お客様からのご連絡を心よりお待ちしております。