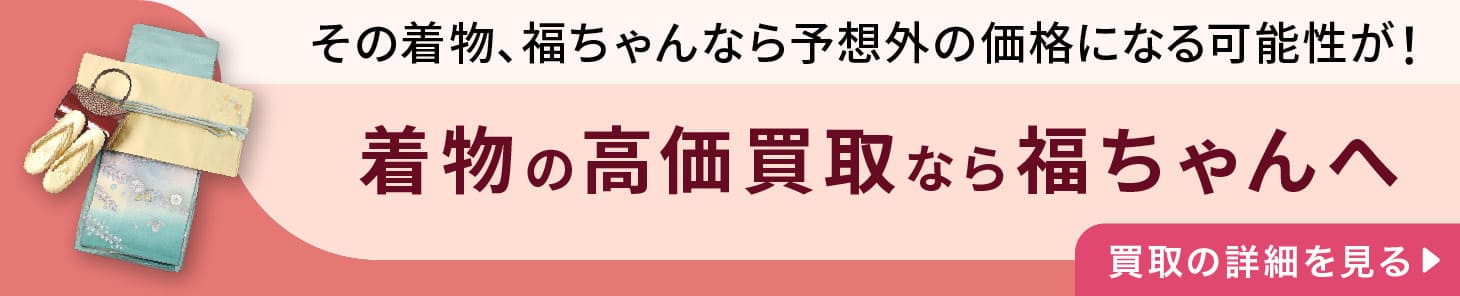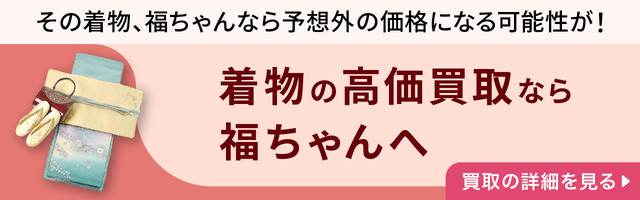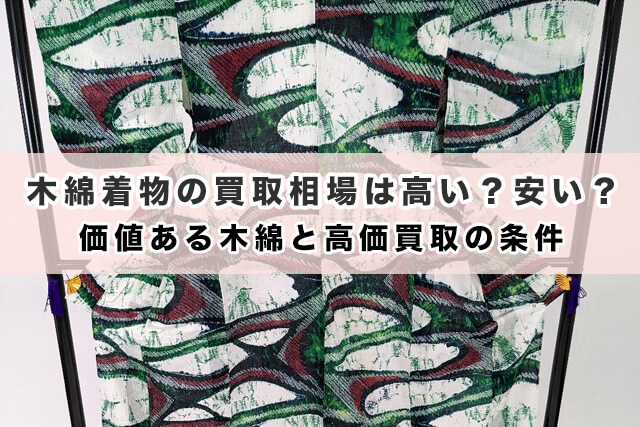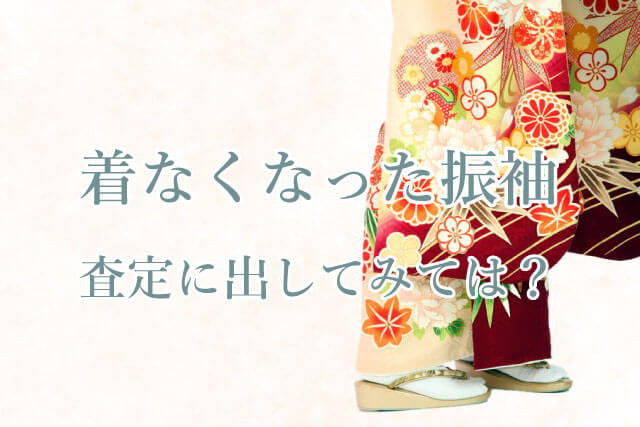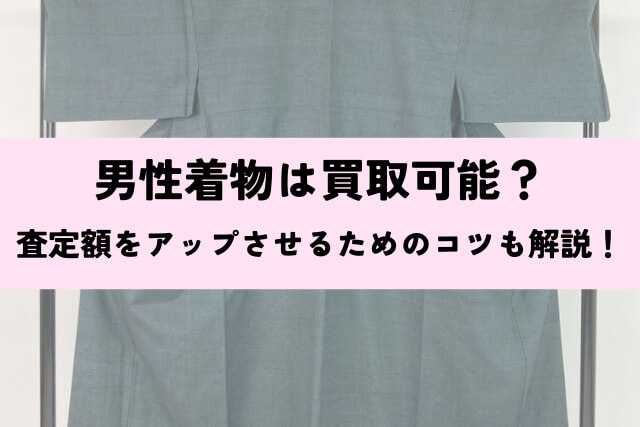- 着物
- 2025.06.18
着物用ショールのマナーを徹底解説|結婚式や室内での注意点とは?

寒さ対策はもちろん、着物姿を一層華やかに見せてくれる「着物ショール」。
非常に便利な和装アイテムですが、「結婚式で使ってもいいの?」「室内ではいつ外すのが正解?」といった、着物ショールのマナーに関する不安をお持ちの方も、多いのではないでしょうか。
この記事では、着物ショールのマナーで失敗しないためのポイントについて、わかりやすくに解説します。
シーン別の具体的なマナーから、美しい所作、TPOに合わせた選び方まで網羅しました。すべてお読みいただくことで、どのような場面でも自信を持ってショールをまとい、ワンランク上の着物姿を演出できるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
まずは結論!着物ショールで押さえるべき【基本マナー3箇条】
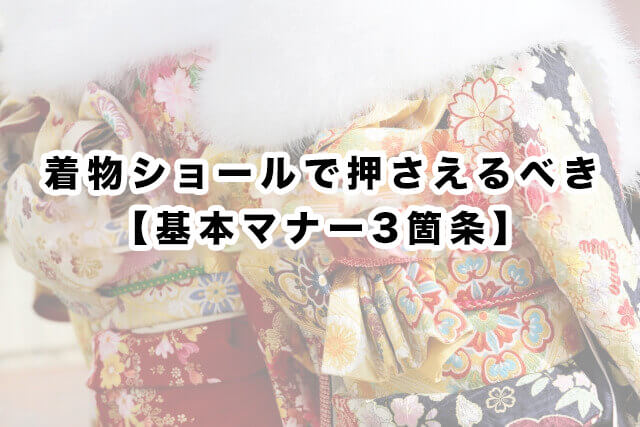
着物ショールのマナーは多岐にわたりますが、まずは「これだけは知っておきたい」という大切な基本を3つご紹介します。
この3点を意識するだけで、ショールの扱い方がぐっと洗練され、立ち居振る舞いにも自信が生まれます。
1.屋内では外すのが大原則
コートと同じく、ショールは屋外での防寒具です。建物に入る前に外すのが基本マナー。例外もありますが、まずは「室内では身につけない」と覚えておきましょう。
2.美しい所作を心がける
羽織るとき・外すときは、ショールの端が地面につかないよう、スマートに行うのが美しい所作です。周囲への配慮にもつながります。
3.TPOに合わせた「素材」選びが最重要
とくにフォーマルな場では、素材選びがマナーの要です。お祝いの席で避けるべき素材もあるため、シーンに合わせた選び方が大切になります。
この3つの基本は、あらゆるシーンで応用できる、いわばショールマナーの「土台」です。この土台をしっかり理解しておけば、結婚式やお茶会といった特別な場面でも、自信を持って振る舞えます。
次の章からは、この基本を元に、より具体的なシチュエーションごとのマナーを詳しく解説していきます。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

【シーン別】これで迷わない!着物ショールの完全マナーガイド
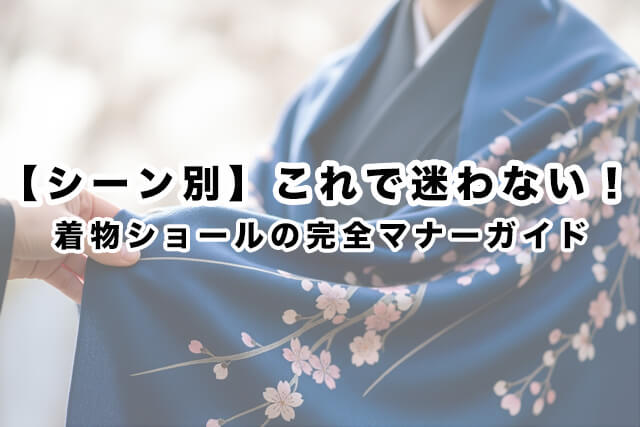
着物ショールをご利用される際、ユーザーが最も悩む、具体的なシーンごとのマナーを解説します。
結婚式・披露宴でのマナー【要注意】
お祝いの席である結婚式では、とくに注意が必要です。
1.会場に入る前にクロークへ預けるのが基本
ショールは防寒具のため、受付を済ませる前に外し、クロークに預けるのが最も丁寧なマナーです。
2.動物の毛皮(ファー)は必ず避ける
最も注意したいのがファー素材です。お祝いの席で「殺生」を連想させるため、リアルファーはもちろん、フェイクファーも避けるのが無難です。成人式では定番ですが、結婚式ではマナー違反と覚えておきましょう。
3.許容されるケースは?
ガーデンウェディングや、会場の空調が効きすぎて寒い場合など、主催者側からアナウンスがあれば着用が許されることもあります。その場合でも、ラメやレース、上質なカシミヤなど、ドレッシーで華やかな素材を選びましょう。とはいえ、自己判断はせず、基本はクロークに預けるのが最も安心です。
お茶会でのマナー
静寂と清らかさを重んじるお茶会では、ショールの扱いにも特別な配慮が求められます。
・「塵を持ち込まない」のが基本精神
茶室は神聖な空間とされています。コートなどの上着と同様に、屋外の塵やホコリがついている可能性のあるショールは、待合(まちあい)か、茶席に入る前に必ず外すのが鉄則です。これは、亭主が整えた清浄な空間への敬意を示す大切なマナーです。
・毛羽の飛ぶ素材は厳禁
ウールやアンゴラ、毛足の長いファーなど、毛羽が舞いやすい素材は厳禁です。舞った毛がお茶碗に入ったりお菓子についたり、畳を汚したりすることは、お席を汚すことになり、亭主や他のお客様に大変失礼に当たります。滑らかな質感のカシミヤやシルクなど、毛羽立ちの少ない素材を選びましょう。
・外したショールは風呂敷に包んで
外したショールは、きれいに畳んで風呂敷に包むか、大きめの手荷物袋にしまい、席に持ち込む荷物の下に置くのがスマートです。他の人の邪魔にならないよう、コンパクトにまとめておきましょう。
観劇・食事会・お買い物などカジュアルなシーン
気軽なお出かけでは、比較的自由にショールを楽しめますが、それぞれの場所に応じた心遣いが、着物姿をさらに美しく見せます。
・観劇・コンサートでは
ロビーで外し、クロークがあれば預けるのがスマートです。座席では、後ろの人の視界を遮らないよう、椅子の背もたれにかけるのは避けましょう。コンパクトに畳んで膝の上か、足元に置いたバッグの上に置きます。空調が寒い場合は、膝掛けとして使うとよいでしょう。
・お食事会では
お店に入る際に外し、きれいに畳んで椅子の背もたれにかけたり、空いている席があればそこに置かせてもらったりします。お料理の匂いや汚れが気になる場合は、お店の方に相談して預かってもらうか、大きめの袋に入れておくと安心です。膝掛けにすると、食べこぼしで汚してしまう可能性もあるため注意しましょう。
・お買い物では
ショールを羽織ったままだと、商品に引っかけてしまったり、両手が使いにくかったりすることがあります。ストールクリップで留めておくと動きやすくなりますが、混雑した店内では外して畳んでおくのが無難です。
ここまでお伝えしたように、シーンに応じたマナーを心得ておけば、気後れすることなくお出かけを楽しめます。
さらに、ショールの扱い方そのものを美しくすることで、着物姿はより一層洗練された印象になります。
次の章では、思わず目で追ってしまうような、優雅で美しいショールの扱い方について、詳しく見ていきましょう。
【立ち居振る舞い編】美しいショールの扱い方マナー

ショールの扱い方1つで、着物姿の印象は大きく変わります。
マナーを知っていることはもちろん大切ですが、その所作にこそ、その人の内面的な美しさや品格が表れるものです。優雅な立ち居振る舞いは、周囲への細やかな気配りから生まれます。
美しい羽織り方・外し方
ショールを羽織る際は、慌ただしくバサッと広げるのではなく、両手で静かに持ち、着物の襟足にふわりと乗せるようにします。肩のラインに沿わせ、裾が地面に触れないよう、また周囲の人に当たらないよう配慮するその一手間が、奥ゆかしさを演出します。
動作はゆっくりと、あくまで自然に行うのがポイントです。
外すときも同様に、肩から滑らせるように静かに下ろします。片方の手でショールを押さえながら、もう片方の手でゆっくりと引き抜くようにすると、帯結びを崩す心配もなく、洗練された立ち居振る舞いとなります。
外した後のショールの扱い方(畳み方・持ち方)
外したショールもまた、美しく扱うのが大人のマナーです。
持ち歩く際はまず縦に半分に折り、次に横へと数回、生地の厚みに合わせて折り畳み、腕にかけられるくらいの大きさに整えます。
立っている間は、その畳んだショールをそっと左腕にかけておくと、右手は自由になり、所作が美しく見えます。
お席に着いた際は、畳んだまま膝の上に置くか、汚れないようバッグの上に置きましょう。椅子の背もたれにかけるのは、ずり落ちたり、隣の人の邪魔になったりする可能性があるため、避けるのが無難です。膝掛けとして使うのは、あくまで親しい間柄でのカジュアルなシーンに限定するのが、スマートな選択といえるでしょう。
【選び方編】TPOに合わせた色・素材のマナー

着物用のショール選びは、マナーとセンスが問われる大切なポイントです。TPOにふさわしい1枚が、着物姿を一層と引き立て、ご自身の品格をも表現します。
ここでは、自信を持ってコーディネートを楽しむための、色と素材の選び方を詳しく見ていきましょう。
「素材」で品格をまとう
TPOに合わせたショール選びで最も重要なのが「素材」です。フォーマルな場では、着物の格を引き立てる上質さが求められます。
滑らかな手触りのカシミヤや、深い光沢が美しいベルベットは、羽織るだけで装いに気品を添えてくれるでしょう。シルクや、繊細なラメ・刺繍が施されたものも、華やかな席にふさわしい選択です。
一方で、普段のお出かけであれば、素材選びはさらに自由になります。温かみのあるウールやコットン、季節によってはさらりとした麻など、着物とのコーディネートを楽しみながら、自分らしいお洒落を表現できます。
「色」で印象を操る
色選びも、全体の印象を左右する大切な要素です。フォーマルなシーンでは、主役である着物との「調和」を意識しましょう。
着物の地色や柄に含まれる一色をショールで拾ったり、クリーム色やシルバーグレーといった「淡く上品な同系色」を選んだりすることで、全体が優しくまとまり、洗練された着こなしが完成します。
一方、カジュアルな場面では、ショールを「差し色」として効かせるのも素敵です。あえて着物と対照的な色を選ぶことで、遊び心のある粋なコーディネートが楽しめます。
【季節別】オススメの色と素材
日本の美しい四季を着こなしに取り入れるのも、着物の楽しみ方の1つです。季節の移ろいに合わせてショールの色や素材を選ぶことで、より一層深みのあるコーディネートが完成します。
ここからは、季節別のオススメの色と素材をお伝えします。
秋から冬へ(10月~3月頃)
木々が色づき、空気が澄んでくる秋から冬にかけては、こっくりとした深みのある色がよく映えます。深緑やボルドー、紺といった落ち着いた色合いは、この時期の着物に温かみを添えてくれるでしょう。素材は、見た目にも暖かなカシミヤやベルベット、ウールなどが最適です。
春の訪れ(4月~5月頃)
やわらかな日差しが心地よい春には、心も華やぐような軽やかな色を選びたいものです。桜色やラベンダーといったパステルカラーや、明るいライトトーンのショールが、春の装いを優しく彩ります。素材も、光沢の美しいシルクや薄手のカシミヤ、軽やかなコットンシルクなど、見た目にも軽やかなものが季節に馴染みます。
夏の涼やかさ(6月~8月頃)
日差しが強くなる夏には、見た目にも涼を感じるショールが活躍します。白や水色、黄緑といった爽やかな色は、清涼感を演出してくれます。素材は、通気性に優れた麻(リネン)や、絽(ろ)や紗(しゃ)といった透け感のあるものがオススメです。汗ばむ季節の肌触りも快適で、冷房が効いた室内での温度調節にも重宝します。
このように、着物ショール1枚を選ぶにも「TPO」や「季節感」を考えることで、マナーを守りつつ、より高度なお洒落を楽しめます。
とはいえ、実際にショールを使っていると「こんなときはどうするの?」という細かな疑問も出てくるものです。
次の章では、そうしたよくある質問にお答えしていきます。
着物ショールに関するQ&A

マナーや選び方について解説してきましたが、最後に、多くの方が抱く細かな疑問にお答えします。
Q1. ショールを留めるクリップやブローチは使ってもいい?
A. はい、お使いいただけます。
ショールがずり落ちるのを防ぐストールクリップや、装いのアクセントになるブローチは便利なアイテムです。ただし、フォーマルな場では、着物の格に合わせた上品で小ぶりなデザインを選びましょう。大切なショールの生地を傷めないマグネット式のものも人気があります。
Q2. 洋服用のストールで代用できる?
A. はい、もちろん代用可能です。
最近では、和装用にこだわらず、洋服用の大判ストールを素敵に合わせる方も増えています。ただし、静電気が起きやすい化学繊維のものは、着物にまとわりついて歩きにくいことがあるため注意が必要です。カシミヤやウール、シルクといった天然素材のものが、着物との相性も良くオススメです。
Q3. ショールのお手入れはどうすればいい?
A. 素材に合わせたお手入れが、ショールを長持ちさせる秘訣です。
ウールやカシミヤなどの獣毛素材は、着用後に洋服ブラシで優しくホコリを払い、毛並みを整えましょう。シルクは非常にデリケートですので、専門のクリーニングに出すのが最も安心です。いずれの素材も、保管する際は湿気を避け、防虫剤を忘れずに入れておくことが大切です。
ここまで、「ショールに関するよくある疑問」についてお答えしました。細かな点まで知っておくことで、より安心して着物のお洒落を楽しめるでしょう。
それでは最後に、この記事でお伝えした「大切なポイント」をもう一度おさらいしましょう。
まとめ

この記事では、着物用ショールのマナーを、基本から応用まで詳しく解説しました。
多くのルールがあり難しく感じたかもしれませんが、大切なのは以下の3つのポイントです。
・ショールは屋外でまとい、屋内では外すのが大原則
・結婚式では殺生を連想させるファー素材はNG
・羽織る・外す・畳むといった所作を美しく
これらのポイントを押さえるだけで、どのようなシーンでも自信を持ってショールを使いこなせ、着物でのお出かけがさらに楽しくなるはずです。マナーは、ご自身と周りの人が心地よく過ごすための心遣いです。ぜひ素敵な着物ショールをまとって、特別な1日をお過ごしください。
マナーを学んで素敵に着こなせるようになると、お手持ちの着物や和装小物を見直す良い機会にもなります。そのなかで、もし「この着物はもう着ないかな」と思われるお品物がございましたら、その際は、着物の買取を専門とする福ちゃんに、ぜひ一度ご相談ください。
福ちゃんには、着物の専門知識を豊富に持った査定士が在籍しており、お客様のお品物の価値を正確に見極めます。
ご納得いただける査定額をご提示できるよう努めますので、一度お問い合わせいただけますと幸いです。