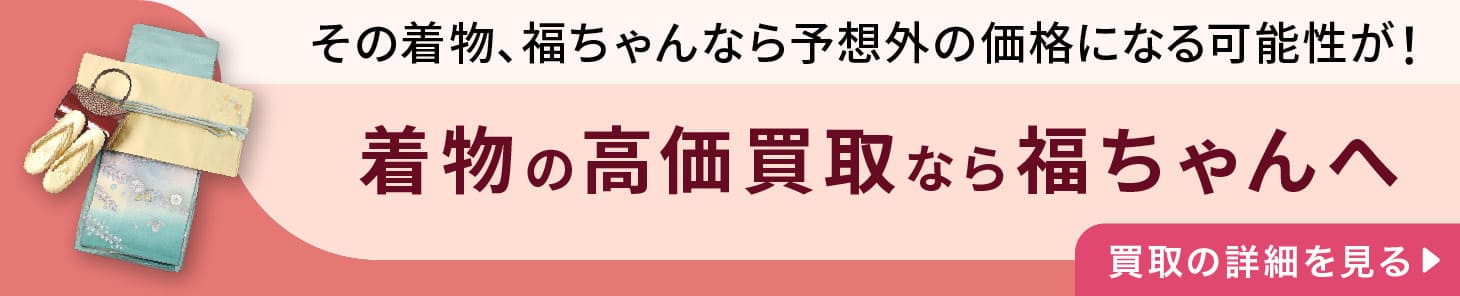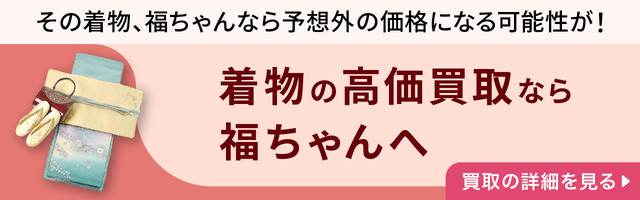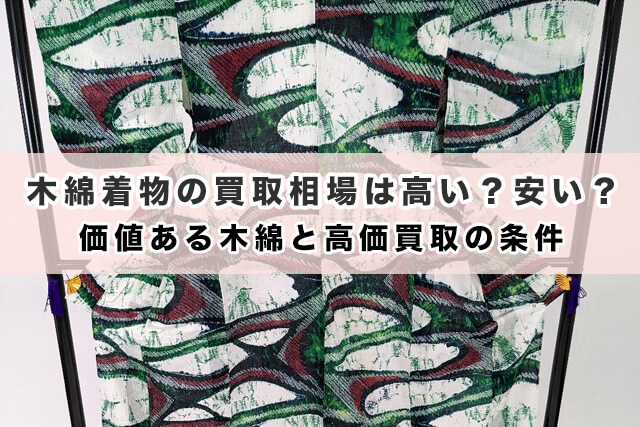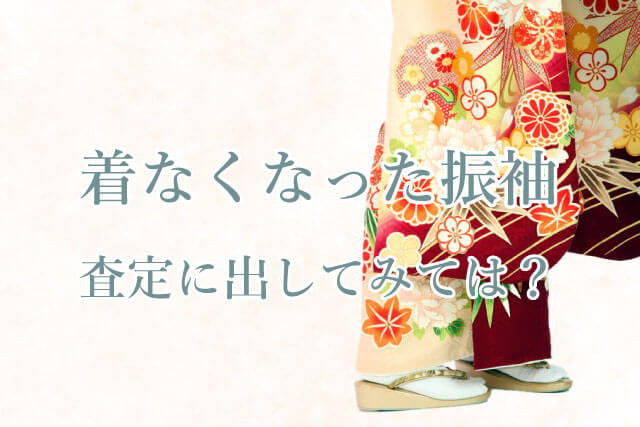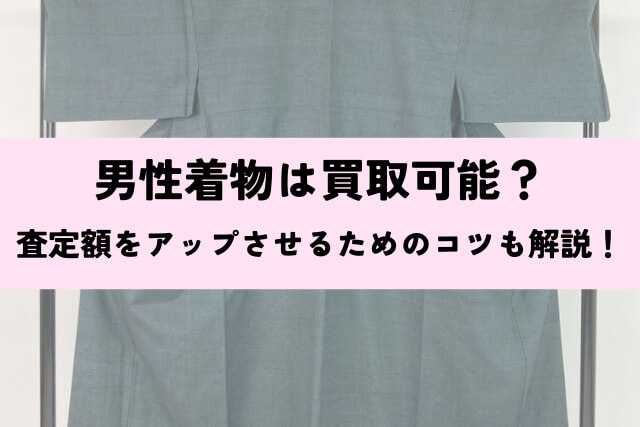- 着物
- 2025.07.16
「銘仙」と「ほかの着物」の見分け方|銘仙の産地ごとの違いとは?
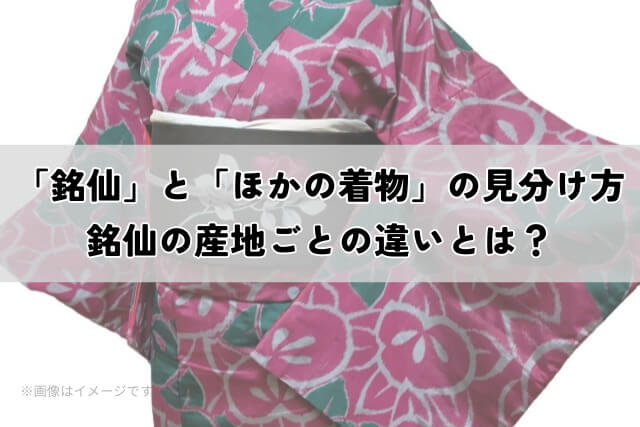
「銘仙とほかの着物の見分け方がわからない」
「銘仙の産地ごとの見分け方を知りたい」
この記事では、こうした疑問をお持ちの方に向けて、銘仙の見分け方についてわかりやすく解説していきます。
銘仙は、「絣」の技法を用いた平織りの絹織物の一種です。
着物の中には、銘仙と混同されやすいものもあり、その違いが正しく認識されていないことも。
さらに、銘仙はかつて全国各地に有名な産地があったものの、それぞれの特徴まではあまり知られていません。
記事を最後までお読みいただくと、銘仙とほかの着物の違いや、銘仙の産地ごとの違いが明確になり、自信を持って着物を選べるようになります。
ぜひご覧ください。
銘仙とはどのような着物?
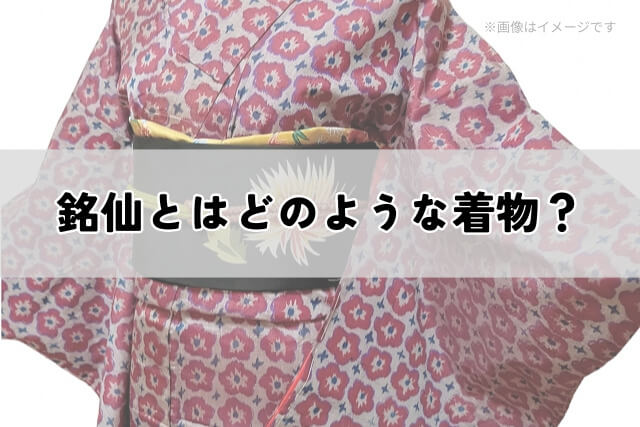
銘仙(めいせん)を見分けるためには、まず「銘仙そのものの特徴を理解する」ことが大切です。
銘仙は、「絣」の技法を用いた「平織り」の絹織物の一種です。
「絣」は、あらかじめ染め分けた糸を使って織り上げることで、多彩な柄を表現する技法。「平織り」は、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に交差させる、最も基本的な織り方です。
鮮やかな色使いと大胆な柄が特徴で、大正から昭和初期にかけて、女性の「お洒落着」や「普段着」として大流行。当時、経糸と緯糸の色を意図的にずらし、色の境界が滲んだように見える、柔らかな表情に仕上げたものがとくに人気を博しました。
第二次世界大戦後、ファッションの主流が洋服へと移り、銘仙の生産量は減少します。
しかし近年、「大正ロマン」や「アンティーク着物」への注目の高まりと共に、その人気が再燃しています。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

「銘仙」と「ほかの種類の着物」の見分け方
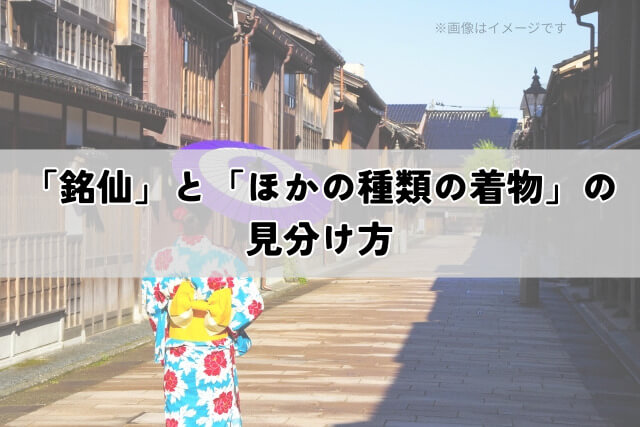
銘仙と混同されやすい着物として挙げられるのが、「紬(つむぎ)」と「お召し」です。
銘仙・紬・お召しは、「先染めの織物(糸を染めてから織る)」という点で共通していますが、それぞれの見た目や風合いに明確な違いがあります。
「紬」との違い
紬は、真綿から手で紡いだ「紬糸(つむぎいと)」で織られた織物です。
紬糸には節があり、それが生地の表面に素朴で自然な凹凸を生み出すため、ざっくりとした風合いに仕上がります。着始めは少し硬く感じられることもありますが、着込むほどに体に馴染み、非常に丈夫なため「親子三代にわたって着られる」といわれるほど長持ちします。
一方、銘仙はくず繭などを機械で紡いだ「絹紡糸(けんぼうし)」などから作られ、紬糸は用いません。銘仙の糸は撚りが甘いため、紬ほどの耐久性はありませんが、その分、生地が滑らかで光沢があります。
着用できる期間が限られているからこそ、流行を取り入れた大胆で華やかな色柄が多いのも銘仙の特徴です。
「お召し」との違い
「お召し」は、糸に強い撚りをかけた「強撚糸(きょうねんし)」を緯糸に用いて織り上げた織物です。
強撚糸で織られたお召しの生地表面には、「シボ」と呼ばれる細かな凹凸があり、これによりシャリ感のある風合いと、品格のある輝くような光沢が生まれます。
一方、銘仙は基本的に平織りのため、お召しのようなシボはありません。銘仙にも滑らかな光沢はありますが、お召しが持つシボ由来の上質な光沢とは異なり、よりカジュアルな印象となります。
銘仙の産地ごとの見分け方
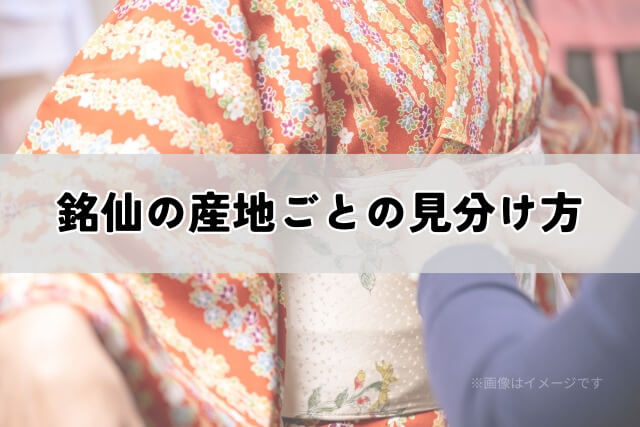
銘仙はかつて全国各地で作られていましたが、生産量がピークだった1930年代を境に産地は徐々に減少。
現在では、以下が「5大産地」として知られ、それぞれに技法や作風の違いがあります。
・足利銘仙
・秩父銘仙
・桐生銘仙
・伊勢崎銘仙
・八王子銘仙
ここからは、各産地の銘仙の特徴を見ていきましょう。
足利銘仙(栃木県)
足利銘仙は、鮮やかでありながらも「柔らかな印象の作風」が特徴です。
古くから織物が盛んだった足利では、大量生産によって安価な銘仙を実現。
さらに、一流画家の美人画をポスターや絵葉書にするなど、優れたマーケティング戦略でその名を全国に広め、1939年には生産高日本一となりました。
秩父銘仙(埼玉県)
秩父銘仙は、「ほぐし捺染(なっせん)」という独自の技法が特徴です。
これは、経糸を仮織りしてから型染めし、一度ほどいてから本織りする技法で、1908年に特許を取得。表裏の区別なく染まるため、裏返して仕立て直しができるという利点があります。
角度によって色が変わる「玉虫効果」が見られることもあり、2013年に国の伝統的工芸品に指定されました。
桐生銘仙(群馬県)
「西の西陣、東の桐生」と称されるほど織物が盛んな桐生(きりゅう)では、非常に質の高い銘仙が作られました。
桐生はお召しの産地としても名高く、その技術を活かしてお召しに使う強撚糸で織られた「お召し銘仙」が特徴で、他の産地にはないシャリ感と高級感を持ちます。
伊勢崎銘仙(群馬県)
伊勢崎銘仙は、かつて全国の銘仙出荷量の約半分を占めるほどの一大産地でした。
特徴は、「併用絣(へいようがすり)」という高度な技法です。経糸と緯糸の両方に同じ型紙で柄を染め、織りながら柄を合わせていくため、非常に鮮明で多色使いの複雑なデザインを表現できます。
この技法は他産地ではほとんど見られず、1975年に国の伝統的工芸品に指定されました。
八王子銘仙(東京都)
古くから「桑都(そうと)」と呼ばれ、織物の一大産地であった東京・八王子市で作られていたのが、八王子銘仙です。
八王子銘仙は、経糸に色糸、緯糸に白糸を使い、凹凸のある地紋を織り出す「ピタン織(ドビー織)」が最大の特徴です。
現在は生産されていませんが、その技術はネクタイなどに受け継がれています。
銘仙の着用シーン

「銘仙の見分け方はわかったけれど、どのようなシーンで着用すべきかわからない」
こうした疑問をお持ちの方も、いらっしゃるかもしれませんね。
銘仙は「普段着」に分類される着物であり、格としては「紬」よりも下、「浴衣」よりは上と位置づけられています。友人とのランチや観劇など、気軽なお出かけに適しています。
銘仙をお洒落に着こなすには、合わせる帯や小物の「格」を揃えることも大切です。
帯は、カジュアルな「名古屋帯(なごやおび)」や、より気軽に結べる「半幅帯(はんはばおび)」が基本となります。金糸銀糸を多用した豪華な袋帯は、着物の格と合わないため避けましょう。
帯締めや帯揚げ、半襟なども、アンティークらしい遊び心のある色やデザインのものを選ぶと、銘仙ならではの大正ロマンの雰囲気をより一層楽しめます。
一方で、結婚式や式典などの格式の高い場では、着用しないよう注意が必要です。
中古買取市場における銘仙の価値
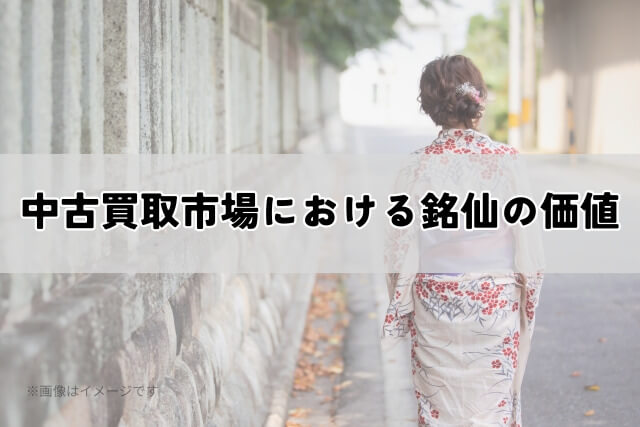
ご不要になった銘仙を買取に出される際、その価値が気になる方も多いでしょう。
結論から申し上げますと、銘仙は普段着に位置付けられるため、全体としては高価買取になるケースは稀です。しかしながら、近年のアンティーク着物ブームにより、銘仙の人気は高まっています。
とくに、伝統的工芸品に指定されている「秩父銘仙」や「伊勢崎銘仙」は、デザイン性も高く人気があるのです。
担い手不足から現在ではほとんど生産されておらず、希少価値を持つ銘仙も少なくありません。こうした背景もあり、状態が良く希少性の高い銘仙であれば、思わぬ価値が付くことも十分に考えられます。
ご自宅に眠る銘仙が、果たしてどれほどの価値を持っているのか。
その答えは、専門家の「確かな目利き」によって初めて明らかになります。
福ちゃんでは、着物の専門知識と豊富な買取経験を持つ査定士が、お客様の大切なお品物の価値を正しく見極めます。
まずは、無料査定でその価値を知ることから始めてみませんか?
価値が高く評価されやすい銘仙の特徴
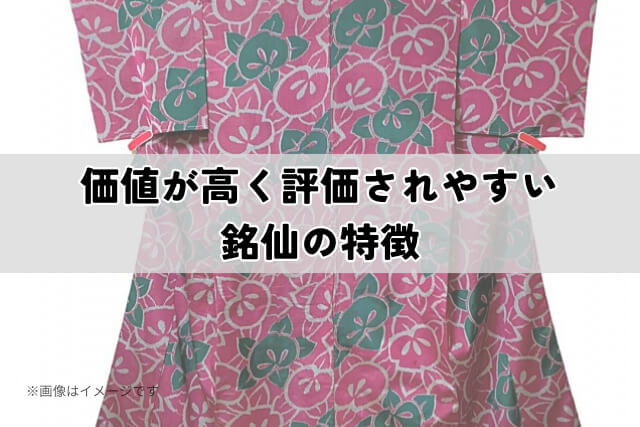
お持ちの銘仙が、価値の高いものかどうかを「事前に把握するためのポイント」をご紹介します。
・保存状態が良い
・証紙が付いている
・仕立てのサイズが大きい
保存状態が良い
着物の価値を左右する最大の要素が「保存状態」です。
シミやカビ、虫食いや色あせがなく、購入時に近い鮮やかさが残っているものは高く評価されます。状態を良くするためにクリーニングに出される方もいらっしゃいますが、買取額がクリーニング代を上回らない可能性もあるため、無理なお手入れはご不要です。
タンスにしまっているだけでも着物は少しずつ劣化します。「手放そう」と思った時が一番の売りどきですので、できるだけ早く査定に出すことをオススメします。
証紙が付いている
証紙は産地や品質を証明する、いわば「保証書」です。
「伝」の文字が入った伝統証紙は、価値の高い銘仙であることの目印になります。この証紙は、国の伝統的工芸品に指定されている「秩父銘仙」や「伊勢崎銘仙」などに見られます。
証紙がなくても買取は可能ですが、あればプラス査定の重要な要素となりますので、忘れず一緒に提出しましょう。
仕立てのサイズが大きい
昔の着物は現代の女性に比べて小さめに作られていることが多く、身丈150cm未満などのサイズは着用できる方が限られるため、査定額が伸び悩む傾向があります。
一方、サイズが大きいものは、仕立て直しなどで対応できるため需要が高く、積極的に買取が行われます。
サイズによって評価が変わることも覚えておきましょう。
銘仙の買取をお考えなら「福ちゃん」へ

銘仙の見分けがいかに奥深く専門知識を要するか、ここまでお読みいただき、おわかりいただけたかと存じます。
産地ごとの技法や、時代の特色によって価値が大きく変わる銘仙は、その違いを正しく判断できなければ、「本当の価値」を見出すことはできません。
だからこそ、「どの業者に査定を依頼するか」が非常に重要なのです。
着物の買取専門店である福ちゃんには、お客様がお持ちの銘仙の価値を正しく見極める、経験豊富な査定士が在籍しています。
・「この着物は買取対象になるのか不安」
・「着物にほつれやシミがある」
・「着物のサイズが小さめだから、値段が付かないのでは」
このようなご不安をお持ちの場合も、どうぞご遠慮なくご相談ください。
専門の査定士がお品物を丁寧に拝見し、全体の価値を漏れなく判断いたしますので、着物買取が初めての方も、安心してご利用いただけます。
査定料やキャンセル料など、お客様にご負担いただく費用は一切ございませんので、「まずは価値だけ知りたい」というご要望も大歓迎です。
まとめ
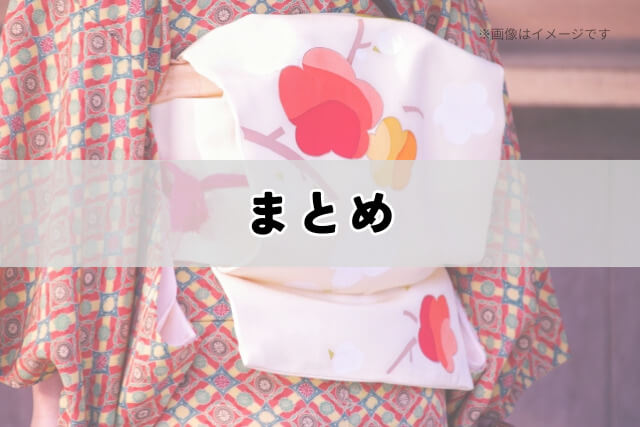
この記事では「銘仙の見分け方」について解説しました。
銘仙は、丈夫な「紬」とは使われる糸が、独特のシボを持つ「お召し」とは織り方が異なります。さらに、「足利」「秩父」など産地ごとの技法の違いも、その価値を大きく左右します。
これらの違いを正確に見分けるのは、専門家でなければ困難です。もし買取をお考えの場合、知識の浅い業者に依頼すると、お持ちの銘仙が持つ本来の価値よりも安く買い取られてしまう恐れがあります。
「銘仙の価値をきちんと見極めてもらいたい」「買取で後悔したくない」とお考えでしたら、ぜひ【買取福ちゃん】にお任せください。
福ちゃんでは、お客様が大切にされてきた想いを受け止めると同時に、なぜその価値になるのか、査定の理由までをしっかりとご説明いたします。
売るかどうかは、価値を知ってからゆっくりお考えください。
お客様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。