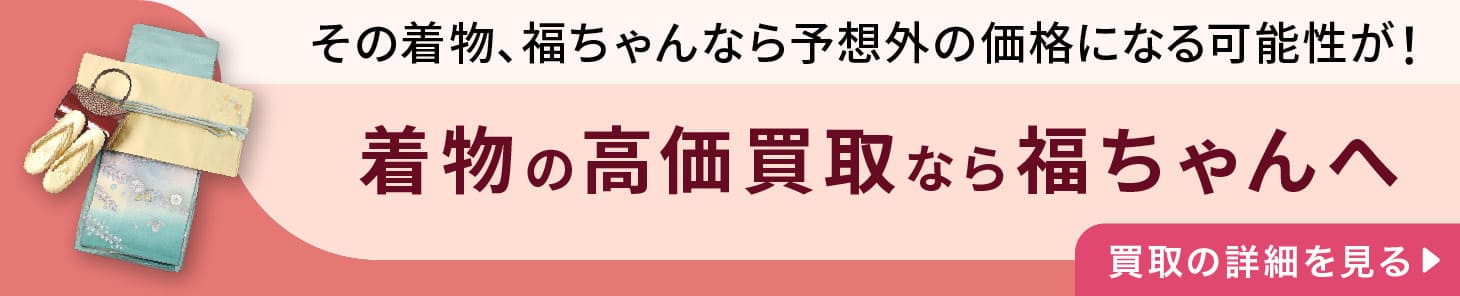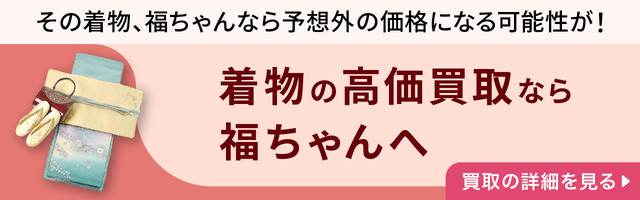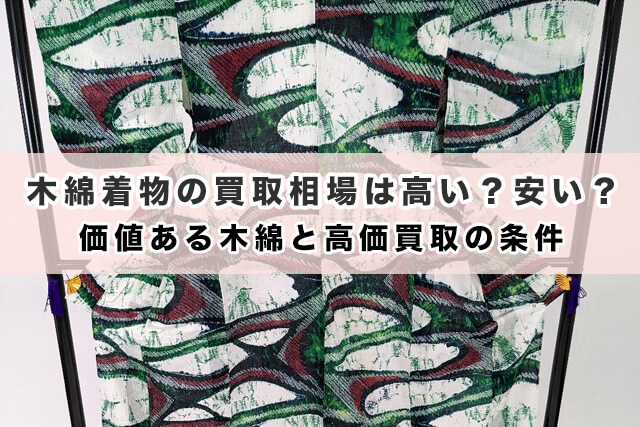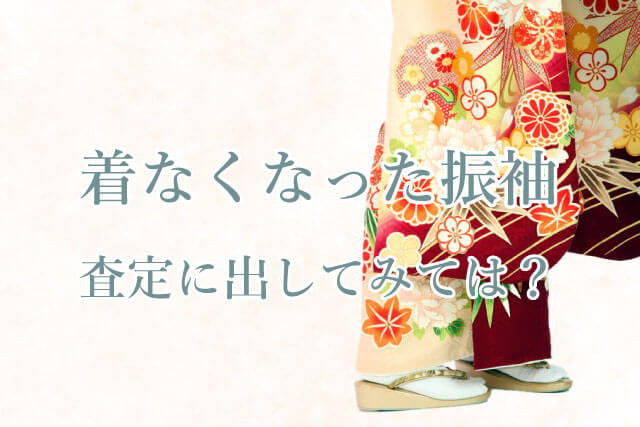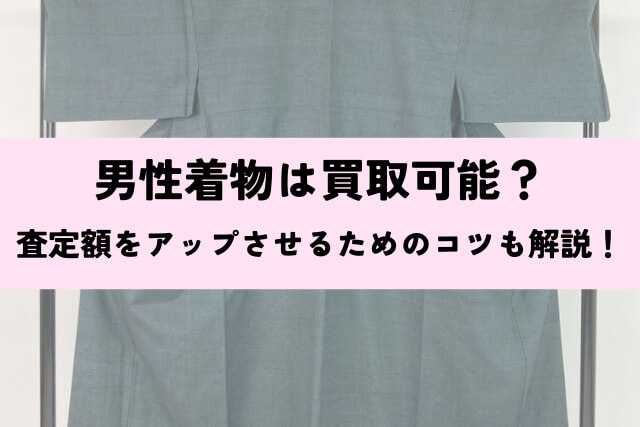- 着物
- 2025.08.01
茜染とは?染め方・効能から歴史、着物の着こなしまで徹底解説
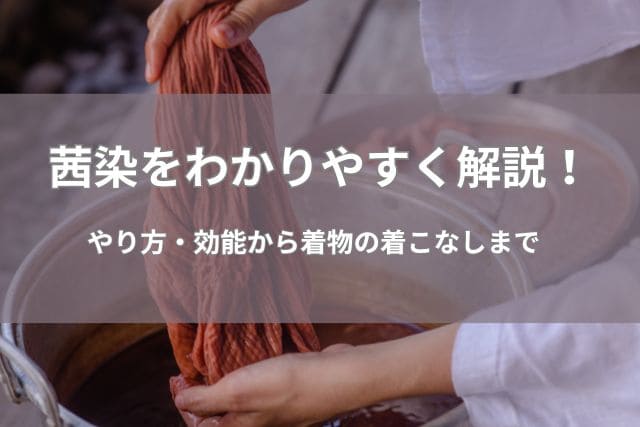
茜染(あかねぞめ)は、日本で古くから伝わる草木染めの一種です。
茜染の魅力は、まるで夕焼け空を映したかのような、深くも優しい「茜色」を楽しめる点にあります。原料となる「アカネ」は、古くは薬草としても用いられていたため、その効能に興味を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、茜染のやり方や歴史、期待される効能について、さまざまな角度から詳しく解説します。
茜染の着物に興味をお持ちの方や、お手持ちの着物の売却を検討されている方にも役立つ情報をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
茜染とは?|植物の「アカネ」で染める古来の染色技法

茜染とは、アカネ科のつる性多年草「アカネ(茜)」の根を煮出した染料液で布を染める、古くから伝わる染色技法です。
その歴史は非常に古く、古代から世界各地で用いられてきました。
日本では、佐賀県の吉野ヶ里遺跡から日本アカネの色素が発見されています。このことから、弥生時代にはすでに、茜染が行われていたと考えられています。
茜染で染められた色は、一般的に黄色みがかった赤色です。赤色といっても、ベージュに近い淡い色から茶色がかった深い色まで、その色合いは多彩に存在します。
色合いが多彩なのは、アカネの根を煮出す時間や回数、そして発色と色を定着させるために用いる「媒染剤(ばいせんざい)」の種類によって、さまざまな表情が生まれるためです。
また、日本の国旗「日の丸」の赤色は、かつて茜染で染められていたという説も知られています。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

茜染の原料「アカネ(茜)」とは?

茜染の原料であるアカネは、日本の本州・四国・九州の野山に自生する、つる性の多年草です。茎は四角形で、節ごとに4枚の葉が四方に向かって生えるのが特徴です。茎には小さなトゲがあり、他の植物などに絡みつきながら成長します。
根を乾燥させると赤くなる性質を持つことから、「赤根(あかね)」と名付けられたといわれています。
秋から冬にかけて収穫されるアカネの根は、世界で最も古い赤色染料の1つとされ、古くは染料としてだけでなく、薬草としても重宝されていました。
現在では、染料用にインド茜や西洋茜なども栽培されています。
茜染に期待される効能とは?

茜染の原料であるアカネは、その根を天日干ししたものが「茜根(せんこん)」という生薬として、漢方にも用いられています。
ここでは、アカネそのものの薬効と、茜染を身につけることで期待される効能について見ていきましょう。
アカネの薬効は活血と止血
アカネの根を乾燥させたものは「茜根(せんこん)」と呼ばれ、漢方の世界では古くから「血(けつ)」に関する不調を整えるための、重要な生薬として扱われてきました。
その主な働きが「活血」と「止血」という、一見すると正反対の作用です。
▼ 活血作用
血行を促進し、滞ってしまった血の流れ(瘀血:おけつ)をスムーズにする作用です。血の巡りが改善されることで、月経不順や生理痛、打撲による内出血といった不調の緩和に用いられてきました。体を温める効果も期待されています。
▼ 止血作用
出血を穏やかに止める作用で、とくに体の内側からの出血に有効とされます。不正子宮出血や鼻血のほか、血尿や喀血(かっけつ)などに用いられてきました。
興味深いのは、この2つの作用が「アカネの根の使い方」によって変わる点です。
一般的に、生のまま用いると血を巡らせる「活血」の働きが、黒焼き(茜草炭:せんそうたん)にして用いると、出血を止める「止血」の働きが強まるとされています。
このようにアカネは、状態に応じて血を動かし、またあるときは止めるという、生命活動の根幹に関わる重要な役割を担ってきたのです。
茜染は「女性のお守り」?
草木染めは身につけることで、「植物の薬効を皮膚から取り入れられる」と、古くから信じられてきました。
茜染の場合、血行を促進する活血作用が期待されることから、とくに女性に適しているといわれています。
月経不順や生理痛の緩和、婦人病の予防といった願いを込めて、古くは赤ちゃんの産着や女性の腰巻にも使われていました。また、血行促進や体温上昇を期待し、男性の間でも茜染の赤いふんどしが用いられていた歴史があります。
燃えるような茜色は、視覚的にも私たちに元気と活力を与えてくれます。
気分が沈みがちな日や、大事な場面で力を発揮したいときに、茜染の布を肌にまとってみるのも良いかもしれません。
時代を彩ってきた茜染の歴史

古代から人々の暮らしに寄り添ってきた茜染。その用途は時代と共に移り変わってきました。
ここでは、時代背景を交えながら茜染の歴史を振り返ります。
弥生時代|卑弥呼も愛した色
稲作が伝わり、日本で本格的な生産が始まった弥生時代。この時代の代表的な遺跡である吉野ヶ里遺跡からは、出土した繊維から日本アカネの色素が発見されています。
また、中国の歴史書『魏志倭人伝』には、邪馬台国の女王・卑弥呼が魏の皇帝へ「絳地縐(あかききぬのちぢみ)」を献上したという記述があり、これが茜染の絹布ではないかと考えられています。
飛鳥時代|高貴な位を示す色
中央集権国家が形成された飛鳥時代、聖徳太子が定めた「冠位十二階」により、役人の位階が冠の色で区別されるようになりました。
位の高い順に、紫・青・赤・黄・白・黒の濃淡で序列が示され、茜で染められた緋色(ひいろ)系の赤色は、紫と青に次ぐ高位の色として用いられました。
奈良時代|万葉集に詠まれた情景
貴族文化や芸術が花開いた奈良時代には、茜染の色合いが和歌にも詠まれています。『万葉集』には、額田王(ぬかたのおおきみ)の有名な、一首が収められています。
「あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る」
この歌の冒頭にある「あかねさす」は枕詞で、茜色に照り映える美しい情景を表現しています。
平安時代|武士の誇りを染める
平安時代の律令制度においても、役人の位階によって着用できる衣服の色(位色)が定められていました。茜染による緋色は、四位の「深緋(こきひ)」と、五位の「浅緋(うすあけ)」として用いられました。
また、東京都の武蔵御嶽神社(むさしみたけじんじゃ)に現存する、国宝「赤糸威鎧(あかいとおどしよろい)」の威糸(おどしいと)は、鮮やかな茜染で染められています。
今なお、その美しい色合いを確認できます(※明治時代の補修で一部に鉱物染料が使われ、部分的に退色しています)。
江戸時代|「日の丸」を染めた色
江戸時代末期、黒船来航を機に日米和親条約が締結されると、日本の船舶を示す国籍標識が必要となりました。
そこで、「日の丸」が日本の総船印として制定されますが、このとき薩摩藩主・島津斉彬が幕府に進言し、福岡藩の秘伝とされた筑前茜染で染められたという説が伝わっています。
茜染をする前に|「媒染」について
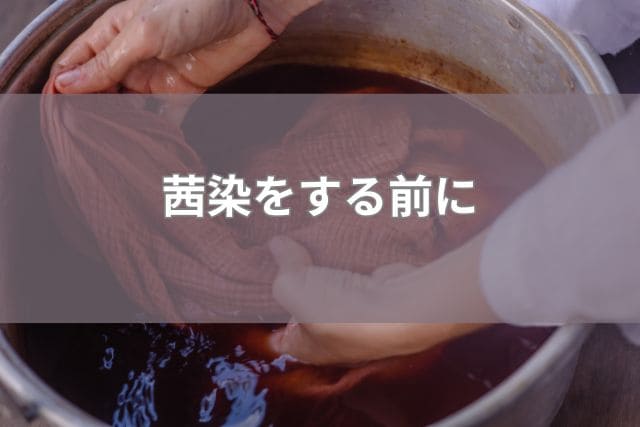
茜染に興味を持つと、「自分でも染めてみたい」と思う方もいらっしゃるでしょう。
美しい茜色に染め上げるには、「媒染(ばいせん)」という工程が欠かせません。
まずは媒染について理解しておくと、作業がスムーズに進みます。
媒染とは?
媒染とは、染料を繊維にしっかりと定着させ、色落ちを防ぐための工程です。
茜染をはじめとする多くの草木染めは、染色だけでは色が定着しにくく、洗濯や日光で色が褪せてしまいます。
そこで、「媒染剤(ばいせんざい)」と呼ばれる液体に浸すことで化学反応を起こし、発色を良くすると同時に、色の定着を促します。
【金属媒染】
・アルミニウム(ミョウバン): 明るく鮮やかな色に
・鉄(錆びた釘を煮出した液など): 落ち着いた渋い色に
・銅:赤みを帯びた色に
【アルカリ媒染】
・木灰汁(もくあくじる)、重曹: 赤みを引き出す
【酸性媒染】
・米酢、クエン酸: 黄みを引き出す
このように、どの媒染剤を選ぶかによって、茜色を鮮やかにしたり渋くしたりと、仕上がりの表情を大きく変えられます。
これが草木染めの面白さであり、重要なポイントです。
先媒染と後媒染|媒染を行うタイミング
媒染を行うタイミングは、染色工程の前か後かによって大きく2種類にわけられます。
それぞれに特徴があり、目指す色合いや素材によって使い分けられます。
● 先媒染(さきばいせん)
布にあらかじめ媒染剤を吸着させてから染める方法です。一般的に、色ムラになりにくく、淡く優しい色合いに仕上げたい場合などに用いられます。
● 後媒染(あとばいせん)
布を染料で染めた後に、色を定着させるために媒染を行う方法です。染料の色合いを直接確認しながら作業できるのが特徴で、濃い色を出したい場合には「染色→媒染」の工程を繰り返すこともあります。
この記事で後ほどご紹介する「茜染のやり方」では、一般的な後媒染の手順で解説していきます。
自宅でできる茜染のやり方
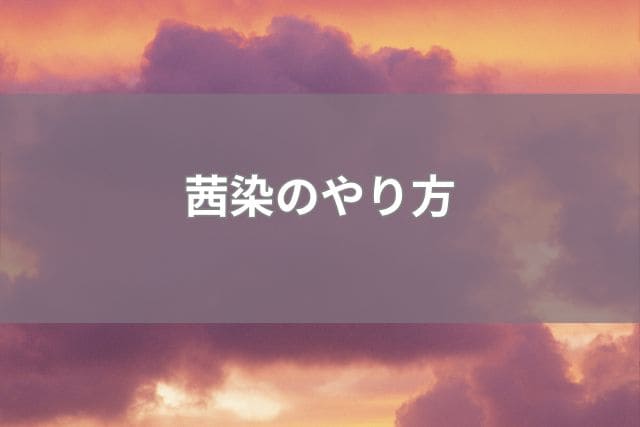
茜染に興味を持ったら、ぜひご自宅で挑戦してみましょう。
ここでは、初心者の方でも失敗しにくい「後媒染」での基本的な手順を、具体的な分量や成功させるためのコツを交えながら詳しく解説します。
1.染める布の準備(精練)
まず、最も重要な下準備です。
新品の布には糊や油分が付着しており、これが染めムラの原因になります。染める前に、これらを洗い流す「精練(せいれん)」という作業を行いましょう。
木綿や麻の布なら、ぬるま湯に中性洗剤(おしゃれ着用洗剤など)を少量溶かし、30分〜1時間ほど浸け置きします。
その後、洗剤が残らないようによくすすぎ、軽く絞っておきます。
2. 材料と道具を準備する
【分量の目安(Tシャツ1枚・約100gを染める場合)】
● 染める布:木綿や絹、麻などの天然繊維 100g
● アカネの根(乾燥): 20g〜30g(染める布の重量の20〜30%が目安)
● 焼きミョウバン(媒染剤): 4g〜8g(染める布の重量の4〜8%が目安)
● 水: 適量
【道具】
● 鍋(ステンレスかホーロー製。染めムラを防ぐため、布がゆったり浸かる大きさが理想)
● 菜箸、ボウル、ざる、計量カップ・スケール
● 不織布のお茶パックやだしパック(アカネの根を入れると後片付けが楽です)
3.染色液を作り染める
アカネの根を細かく刻んでお茶パックに入れ、鍋に水と一緒に入れて火にかけます。沸騰したら弱火にし、コトコトと30分ほど煮出して、染色液(一番液)を作りましょう。
一度アカネのパックを取り出し、染色液をボウルなどに移します。鍋に新しい水と先ほどのアカネのパックを入れ、同様に二番液を煮出しましょう。一番液と二番液を合わせ、染める布がしっかり浸かる量になるように水を足します。
精練しておいた布を染色液に浸し、中火で加熱。沸騰直前で火を弱め、15〜20分ほど、ときどき菜箸で布を動かしながら染めます。色ムラを防ぐため、布は広げて入れ、常に液に浸かっている状態を保ちましょう。
4.媒染液を作り媒染する
布を染めている間に媒染液を作ります。別のボウルに、焼きミョウバン(4g〜8g)を、60℃程度のお湯2リットルによく溶かします。
染め上がった布を軽くすすいで水気を切り、この媒染液に浸しましょう。ここでもムラにならないよう、ときどき布を動かしながら20分ほど媒染させます。
5. 染色と媒染を繰り返す
より濃く、鮮やかな色にしたい場合は、「再度、染色液で煮染め(15分)→媒染液に浸す(15分)」という工程を、好みの色合いになるまで2〜3回繰り返します。
繰り返すほどに、色は深く、定着も強くなります。
6. すすぎと乾燥
好みの色になったら、最後の仕上げです。まず、布をぬるま湯でよくすすぎ、色が出なくなったら水に切り替えてさらにすすぎます。強く絞ると生地を傷めるので、軽く押して水気を切るか、洗濯ネットに入れて洗濯機で1分ほど短く脱水します。
脱水後はすぐにシワをよく伸ばして形を整え、直射日光を避けて風通しの良い「日陰」で干しましょう。直射日光は急激な乾燥と色褪せの原因になるので、必ず陰干ししてください。
完全に乾いたら、世界に1つだけの、オリジナルの茜染の完成です!染めたての色合いや、草木染めならではの優しい風合いをじっくりとお楽しみください。
【完成後の注意点】お手入れについて
茜染は、化学染料と比べてデリケートです。
長く美しい色合いを保つために、以下の点にご注意ください。
● 洗濯
最初の数回は色落ちすることがあるため、他の洗濯物とは分けて単独で手洗いしてください。洗剤は中性洗剤(おしゃれ着用洗剤)を使い、漂白剤やアルカリ性の強い洗剤は変色の原因になるため避けましょう。
● 保管
直射日光や蛍光灯の光が長時間当たると「色褪せの原因」になります。保管される際は、光の当たらない場所にしまいましょう。
少しの手間が、ご自身で染め上げた大切な1枚をより長持ちさせます。
愛情込めて、ぜひ長くご愛用ください。
茜染の着物について

茜染の着物としてとくに有名なのが、岩手県盛岡市で作られる南部茜染(なんぶあかねぞめ)です。
ここでは南部茜染に触れるとともに、「茜染の着物の着こなし方」について解説します。
南部茜染とは
南部茜染は、南部藩の城下町であった盛岡と秋田県の一部で作られる「南部絞り」の代表格です(紫根染と並び称されます) 。
職人が手作業で布を括り、独特の模様を生み出す「絞り」の技法と茜染の素朴な風合いが融合し、透明感と深みを併せ持つ美しい茜色を表現します。
染めには非常に古いアカネの根が必要で、媒染と染色を何度も繰り返すなど、完成までに膨大な時間と手間がかかります。その技術の難しさから、一度は生産が途絶えましたが、1916年(大正5年)に復興を遂げました。
繊細な職人技によって生み出される南部茜染の着物は、現在でも希少価値の高い逸品として高く評価されています。
茜染着物の着こなし|TPOと帯合わせのポイント
茜染の着物をまとう際は、まず着物の「格」を理解することが大切です。
茜染の着物は、その多くが着物全体に模様の入った「小紋(こもん)」と同じ「おしゃれ着」としての位置づけになります。
そのため、ご友人との食事会や観劇、ショッピングなど、普段のおしゃれを楽しむシーンに最適です。反対に、結婚式や式典といった、フォーマルな場での着用は「原則として避ける」のがマナーとされています。
帯合わせについては、以下のようなポイントを意識すると、すっきりと洗練された着こなしが楽しめます。
【メリハリをつける】
小紋のように柄が全体に広がる着物には、黒や白、紺といった反対色の帯を合わせると、全体が引き締まりメリハリの効いた装いになります。
【同系色でまとめる】
着物と同系色の帯を合わせる場合は、ぼやけた印象にならないよう、帯揚げや帯締めにアクセントカラーを取り入れるのがオススメです。
もちろん、茜染の中には振袖や訪問着として作られた格の高い着物もあります。その場合は、格に合わせて金糸や銀糸が織り込まれた袋帯を締めましょう。
このように、茜染の着物は合わせる帯や小物1つで、さまざまな表情を見せてくれます。
手仕事の温かみが感じられる茜染の着物は、大切に長く着続けたい1枚ですが、もしご事情により手放すことをお考えの場合は、いくつか知っておきたい注意点があります。
茜染の着物を買取に出す際の注意点
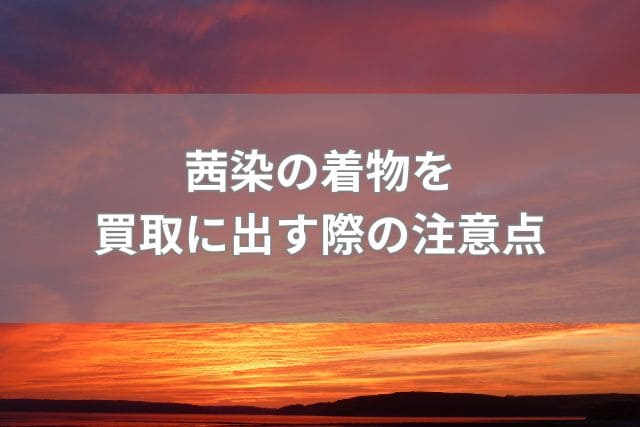
手仕事の温もりが感じられる茜染の着物ですが、その価値は、買取に出す際のほんの少しの知識で、大きく変わってしまうことがあります。
大切な着物を正しく評価してもらうために、必ず押さえておきたい2つの重要なポイントを見ていきましょう。
自己流のお手入れは厳禁
茜染の着物が汚れたからといって、ご自身でお手入れをするのは避けましょう。
天然素材で染められた着物は非常にデリケートで、水洗いだけでも色落ちや変色を起こす可能性があります。せっかくの茜染に色落ちや変色があると、買取額に大きな影響を与えかねません。
多少の汚れが見つかっても自己流でお手入れはせず、そのままの状態で査定してもらうのが最善です。
とくに、南部茜染のような絞り技術を使った着物は、絞りの風合いが損なわれるため、アイロンがけも避けてください。
着物専門の買取業者に依頼する
茜染の着物を買い取ってもらうなら、必ず着物専門の買取業者に依頼しましょう。
なぜなら、着物の知識や経験が豊富な査定士は、茜染の文化的価値や希少性をよく理解しているからです。
そのため、安心して取引ができ、高価買取も期待できます。
リサイクルショップなどでは、専門の査定士が常駐していないケースが多く、茜染が持つ本来の価値を見抜けない可能性が高いといえます。
場合によっては、着物の重さで買取価格が決まるなど、ただ同然で手放すことにもなりかねないでしょう。
大切な茜染の着物だからこそ、その価値を正しく見極めてくれる、着物専門の買取業者を選ぶのが賢明です。
茜染着物の買取は福ちゃんにご相談ください
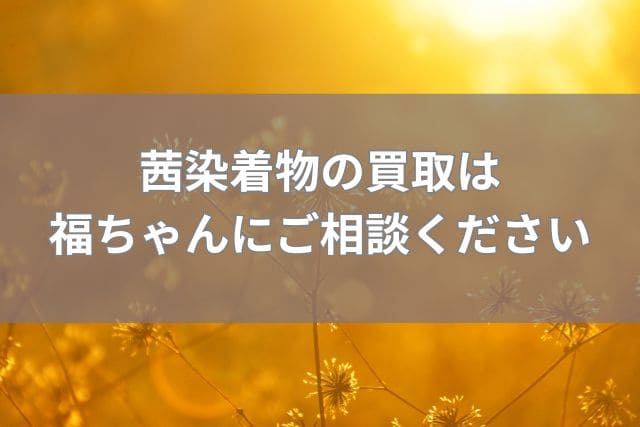
ご自身で大切にされてきた茜染の着物、あるいはご家族から譲り受けた思い出の詰まった1枚。
そのような大切な着物を手放すのですから、「価値を正しく理解してくれる人に見てほしい」と願うのは当然のことです。
福ちゃんには、茜染をはじめとする、草木染めや伝統工芸品に関する深い知識と豊富な査定経験を持つ、専門の査定士が在籍しております。
私たちは、1枚の着物に込められた職人の手仕事や歴史的背景、お客様が紡いでこられた物語まで想像しながら、丁寧に価値を見させていただきます。
お品物の価値を最大限に引き出した査定額をご提示するのはもちろんですが、何よりも大切にしているのは、お客様に心からのご納得をいただいた上でお取引いただくことです。
もし査定額にご満足いただけなかった場合でも、強引な買取を行うことはございません。もちろん、キャンセル料や手数料は一切いただきませんので、どうぞご安心ください。
「まずはこの着物の価値がどれくらいか知りたい」というご相談だけでも大歓迎です。
ご自宅までお伺いする無料の出張買取も、大変ご好評いただいております。大切な茜染の着物のご売却は、ぜひ一度、福ちゃんにお任せください。
まとめ
茜染は、夕日に染まる空のような優しい色合いが大きな魅力です。
その美しさだけでなく、古くから薬草としての効能にも注目されてきました。一度は茜染に袖を通し、その風合いを肌で感じ、茜染でしか出せない色の力を堪能してみてはいかがでしょうか。
そのような魅力あふれる茜染ですが、もしお手元に着る機会のなくなったお品物がございましたら、その価値を次の世代へとつなぐお手伝いをさせていただけませんか。
福ちゃんでは、茜染の着物や帯を積極的に買い取っております。
「もう古いから」「価値がなさそうだから」とあきらめているお品物でも、着物に精通した専門の査定士が拝見することで、思いがけない価値が見つかることも少なくありません。
たとえ他店様でお値段がつかなかった着物でも、あきらめてしまうのは、まだ早いのではないでしょうか。
お客様が心からご納得できる、丁寧なご説明と誠実な査定。それこそが、福ちゃんのお約束です。
まずはお品物の本当の価値を、ぜひ一度お確かめください。