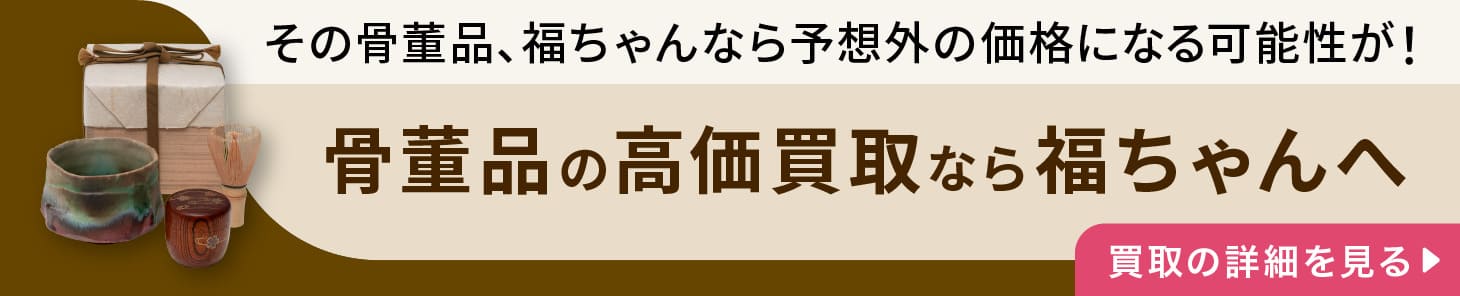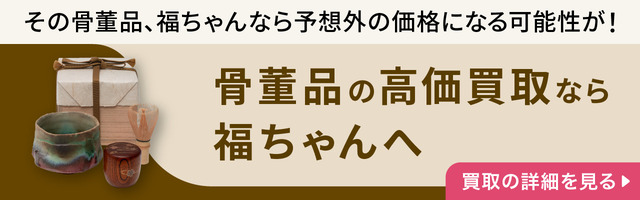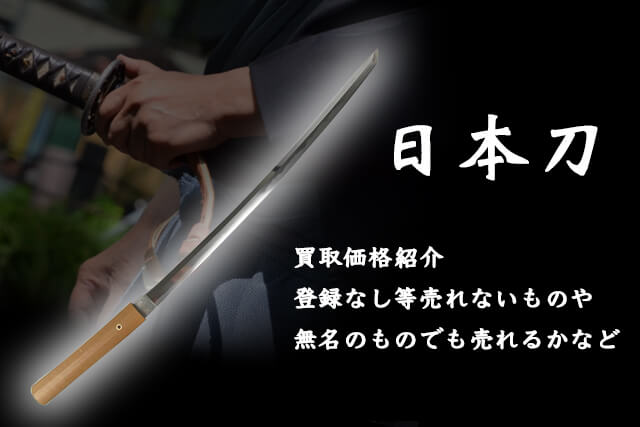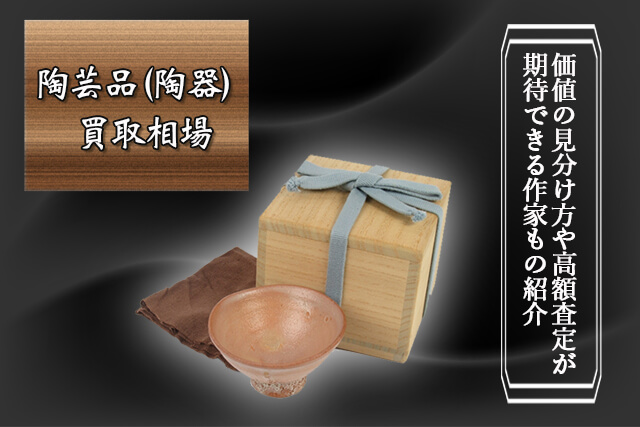- 骨董品
- 2025.06.20
たぬきの置物の効果とは?信楽焼たぬきが有名になった理由も解説

お店の軒先や玄関で、愛嬌たっぷりの表情で私たちを迎えてくれる「たぬきの置物」。縁起物として、多くの人に愛されている身近な存在です。
とくに有名な「信楽焼のたぬき」は、縁起担ぎのアイテムとして大人気ですが、「具体的にどんなご利益があるんだろう?」「効果を最大にするには、どこに置くのが正解?」と、意外と知らないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、たぬきの置物が持つさまざまな効果から、そのご利益を最大限に引き出す置き場所、そして「なぜ信楽焼のたぬきが日本一有名なのか」という理由まで、わかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、ご自身の願いにぴったりの一体と出会い、日々の暮らしに多くの福を招き入れるヒントが見つかるはずです。
なぜ縁起物?たぬきの置物に秘められた本当の効果

「たぬきの置物は縁起物といわれるけれど、具体的にどのような効果があるのかわからない」
「自分が求めている効果を得られるのか知りたい」
お店の軒先で見かける愛嬌たっぷりのたぬきに、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
たぬきの置物がもたらす縁起の良さは、主に「語呂合わせ」と、その姿かたちに込められた「八相縁起(はっそうえんぎ)」に由来します。
それぞれがどのような幸運を呼び込むのか、詳しく見ていきましょう。
商売繁盛・開運招福のご利益
たぬきの置物といえば、まず思い浮かぶのが「商売繁盛」のご利益です。
このご利益は「他抜き」という、強力な語呂合わせに由来します。
「他(た)」より「抜き」んでるという意味が込められており、ライバルに差をつけ、ビジネスを成功に導くと考えられているのです。
この「他を抜く」という縁起の良さから、学業成就や合格祈願の縁起物としても人気があり、受験を控えたお子さんのために購入される方もいらっしゃいます。
また、たぬきは古くから「福の神」の使いや、里山の「豊かな自然の象徴」として、人々に福を招く存在と信じられてきました。こうした歴史的背景から、家内安全や金運アップといった、暮らし全般の幸せを呼び込む「開運招福の効果」も期待できます。
たぬきの置物は、商売や受験といった勝負事から家庭の幸せまで、幅広く見守ってくれる「心強い味方」なのです。
八相縁起(はっそうえんぎ)
信楽焼のたぬきは、笠をかぶり「徳利(とっくり)」や「金袋(かねぶくろ)」を持っている、おなじみの姿が特徴です。
実は、これらの持ち物や体のパーツの一つひとつに「八相縁起」と呼ばれる、8種類の縁起の良い意味が込められています。
詳細は以下のとおりです。
1.【笠】
常に上から降りかかる、予期せぬ災難や困難から身を守るための「備え」を象徴しています。
2.【笑顔】
お互いに愛想よく接することが、良好な人間関係と商売繁盛につながることを表しています。
3.【目】
周囲の状況に気を配り、物事の本質を見抜く「正しい判断力」の象徴です。
4.【腹】
何事にも動じない「冷静さ」と、いざというときの「大胆な決断力」を兼ね備えるように、との願いが込められています。
5.【金袋】
文字どおり、金運に恵まれ財を成すことを願う、商売繁盛のシンボルです。
6.【徳利】
人との付き合いに欠かせない「人徳」を身につければ、飲食に困らない豊かな生活が送れる、という教えです。
7.【通い帳】
お客様や取引先との「信用」が第一であるという、商売のきほんを示しています。
8.【尾】
何事も終わりが肝心。太くたくましい尾は、終わりよければすべてよし、という「善終」を意味します。
ご自身の願いや目標に合わせて、どのパーツが強調されているかに注目して一体を選ぶのも、「たぬきの置物探しの醍醐味」といえるでしょう。
これほど多くのご利益が込められた、たぬきの置物。
せっかくなら、その効果を最大限に引き出したいものですよね。次の章では、運気をさらにアップさせるための、オススメの置き場所をご紹介します。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

運気アップ!たぬきの置き場所

たぬきの置物自体が縁起物なので、「置き場所はここでなければならない」という厳密な決まりはありません。
しかし、どこに置くかによって、とくに強めたい運気が変わってきます。
ここでは、願い事別にオススメの「たぬきの置き場所」をご紹介します。
・玄関やお店の入り口【商売繁盛・千客万来】
・リビング【家庭円満・家内安全】
・書斎や勉強部屋【学業成就・仕事運アップ】
それぞれの置き場所が持つ意味と、置き方のポイントを見ていきましょう。
玄関やお店の入り口【商売繁盛・千客万来】
商売繁盛や千客万来を願うなら、玄関やお店の入り口はまさに「王道」の置き場所です。
風水において、玄関はすべての運気が入ってくる最も重要な場所。ここに縁起の良いたぬきの置物を置くことで、良い運気やお客様をどんどん招き入れるという考え方があります。
置き方のポイントは、たぬきの顔の向きです。
「外から福を迎え入れる」という意味を込めて、顔を建物の外側に向けてあげましょう。にこやかな笑顔のたぬきは、お店の看板としてお客様を温かくお迎えするメッセージにもなります。
リビング【家庭円満・家内安全】
「玄関に置くのは少し気恥ずかしい……」という方には、家族が集まるリビングがオススメです。
実はたぬきは、オスも子育てに参加するほど夫婦仲が良い動物。その習性から、家庭円満や家内安全の象徴とされています。家族運を司るといわれるリビングに置くことで、家族の絆を深め、家全体の運気を高めてくれるでしょう。
リビングに置く際は、家族に福が向くよう、顔を部屋の内側に向けて置くのが一般的です。家族がいつも目にする場所に置くことで、たぬきの笑顔が日々の暮らしに和みをもたらしてくれます。
書斎や勉強部屋【学業成就・仕事運アップ】
たぬきの「他を抜く」という強力な語呂合わせは、学業や仕事の成果を上げたいときにも心強い味方になります。
集中力を高めたい書斎や、お子さんの勉強部屋に置くことで、目標達成や合格祈願の後押しをしてくれるでしょう。仕事の成功や昇進を願う方にもぴったりの場所です。
机の上に「ミニチュアサイズのたぬき」を置くのもオススメです。仕事や勉強の合間にその愛嬌ある姿を眺めれば、良い気分転換にもなるかもしれません。
「信楽焼=たぬき」の理由

なぜ数ある焼き物の産地の中で、「信楽焼」だけがこれほど強く、「たぬき」のイメージと結びついているのでしょうか。
その背景には、ある「歴史的な出来事」と、この土地ならではの「土の恵み」という、2つの大きな理由が存在します。
きっかけは、昭和天皇への「おもてなし」
「信楽焼=たぬき」のイメージを決定づけたのが、1951年(昭和26年)に昭和天皇が信楽の地を訪れた際の、心温まるエピソードです。
当時、信楽の人々は、日の丸の旗を持たせた信楽たぬきの置物を沿道にずらりと並べ、熱烈な歓迎の意を示しました。その光景に感銘を受けられた昭和天皇が、「幼なとき 集めしからに懐かしも しがらき焼の狸をみれば」という歌を詠まれました。
この出来事が報道を通じて全国に知れ渡り、「信楽たぬき」の名は一躍有名になったのです。
たぬきを生んだ、信楽の「土の恵み」
信楽焼たぬきの文化を根底から支えているのが、この土地ならではの「土の性質」です。
信楽一帯は、数百万年という壮大な時間をかけて移動した「古琵琶湖層」と呼ばれる地層の上にあり、湖の底に堆積した良質な粘土が豊富に採れます。この粘土から作られる陶土は非常に「コシが強い」のが特徴で、粘り気があって成形しやすく、乾燥や焼成の際にも割れにくいという利点があります。
信楽焼たぬきを大きく、そして愛嬌のある立体的な造形を可能にしたのは、まさにこの「土の力」だったのです。
昭和の心温まるエピソードと、大物づくりに適した奇跡の土。この2つが重なり合い、「信楽焼といえばたぬき」という、日本中に愛される文化が花開きました。
信楽焼のきほん【3分でわかる】

たぬきの置物で有名な信楽焼ですが、その本来の魅力をご存じでしょうか。
この章では、多くの人を惹きつけてやまない信楽焼の魅力と、その長い歴史についてご紹介します。
土と炎が織りなす、素朴な魅力
信楽焼の最大の魅力は、豊かな自然の恵みをそのまま焼き締めたような、素朴で温かみのある風合いです。
その魅力は、まず「土の質感」にあります。信楽の土は粒子が粗く、焼き上げると土の息づかいが感じられるような、ざらりとした手触りが生まれます。
次に挙げられるのが、窯の中で薪の灰が降りかかって自然に生まれる、「自然釉(しぜんゆう)」のビードロ(緑色のガラス質)と、炎が直接当たって赤褐色に変化する「火色(ひいろ)」です。
これらは2つとして同じものが生まれない、世界に1つだけの“景色”となり、多くの人々を魅了してきました。
日本で最も歴史ある焼き物の1つ
信楽焼は、日本に古くから存在する代表的な6つの窯、「日本六古窯(にほんろっこよう)」の1つに数えられる、非常に格式高い焼き物です。
その歴史は鎌倉時代まで遡り、約800年もの間、一度も途絶えることなく焼き物が作られ続けてきました。
当初は壺や甕(かめ)といった日用の器が中心でしたが、安土桃山時代には茶の湯の道具として、時の茶人たちに愛されるなど、時代ごとのニーズに応えながら独自の発展を遂げてきたのです。
親しみやすい「たぬきの置物」というイメージの背景には、こうした日本の焼き物の歴史を背負ってきた、奥深い世界が広がっています。
土の温もり、炎の景色、そして800年の歴史。たぬきの置物で知られる信楽焼が、なぜこれほどまでに人々を惹きつけるのか、その理由の一端に触れていただけたのではないでしょうか。
主役は、たぬきだけじゃない!幸運を運ぶ動物たち

たぬきが有名な信楽焼ですが、実はその陰には、同じく幸運を運んでくれる頼もしい仲間たちがいます。
ここでは代表的な縁起物として、「かえる」と「ふくろう」の置物が持つ意味をご紹介します。
かえる【無事かえる・お金がかえる】
その名のとおり、「無事にかえる(交通安全)」や「お金がかえる(金運アップ)」といった、縁起の良い語呂合わせで人気の置物です。
信楽焼のものはとくに「福かえる」とも呼ばれ、古くから親しまれてきました。
また、一度に多くの卵を産むことから「子孫繁栄」の象徴でもあります。玄関に置けばお客様を迎え、お店に置けばお客様がまた帰ってくる(再来店する)ともいわれ、商売の縁起物としても活躍してくれる存在です。
※信楽焼の中には、たぬきの八相縁起のように、体の各部分に縁起の良い意味が込められた、かえるの置物もあります
ふくろう【不苦労・先見の明】
ふくろうは、「不苦労(苦労しない)」や「福来郎(福が来る)」といった語呂合わせから、幸せを運ぶ鳥として大変な人気を誇ります。
その生態もまた、縁起の良さの由来です。たとえば、暗闇でもよく見えるその優れた視力は、「先を見通す力」や「商売のチャンスを見逃さない」力につながると、いわれてきました。
さらに、くるりと回る首は「お金に困らない(首が回らないの逆)」ことの象徴とされ、金運アップのご利益も期待できるでしょう。
信楽焼のふくろうは、ときに「福々浪」と呼ばれ、大きな幸運の波を呼ぶ縁起物として大切にされています。
このように、たぬき以外にも魅力的な縁起物が多数あります。ご自身の願い事や、しっくりくる動物のイメージに合わせて、お気に入りの一体を探してみてはいかがでしょうか。
さよならの前に、ちょっと待って。たぬきの置物の価値と手放し方

大切にされてきた「たぬきの置物」も、引っ越しやお店の代替わりなどで、手放さなければならないときが来るかもしれません。
「愛着があるけど、どうしよう」
「ごみとして捨てるのは、なんだか気が引ける……」
そのような悩みをお持ちではないでしょうか。
実はそのたぬきの置物には、思わぬ価値が眠っているかもしれません。ここでは、後悔しないための2つの手放し方をご紹介します。
【方法1】価値を知る第一歩「買取業者」への査定依頼
まずご検討いただきたいのが、陶器や骨董品を扱う「買取専門業者」に査定を依頼する方法です。
素朴で温かみのある風合いが魅力の信楽焼は、買取市場でも根強い人気があります。その中でも、縁起物として親しまれるたぬきの置物は、お持ちの方も多いのではないでしょうか。
お品物によっては、信楽焼たぬきの置物も買取対象となりますが、価値を正しく見極めるには専門的な知識が必要です。有名作家の作品や骨董的価値のある古いお品物、大型たぬきの置物などは、想像以上の価値を秘めている可能性もございます。
買取業者に依頼する最大のメリットは、こうしたご自身では判断が難しいお品物の価値を、プロの目でしっかりと見極めてもらえる点にあるのです。また、大切にされてきたお品物を次の持ち主へとつなげる、「心のこもった手放し方」でもあります。
私たち「福ちゃん」では、たぬきの置物に限らず、信楽焼の壺や花瓶や食器など、骨董品の買取を強化中です。専門の査定士が、お品物の価値を丁寧に見極め、ご納得いただける査定額をご提示します。
重く運ぶのが大変なたぬきの置物には、査定士がご自宅まで伺う「出張買取」が大変便利です。玄関先に置いたままで査定が可能で、運び出しもお任せいただけます。
査定料・出張料・キャンセル料などの費用は一切頂きませんので、まずはお気軽にご相談ください。
★ 福ちゃんへのご相談はこちら
【方法2】破損している場合は「ごみ」として処分
残念ながら、ひび割れや破損がひどく買取が難しい場合や、値段がつかなかった場合には、ごみとして処分する方法を検討することになるでしょう。
しかし、福を招いてくれた縁起物だと思うと、そのまま捨てることには抵抗を感じますよね。
そのような場合は、まず長年の感謝を伝えることから始めましょう。
きれいな布でほこりを拭き、白い紙や布で丁寧に包むだけでも、気持ちの整理がつきやすくなります。人によっては、塩を少量振りかけてお清めをすることも。
処分のルールは自治体によって大きく異なり、一般的には「不燃ごみ」や、サイズによっては「粗大ごみ」として扱われます。お間違いのないよう、必ずお住まいの自治体のホームページなどで分別方法を確認してください。
また、陶器は割れると危険です。収集作業員の方が安全に扱えるよう、新聞紙などで厚く包み、ごみ袋に「キケン」や「陶器」と明記しておくと、より親切でしょう。
どうしてもごみとして出すのが忍びないという方は、神社やお寺での供養を検討するのも1つの手です。人形供養と同様に、置物の供養を受け付けている場合がありますので、近隣の寺社に問い合わせてみるのも良いかもしれません。
「うちの信楽焼たぬきは価値があるかな?」と思いでしたら、処分してしまう前にぜひ一度、「福ちゃん」までご相談ください。
たぬきの置物はもちろん、ご自宅に眠っている他の信楽焼(壺・花瓶・食器など)もあわせて、専門の査定士が価値を拝見します。
まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。お店の軒先や玄関にいる、愛嬌たっぷりのたぬきの置物を見る目が、今日から少し変わったのではないでしょうか。
そのユーモラスな姿の裏には、「他を抜く」という商売繁盛の願いや、幸せを願う「八相縁起」という深い意味が込められています。そして、その文化が信楽の地で花開いたのは、心温まる歴史的なエピソードと、豊かな土の恵みがあったからでした。
ぜひ、ご自身の願いにぴったりの一体を見つけて、ご自宅やお店に多くの福を招き入れてみてください。
もしご自宅で役目を終えたり、置き場所に困ったりしているたぬきの置物があれば、処分される前に一度、その価値を確かめてみませんか?
私たち「福ちゃん」は、たぬきの置物に限らず、お客様が大切にされてきた信楽焼の価値を見出し、次の方へとつなぐお手伝いをしています。専門知識が豊富な査定士が、お客様のお品物を丁寧に拝見し、その価値をしっかりとご説明いたします。
査定料やキャンセル料などの発生はなく、サービスのご利用はすべて無料です。
「うちのたぬきは価値があるかな?」といった、小さな疑問だけで十分です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。