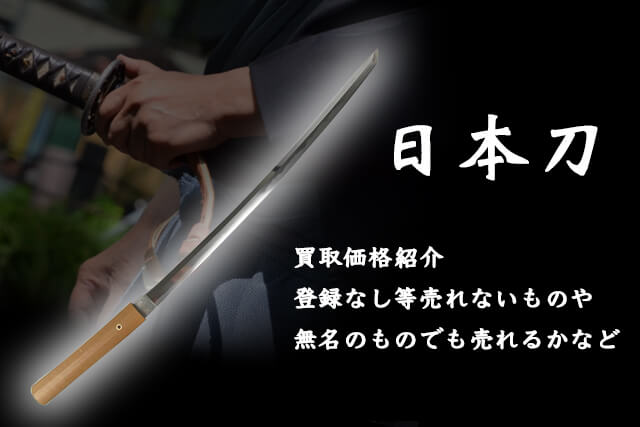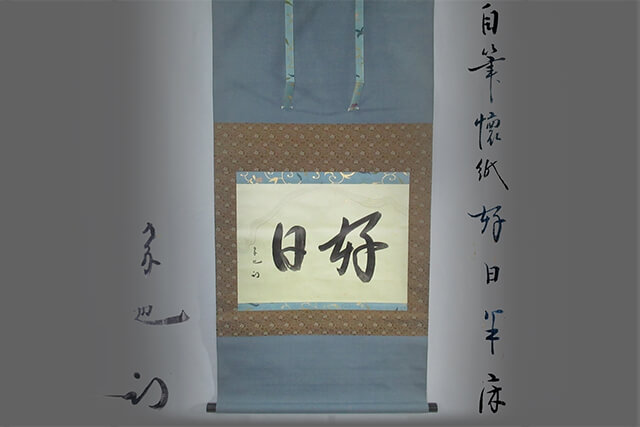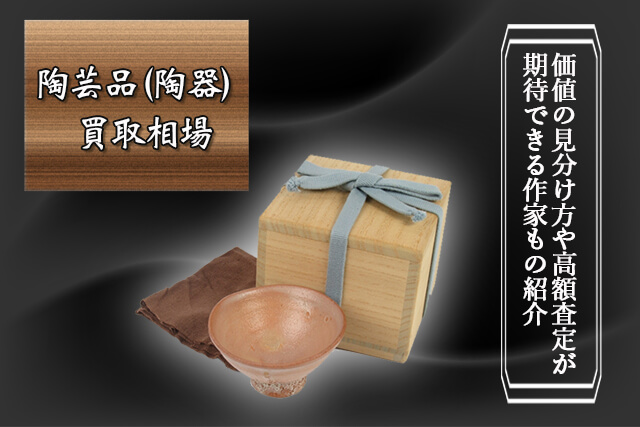- 骨董品
- 2025.11.18
たぬきの置物の意味と効果を解説!信楽焼が縁起物として愛される理由と価値

飲食店や商店の入り口で、愛らしいたぬきの置物を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
丸みのある体とにこやかな表情が特徴のたぬきの置物には、商売繁盛や開運招福を願う縁起物としての意味が込められています。産地は滋賀県の信楽町(しがらきちょう)で、長い歴史と職人の技によって受け継がれてきた価値のある置物です。
この記事では、信楽焼のたぬきの置物に込められた意味や、全国的に有名になった背景などを詳しく解説します。
【記事のポイント】
- ✅たぬきの置物には「八相縁起」という8つの福を願う意味があります
- ✅たぬきの置物自体が縁起物のため「置き場所はここでなければならない」という厳密な決まりはありません
- ✅専門の査定士が無料で丁寧に査定しますので、価値が気になる方もお気軽にご相談ください
たぬきの置物が縁起物とされる理由と意味

たぬきの置物は、単なる装飾品ではありません。丸みのある体と素朴な表情が印象的なたぬきの置物には、古くから商売繁盛や開運招福などの意味が込められています。
縁起物だと認知されているのは、「他抜き」との語呂合わせや、八相縁起という考え方に由来しているためです。以下で、たぬきの置物に込められた思いやその背景を理解しましょう。
商売繁盛・開運招福のご利益【たぬきの語呂合わせ由来】
たぬきの置物が縁起物とされる理由は、たぬきを「他抜き」と読む語呂合わせに由来しています。商売で他を抜く、つまりお店が繁盛して他との競争に勝ち抜くという意味を持ち、事業の成功や繁盛を象徴する存在として親しまれてきました。そのため、飲食店や商店の軒先に置かれていることが多いのです。
現在では自宅の玄関やリビングに置かれたり、学業成就や合格祈願の縁起物として選ばれたりするケースもあります。
また、たぬきは日本神話で「福の神」として登場する動物でもあります。福の神は人々に幸福をもたらす神であり、家内安全や金運上昇を願って信仰の対象とされてきました。語呂合わせだけでなく、福を呼ぶ象徴としての信仰も、たぬきが縁起物として愛される理由の1つです。
八相縁起に込められた8つの意味
たぬきの置物には、八相縁起(はっそうえんぎ)と呼ばれる8つの意味が込められています。八相縁起は、たぬきの姿形を通して商売人の心得や人生の指針を表したものです。
信楽焼のたぬきは、笠をかぶり「徳利(とっくり)」や「金袋(かねぶくろ)」を持っている姿が特徴です。実は、これらの持ち物や体のパーツごとに八相縁起の縁起の良い意味が込められています。
具体的には、以下のような教えが込められています。
1.笠:予期せぬ災難や困難から身を守るために常に備える
2.笑顔:愛想良く人と接することで、良好な信頼関係が構築でき、商売繁盛につながる
3.目:物事の本質を見抜けるよう、常に周囲の状況に気を配り、正しい判断力を身に付ける
4.腹:何事にもどうじない冷静さ・いざというときの大胆な決断力を兼ね備えておく
5.金袋:金運に恵まれて財を成す(商売繁盛につながる)
6.徳利:人徳を身に付けて飲食に困らない豊かな生活を送る
7.通い帳:お客さま・取引先との信用を大切にする(商売の基本)
8.尾:「終わり良ければ全て良し」という善終を表す
この八相縁起は、見た目のかわいらしさの裏に「努力と誠実さを忘れずに商売に取り組む」という教訓を表しています。そのため、単なる装飾品ではなく、日々の心構えを思い出させてくれるものとして、今も多くの人に愛されています。
たぬきの置物はそれぞれ姿や表情が異なるため、願いや目標に合わせて、どのパーツが強調されているかに注目して選べるところも魅力です。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

たぬきの置物を置く場所と意味

たぬきの置物をどこに飾るべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。商売繁盛を願う店先に置かれるケースが多い一方で、家庭運や学業運を高める縁起物として自宅に飾られることもあります。
結論、たぬきの置物自体が縁起物のため「置き場所はここでなければならない」という厳密な決まりはありません。しかし、どこに置くかによって込められる意味や願いが変わります。
ここでは、玄関・リビング・書斎などの場所ごとに、たぬきの置物が持つ意味を紹介します。
玄関やお店の入り口【商売繁盛・千客万来】
玄関やお店の入り口にたぬきの置物を飾ると、商売繁盛や千客万来のご利益が得られると言われています。
商売繁盛とは、商売が順調に進み利益を安定して得られる状態を指します。千客万来は、多くのお客さまが次々と訪れる意味を持つ四字熟語です。風水でも玄関は「運気の通り道」とされており、縁起物のたぬきを飾ることで良い気が家や店内に流れ込み、繁栄へつながると考えられています。
また、昔から「たぬきに取り憑かれるとお酒を飲みたくなる」という言い伝えがあります。そのため、飲食店では「たぬきに取り憑かれたように楽しく食べて飲んでほしい」という願いを込めて置かれるケースもあるようです。ふっくらしたお腹は、満腹や満足の象徴でもあります。
設置するときは、たぬきの顔を外側に向けるのがポイントです。「外から福を招き入れる」という意味を込めて顔を外側に向けることで、お客さまを温かくお迎えするメッセージにもなります。
リビング【家庭円満・家内安全】
リビングにたぬきの置物を飾ると、家庭円満や家内安全のご利益があると言われています。
たぬきは夫婦で協力して子育てをし、家族愛を大切にする生き物です。その仲睦まじい習性から、家庭円満・家内安全の象徴とされており、リビングに置けば穏やかで仲が良い家庭へと導いてくれると言われています。
また、たぬきは日本神話で福の神として登場する動物の1つです。そのため、リビングに飾ることで、家族一人ひとりに幸福が訪れると伝えられています。
リビングに置く際は、たぬきの顔を部屋の内側に向けるのが基本です。家族の方へ笑顔を向けることで、たぬきの優しい表情が家庭に穏やかな安らぎを与えてくれるでしょう。
書斎や勉強部屋【学業成就・仕事運アップ】
学業成就・仕事運アップを狙いたい方は、自分の書斎や勉強部屋に飾ると良いでしょう。
たぬきが縁起物として親しまれる理由の1つに、「他抜き」という語呂合わせがあります。「他の人を抜いて競争に勝つ」という考え方は、商売だけでなく、学業や仕事にも通ずる考え方です。
例えば、「受験で第一志望に合格したい」「誰よりも努力して昇進を目指す」といった考え方が思い浮かぶでしょう。たぬきの置物は、このような目標に向かって頑張る人の背中を押してくれるお守りのような存在になります。
大きいサイズのたぬきは場所を取るため、書斎や勉強部屋に飾るならミニチュアサイズがおすすめです。仕事や勉強の合間にその愛嬌ある姿を眺めることで、良い気分転換になるだけでなく、目標達成へ向けたモチベーションの維持にもつながるかもしれません。
信楽焼たぬきが有名になった理由

信楽焼と聞いて、たぬきの置物を連想する方は多いでしょう。信楽焼のたぬきが全国的に有名になった背景には、歴史的な出来事と土地ならではの魅力が深く関係しています。
ここからは、信楽焼の知名度を高めた昭和天皇の行幸エピソードと、信楽の土が生んだたぬきの魅力を紹介します。
昭和天皇の行幸とたぬきのエピソード
信楽焼のたぬきが全国的に知られるようになったのは、1951年(昭和26年)に行われた昭和天皇の行幸がきっかけです。
当時、天皇陛下が信楽町を訪れた際、地元の人々は日の丸の旗を持ったたぬきの置物を沿道に並べて歓迎しました。その光景を見た昭和天皇がある歌を詠んだことで、信楽焼のたぬきが有名になったのです。
昭和天皇は日の丸を持ったたぬきの置物に感動し、このような歌を詠みました。
幼なとき 集めしからに懐かしも しがらき焼の狸をみれば
この出来事は新聞やラジオなどを通じて全国に広まり、信楽焼のたぬきが一躍有名になりました。以来、信楽焼=たぬきというイメージが定着し地域の代表的な工芸・観光資源として受け継がれていったのです。
信楽の土が生んだたぬきの魅力
信楽焼が有名になった理由の1つに、信楽の土の性質が挙げられます。
信楽焼の原料となる土は、およそ400万年前から琵琶湖の湖底に堆積している粘土層から採取されています。この土は耐火性に優れており、高温で焼いても変形しにくいのが特徴です。このため、大型の置物から繊細な焼き物まで、幅広い陶器作りに適しています。
可塑性にも優れており、職人の手によって自由な形に成形しやすい柔軟さを持っているのも特徴です。たぬきの丸い体や愛嬌のある表情を生き生きと表現できるのも、この土の粗さによるものです。
このように、長い年月を経て生まれた土の性質と職人の技が融合することで、見る人の心を和ませる信楽焼のたぬきが生まれました。
信楽焼の特徴と歴史【3分解説】

信楽焼は、滋賀県甲賀市信楽町を中心に作られている日本六古窯の1つです。鎌倉時代中期に始まったとされている歴史的な焼き物で、1975年(昭和50年)9月に国の伝統工芸品に指定されています。
「信楽焼と言えばたぬき」と言われていますが、実は傘立てやタイル、食器などにも伝統的な技法が採用されています。ここからは、信楽焼きの主な特徴や歴史を見ていきましょう。
(参考:『信楽陶器工業協同組合 信楽焼とは?』)
土と炎が織りなす、素朴な魅力
信楽焼の最大の魅力は、豊かな自然の恵みをそのまま焼き締めたような、素朴で温かみのある風合いです。
陶器は、ろくろや手びねりで形を整えた後、乾燥・素焼き・釉薬かけ・本焼きを通して完成します。信楽の土は粒子が粗く、焼き上げると土の息づかいが感じられるような、ざらりとした手触りが生まれます。1つとして同じ仕上がりにならず、それぞれが異なる表情を見せるのも魅力です。
さらに、信楽焼の美しさにつながっているのが「自然釉(しぜんゆう)」と「火色(ひいろ)」です。自然釉は、焼成中に薪の灰が溶けてできるビードロ(緑色のガラス層)のことで、自然の力だけで生まれる艶やかな輝きを放ちます。火色は炎が直接当たることで現れる赤褐色で、素朴で温かな印象を与えます。
他にも、焼成のときに灰がかかって表面が黒く変化する「こげ」や、土の中に含まれる長石が溶けてガラスの粒のように見える「霰(あられ)」も、信楽焼ならではの特徴です。
日本で最も歴史ある焼き物の1つ
信楽焼は、日本に古くから存在する代表的な6つの窯「日本六古窯(にほんろっこよう)」の1つに数えられる、非常に格式高い焼き物です。その歴史は鎌倉時代まで遡り、約800年もの間、一度も途絶えることなく焼き物が生産され続けています。
生産を開始した当初は、東海地方の常滑焼(とこなめやき)から支援を受けていました。戦国時代になると茶の湯文化が盛んになり、信楽焼はその素朴な風合いと火色の美しさで茶人たちに愛されるようになります。
生産量が大きく増えたのは江戸時代で、京焼の影響を受けた華やかな作風を取り入れたことがきっかけです。この頃には茶壺や大壺の製造が盛んになり、お茶壺道中の主役として使われるなど、全国にその名を広めました。
明治から昭和にかけては、火鉢の生産で全国的に知られるようになり、昭和30年代前半まで国内シェア約80%を占めていました。この過程で身に付けた技術は、後にたぬきの置物作りへと受け継がれます。
親しみやすいたぬきの置物には、このような日本の焼き物の歴史を背負ってきた奥深い世界が広がっているのです。
(参考:『信楽陶器工業協同組合 信楽焼とは?』)
(参考:『滋賀県教育委員会・滋賀県埋蔵文化財センター 信楽焼甲府市信楽町一帯』)
【関連記事】
信楽焼の買取相場は?花瓶や壺、たぬき・干支の置物の価値や査定ポイントなど解説
たぬきの置物を売る・処分する方法

「たぬきの置物を売りたい」「処分したい」と考えている方も多いでしょう。
手放す方法は、買取に出すか処分するかの2つが主な選択肢です。買取相場は数千円〜数万円程度で、状態やサイズによっては高価買取が期待できる場合もあります。
ここでは、たぬきの置物を買取に出す際のポイントや買取相場、適切な処分方法を解説します。
買取業者への査定依頼
たぬきの置物を少しでも高く売りたい場合は、買取業者への査定依頼がおすすめです。
特に有名作家が手がけた作品は希少価値が高く、思わぬ高値が付くかもしれません。例えば、鷲塚暁珉や村田宏、仁阿弥道八の作品であれば、高く評価される場合があります。
一般的な買取相場は数千円〜数万円程度ですが、状態やサイズによって金額は大きく変わります。100センチ以上であれば500円〜1,000円程度にとどまるケースが多いです。一方で、信楽焼の作家物や大型品は、数万円前後の査定額が付く可能性があります。
買取業者を選ぶ際は、陶磁器や骨董品の取り扱い実績が豊富な店舗を選びましょう。出張買取に対応している業者なら、たぬきの置物のように重くて運びにくいものも自宅で手軽に査定してもらえます。
私たち「福ちゃん」では、たぬきの置物に限らず、信楽焼の壺や花瓶・食器など骨董品の買取を強化中です。専門の査定士が、お品物の価値を丁寧に見極め、ご納得いただける査定額をご提示します。
査定料・出張料・キャンセル料などの費用は一切いただきませんので、まずはお気軽にご相談ください。
※製品の状態によっては買い取れない場合がございます、予めご了承ください。
破損している場合は「処分」
破損がひどく、買取を断られた場合は、残念ですが処分を検討しましょう。たぬきの置物は陶器製のため、一般的には不燃ごみとして出すのが基本です。
しかし、福を招いてくれた縁起物だと思うと、そのまま捨てるのに抵抗を感じる方もいるかもしれません。その場合は、まず長年の感謝を伝えることから始めましょう。きれいな布でホコリを拭き、白い紙や布で包むだけでも、気持ちの整理が付きやすくなります。
処分方法は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。例えば、東京都港区では、陶磁器やガラス類を清掃事務所で回収し、海外でリユースする仕組みを取っています。一方、大阪市では、厚紙などで包んで普通ごみで出すのがルールです。
また、置物のサイズが大きい場合、粗大ごみ扱いとなる場合があります。出し方を誤ると収集されない場合があるため、処分する前にルールをご確認ください。
なお、処分する際は、作業員の方がけがをしないよう、ごみ袋に「キケン」「陶器」などと記載しておきましょう。
処分するのがどうしても忍びない方は、神社やお寺での供養を検討するのも選択肢の1つです。中には置物の供養を受け付けているところもあるため、近隣の寺社に問い合わせてみましょう。
たぬきの置物の高価買取を狙うなら福ちゃんにご相談ください
信楽焼のたぬきの置物は、商売繁盛や開運招福などの縁起物として古くから親しまれています。信楽特有の土は耐火性と可塑性に優れ、焼き上げると温かみがあって素朴な雰囲気に仕上がるのが特徴です。
このような魅力と歴史の深さから、信楽焼のたぬきは縁起物として全国で親しまれています。保存状態の良いものや作家作品は、美術的価値が高く高額で取引される可能性があります。
たぬきの置物を少しでも高く売りたい方は、陶磁器や骨董品の買取実績が豊富な福ちゃんにご相談ください。査定経験が豊富なスタッフが丁寧に査定いたします。査定料やキャンセル料などの発生はなく、サービスのご利用は全て無料です。
信楽焼のたぬきは、職人の技と歴史が詰まった伝統工芸品です。思い出の詰まった品を手放す前に、ぜひ福ちゃんの無料査定をお試しください。