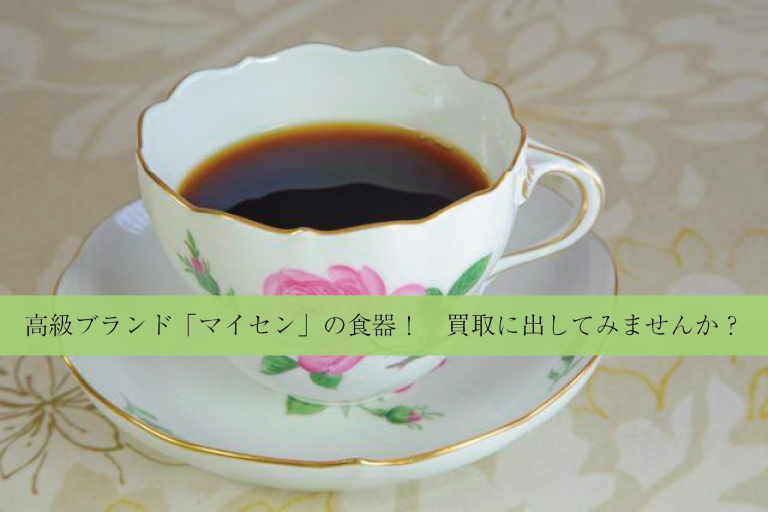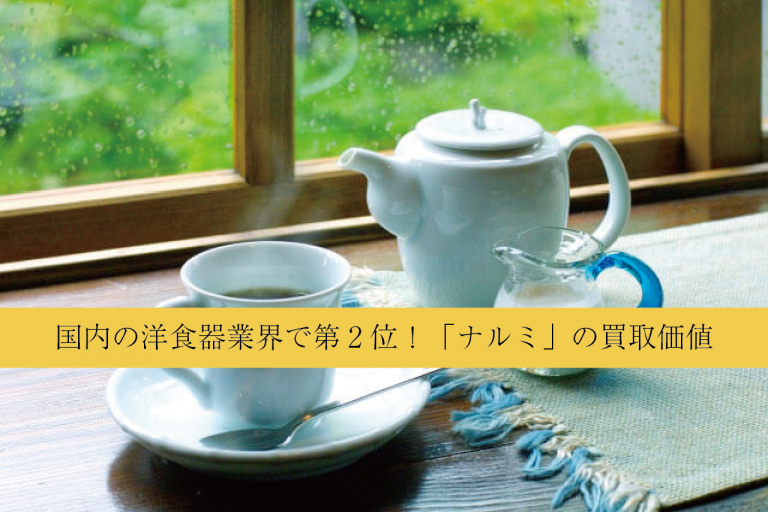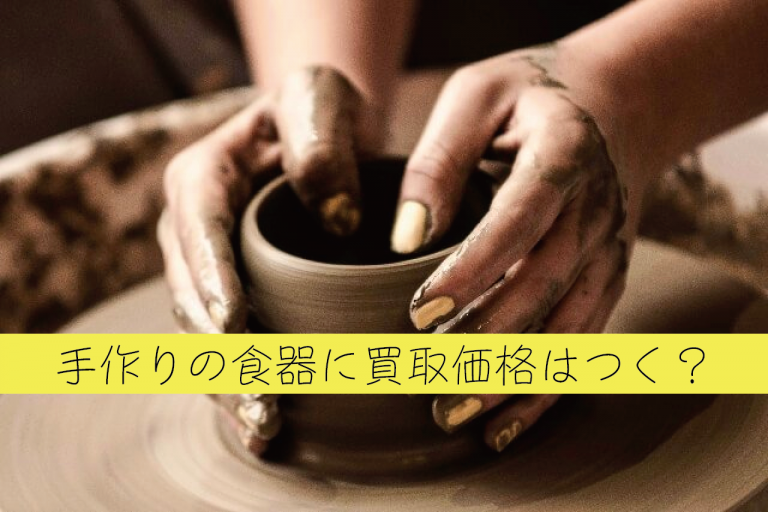- 食器
- 2025.11.19
陶器と磁器の違いを徹底解説!特徴・見分け方と買取ポイントまで紹介

陶器と磁器の違いが分からず、どう使い分けたらよいか分からない方は多いのではないでしょうか。
どちらも焼き物ですが、実は原料や焼成温度、手触りなどに違いがあります。見た目だけでなく、強度や吸水性などの扱いやすさにも差があるため、正しく見極めるにはそれぞれの特徴を知ることが大切です。
この記事では、陶器と磁器の特徴や見分け方、主な違いを分かりやすく解説しています。焼き物の基礎知識を身に付け、大切な食器をより賢く活用しましょう。
【記事のポイント】
- ✅陶器と磁器は、叩いた時の音や光の透過性で見分けられます
- ✅陶器は土が原料で冷めにくく、磁器は石が原料で衛生的です
- ✅正確な価値は専門家の査定が不可欠です。福ちゃんならプロが手数料無料で価値をしっかり見極めます
焼き物の基本分類(陶器・磁器・炻器・土器)

焼き物と聞くと、有田焼や美濃焼、瀬戸焼などを思い浮かべるのではないでしょうか。これらは焼き物という点では共通していますが、全て同じカテゴリーに分類されるわけではありません。
焼き物は、大きく分けて陶器・磁器・炻器(せっき)・土器の4つに分かれます。見た目は似ていても素材や製法、性質などが大きく異なるため、まずは基本的な分類を理解しましょう。
土器・陶器・炻器・磁器の特徴
陶器・磁器・炻器・土器の違いを以下にまとめました。
| カテゴリー | 原材料 | 吸水性 | 焼成温度(目安) | 特徴 |
| 陶器 | 粘土(陶土) | あり(低い) | 1100度~1250度 | ・厚手で保温性が高い・低温で焼いて仕上げるため焼き締まらず、厚さと温かみがある・水を通しやすいため手入れが必要 |
| 磁器 | 陶石 | なし | 1250度~1400度 | ・硬度が高く、滑らかな手触りに仕上がる・熱しやすく冷めやすい・有田焼や京焼などで知られている |
| 炻器 | 鉄分の多い粘土 | ほぼなし | 1200度~1300度 | ・陶器と磁器の中間くらいの質感・硬く焼き締まるが、透過性はない・須恵器や信楽焼で知られている |
| 土器 | 粘土 | あり(高い) | 600度~800度 | ・縄文土器・弥生土器で知られている・現在は植木鉢などに採用されている・低温で仕上げるためもろい |
このように素材や焼成温度、質感の違いによって、どの焼き物にも独自の魅力と個性が生まれています。
陶器や磁器は日常的な食器に採用されるケースが多く、炻器は土鍋や急須などに採用されているのが特徴です。土器は縄文時代から続く歴史的背景がある焼き物ですが、現在では日常的な食器ではなく、植木鉢などの園芸用品に使用されています。
陶器と磁器の製造工程(原料・成形・焼成)
焼き物の種類を理解する上で欠かせないのが、陶器と磁器の製造工程の違いです。陶器は柔らかく温かみのある風合いが特徴で、磁器は硬く滑らかな質感が特徴です。このような違いが生じる背景は、単なる素材の差ではなく、原料の選定から焼成に至るまでの工程が深く関わっています。
ここでは、それぞれの製造工程における3つの重要なポイントを解説します。
原料(陶器=土、磁器=石)
陶器の原料は、陶土と呼ばれる粘土です。陶土のみで作られるのではなく、長石や珪石を調合して焼き物を作っています。配分の目安は粘土50%・長石10%・珪石40%となっており、粘土の可塑性(かそせい:変形しやすい性質)を生かして作られるのが特徴です。ザラザラとした手触りと、素朴な見た目が主な特徴で、磁器より分厚くなります。
一方、磁器は陶石を粉状に砕いた石粉を主原料としています。陶器は粘土の割合が多いですが、磁器は粘土30%・長石30%・珪石40%と石が大きな成分割合を占めているのが主な特徴です。
陶器が土の温もりを感じるのに対し、磁器は硬く透明感のある上品な印象を与えます。
(参考: 『土岐市 磁器と陶器の違いは』)
成形方法の違い
陶器は軟らかい粘土を使用するため、ろくろや手びねりなど多様な技法で成形されるのが特徴です。
まずは粘土を練り、内部の膨張による爆発を防ぐために気泡を抜きます。その後、ろくろや手びねりなどで成形し、低温で素焼きします。最後に絵付けや釉薬を施し、さらに高温で本焼きすることで陶器特有の温かみのある質感が生まれる流れです。
磁器も同様に成形・焼成の工程を経ますが、原料が硬く可塑性に乏しいため、石膏型に原料を流し込む「鋳(い)込み成形」が多く用いられます。鋳込みは均一な厚みと精密な形状を作りやすく、大量生産に向いている技法です。
また、磁器の場合は最初に陶石を粉砕して細かくする工程が必要で、この点が陶器との大きな違いです。
焼成温度と特徴
陶器と磁器の製造過程で大きく異なるのは、焼成温度です。
陶器は、1100度~1250度と比較的低温で焼き上げます。焼いた段階では素地が完全に固まらないため、表面に多孔質と呼ばれる小さな穴が残ります。この穴が水分を吸収するため、長く使ううちに色や質感が変化していくのが陶器の特徴です。
一方、磁器は1250度~1400度の高温で焼成されます。高温でじっくり焼き上げることで、素材の密度が高まり、陶器よりも頑丈な作りになります。
磁器を叩くとガラスのような澄んだ音がするのは、陶石や長石が溶けて隙間を埋め、表面の強度を高めているためです。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

陶器と磁器の違い(特徴比較)

ここまで陶器と磁器の製造過程を見てきましたが、本項ではその違いをさらに詳しく掘り下げていきましょう。
両者は同じ焼き物の仲間でありながら原料の構成や焼成温度、吸水性、硬度などに差があります。製造過程以外にどのような違いがあるのかを押さえながら、素材ごとの特徴や物理的な差を理解していきましょう。
陶器と磁器の特徴比較(原料・焼成温度・吸水率など)
陶器は粘土を主原料とし、柔らかく温かみのある質感が特徴です。一方、磁器は陶石を使い、高温で焼き締めることで硬く緻密な仕上がりになります。
さらに、熱伝導性や光の透過性といった性質にも差があり、用途や見た目の印象にも影響します。ここでは、両者の基本的な特徴を比較して見ていきましょう。
物理特性の各比較(主原料~重量)
陶器と磁器の違いを分かりやすくするため、以下で主な物理特性を項目ごとに整理しました。
| 相違点 | 陶器 | 磁器 |
| 主原料 | 粘土(陶土) | 陶石 |
| 焼成温度 | 1100度~1250度(比較的低温) | 1250度~1400度(高温) |
| 吸水率 | 5%~10%程度 | 0%(ほぼなし) |
| 硬度 | 比較的軟らかい | 非常に硬い |
| 熱伝導率(熱の伝わりやすさ) | 低い(冷めにくい) | 高い(熱が伝わりやすい) |
| 光透過性 | なし | あり |
| 重量 | 厚みがあって重い | 薄くて軽い |
陶器は粘土を多く含むため軟らかく、温かみのある質感を持ちますが、吸水性が5%~10%程度と高くやや重みがあります。熱が伝わりにくい性質を持っているため、保温性にも優れています。
ただし、衝撃に弱く欠けやすい他、吸水性があるためカビやにおい移りに注意が必要です。
磁器は高温で焼くため、硬く軽い仕上がりになり、光に当てるとうっすらと透けて見えるのが特徴です。熱伝導性が高いため、熱いものを入れると器自体も熱くなります。
丈夫で欠けにくい点はメリットですが、熱が伝わりやすく熱くなりやすい点や、やや冷たい印象になりやすい点はデメリットになります。
陶器と磁器の見分け方(音・光・手触り)

陶器と磁器をどのように見分けたらよいか分からない方も多いのではないでしょうか。
両者には物理的な性質の違い以外にも音や光、手触り、見た目に違いがあります。違いを見分けられるようになれば、食器を料理に応じて使い分けたり、好みの焼き物を見つけやすくなったりと多くのメリットがあります。
以下で具体的な見分け方を紹介しているため、お手持ちの食器でぜひ試してみてください。
見分け方詳細(音・光・手触り・見た目)
陶器と磁器を見分ける際の主なチェックポイントと、それぞれの違いを以下にまとめました。
| チェックポイント | 陶器 | 磁器 |
| 叩いたときの音 | 「コンコン」「ゴンゴン」と鈍く低い音がする | 「キーン」「チン」と金属的で高く澄んだ音がする |
| 光に当てたときの見え方(透過性) | 光をまったく通さない | 薄い部分では光を通すことがある |
| 手触り | 高台にざらつきがあり、土の質感を感じる ※高台:器の底にある台の部分(底のでっぱり) | 高台は滑らかでつるりとした質感 |
| 見た目 | 厚みがあり、温かみのある素朴な印象(ぽってりとしている) | 薄手でシャープ透明感があって上品な印象 |
※叩いて確認するときは、衝撃で割れないように注意しましょう。
上の比較から分かるように、陶器と磁器は音や光の透け方、手触りなど感覚的な部分でも違いがあります。これらの特徴を押さえることで、質感や響きからも焼き物の種類を見分けやすくなるでしょう。
実用シーンでの使い分け

陶器と磁器にはそれぞれ異なる特性があり、どちらを選ぶかで料理の印象や使い心地が変わります。実用的な使い方を知らないと、料理が冷めやすくなったり、器と食事の雰囲気が合わなかったりする場合があります。
上手に使い分ければ、日常の食卓をさらに彩れるようになるでしょう。毎日の食事を楽しくするためにも、以下で料理別の使い分けのポイントを確認しましょう。
シーン別使い分け(温かい料理・刺身・コーヒー)
みそ汁やシチューなどの温かい料理には、陶器の器がおすすめです。陶器は磁器と比べて保温性が高く、温かい料理を入れても冷めにくい特徴を持っています。触っても熱さを感じにくいため、やけどのリスクを防ぐことも可能です。
一方、お刺身などの生ものを使った料理には、においや汚れが付きにくい磁器の器が向いています。陶器と比べて汚れが落ちやすいため、洗い物の効率が上がる点もうれしいポイントです。涼しげな白磁や青磁は、魚の鮮度をより一層引き立ててくれるでしょう。
コーヒーのマグカップは、シーンや気分で選ぶのがおすすめです。ゆっくり味わいたいときは陶器、手軽に楽しみたいときは、洗いやすくにおい移りしにくい磁器を選ぶとよいでしょう。電子レンジ対応であれば、やけどの不安も軽減でき、温め直しにも便利です。
陶器とは?原料・特徴・代表産地

陶器は、日本の食卓や暮らしに古くから根付いてきた焼き物の一種です。有名産地の職人技が光る陶器は、手作業ならではの温もりや独特の質感を感じられます。
原料の違いや釉薬の特徴を知ると、器選びの幅が広がり、料理や空間に合った焼き物を見つけやすくなります。陶器の基礎知識を押さえ、ライフスタイルをより豊かにする焼き物と出会いましょう。
陶器の原料と特徴
陶器は、陶土と呼ばれる粘土で作られています。陶土の種類は、大きく分けて以下の6つに分けられています。
| 種類 | 概要 | 特徴 |
| 白土 | 焼成すると白く焼き上がる土 | ・鉄分が少なく、焼き上がりは白やベージュなどの明るい色になる |
| 赤土 | 赤みを帯びている土 | ・鉄分が多く、焼き上がりはレンガのような赤褐色になる |
| 黒土 | 白土に黒い顔料を加えた土 | ・深みのあるグレーや茶色がかった黒に仕上がる |
| 磁器土 | 長石・ケイ石などで構成された土 | ・白く透明感がある仕上がりになる・薄いが強度が高い |
| 半磁土 | 陶土と磁器土を混ぜ合わせた中間的な素材 | ・成形方法の幅が広い・透明感がないが強度は高い |
| 鍋土 | 耐火性に優れた土 | ・直火が可能で、土鍋や耐熱皿などに使われる・ペタライトを配合して熱衝撃を抑えている |
鉄分を多く含む粘土は、赤茶色や黒っぽい焼き上がりになります。一方で鉄分が少ない粘土は、白やベージュ系の明るい焼き上がりになります。
陶芸家は、これらの性質の異なる粘土を複数ブレンドしたり、砂や他の鉱物を混ぜたりして、目指す質感や強度をコントロールしているのです。
なお、陶器の産地は、岐阜県の美濃焼や栃木県の益子焼、滋賀県の信楽焼などが代表的です。
釉薬と仕上げの特徴
陶器の表面には、釉薬(ゆうやく)と呼ばれるガラス質のコーティングが施されています。陶器は吸水性が高く、釉薬を塗らないと水漏れやひび割れ、カビが発生する可能性があるためです。釉薬を塗ることで表面が密閉され、液体が染み込みにくくなり、長く使える丈夫な器に仕上がります。
炻器や土器のように釉薬を使用しないものもありますが、日常的に使う食器には施釉されているのが一般的です。
また、釉薬を塗ると表面に磨きがかかって、美しい色や光沢が現れます。その仕上がりは、釉薬の種類によって異なります。例えば、透明釉を使うとツヤが出て明るい印象になり、マット釉であれば光沢を抑えて落ち着いた雰囲気に仕上がるのが特徴です。
他にも、植物の灰を主成分とする「灰釉」や、鉱物の長石を主成分とする「長石釉(ちょうせきゆう)」などがあります。これらの釉薬が焼成中に溶け、冷えて固まることで、陶器独特の美しい表情が生まれるのです。
陶器の経年変化と楽しみ方
陶器は、使い込むほどに表情を変えるものです。新品のときには見られなかった独特な風合いは、年月とともに味わい深くなっていきます。
このような変化は劣化ではなく、使う人の手や料理、環境が生み出した陶器の魅力です。ここでは、代表的な経年変化である貫入や染み・色の変化について、その特徴と楽しみ方を紹介します。
貫入(模様の特徴)
貫入(かんにゅう)とは、陶器の製造過程で生まれるヒビのような細かな模様です。
焼き上がりの高温の陶器が急激に冷やされると、釉薬と素地の間に微細な圧力がかかり、結果として貫入が生じます。これは破損ではなく、熱膨張の仕組みによって生まれる自然な現象です。
貫入は使い込むうちに少しずつ色素や水分が入り込み、模様がより際立っていくのも魅力です。経年によって深まる模様の変化を楽しむことで、陶器への愛着もさらに湧くでしょう。
貫入の進行を抑えたい場合は、目止め(使用前に米の研ぎ汁に浸すこと)を試してみてください。
【関連記事】
必見!陶器の正しいお手入れ方法とは
染みや色の変化
陶器を繰り返し使用していると、染みや色の変化が生じるケースがあります。これは経年劣化で自然に生じるものですが、逆をいえば器が重ねてきた時間を映し出す証なのです。
例えば、素地の上に白い化粧土をかけた「粉引(こひき)」の器は、年月とともに染みが生じる可能性があります。貫入のあるマグカップでは、コーヒーや紅茶の色素が模様のように入り込む場合もあるでしょう。その他、釉薬が流れ込んだ跡やピンホール(小さな黒い穴)が生じるケースもあります。
このように、持ち主の使い方によって器の表情が変わっていく様を、愛好家たちは「器を育てる」と表現します。使用後すぐに洗ってよく乾かしたりと、少し手間はかかりますが、愛着の湧く自分だけの1枚になってくれるのです。
なお、染みやにおいを防ぎたい場合は、使用前に米の研ぎ汁などで目止めをしておくと効果的です。
【関連記事】
陶器の食器のシミ、汚れを落とすには
磁器とは?原料・特徴・代表産地

磁器は、陶石や長石などの石を主な原料として高温で焼き上げた焼き物です。白く透き通るような質感と、硬く緻密な仕上がりを特徴としています。
代表的な産地は、長崎県の波佐見焼や佐賀県の有田焼、伊万里焼などです。これらの地域では、実用性と美しさを兼ね備えた製品が多く生み出されています。
まずは、磁器の原料とその特徴を詳しく見ていきましょう。
磁器の原料と特徴
最初に述べたように、磁器は粘土ではなく、石を粉砕して細かくした原料から作られます。
石といっても一種類ではなく、主に以下の3つの原料が緻密な計算の基でブレンドされています。
- 陶石
- 長石
- 珪石
これらの原料は、それぞれが異なる役割を持ち、組み合わせによって磁器特有の硬さや透明感が生まれます。以下で、どの原料が何のために配合されているのかを確認しましょう。
陶石
陶石とは、磁器の主原料となる石質の鉱物です。磁器の製造では、この陶石を細かく砕き粉状にし、鉄分などの不純物を丁寧に取り除いてから使用します。磁器の骨格としての役割を果たし、焼き上がりの強度や透明で美しい見た目の形成につなげています。
日本で初めて磁器の大量生産に成功した地域は、有田焼で知られる佐賀県有田町です。1616年に有田町の泉山で上質な陶石が採掘されたのをきっかけに、有田焼としての名を広めていきました。
陶石の中でも、熊本県の天草陶石は、他の原料を混ぜずに単独の陶石だけで磁器を作れるとして希少性があります。
(参考: 『佐賀県陶磁器工業協同組合 原料』)
(参考: 『日本セラミックス協会 日本のやきもの 陶磁器の主な原料』)
長石
長石とは、カリ長石やソーダ長石などを主成分とする鉱物です。焼成時に高温で一部が溶けてガラス質となり、陶石の粒子を結び付ける接着剤のような役割を果たします。磁器特有の滑らかで透明感のある質感は、この長石の融解作用によって生み出されるものです。
具体的には、焼成の過程で長石が液状化し、他の成分との結合を強めることで焼き締まりが進みます。その結果、表面には美しい光沢が現れ、内部は密度の高い硬質な構造になる仕組みです。
また、長石は釉薬の調合にも欠かせない成分です。長石釉は、長石を主原料として作られる釉薬で、焼成時にガラス状に溶けて器の表面を覆います。
(参考: 『日本セラミックス協会 日本のやきもの 陶磁器の主な原料』)
珪石
珪石は、二酸化ケイ素(SiO2)を化学組成とする原料です。透明できれいに成形された石英を水晶と呼びますが、その細かな石英の粒が集約した岩石を珪石と呼びます。
磁器の製造で使用するのは、粉砕したケイ石です。ケイ石を混ぜると、乾燥や焼成のときに素地が縮み過ぎたり歪んだりしにくくなり、形が安定します。
また、珪石は釉薬にも使用される重要な材料です。釉薬は表面をコーティングし、器のツヤを出したり、装飾を美しく見せたりする役割を果たします。
つまり、珪石は器を丈夫にするだけでなく、見た目もきれいにするために欠かせない原料なのです。
(参考: 『日本セラミックス協会 日本のやきもの 陶磁器の主な原料』)
薄造りの技術
磁器は、薄くても強度を保てる特性を持っています。これは、原料に含まれる鉱物が高温で焼かれることで溶け、表面をガラスのように硬く仕上げるためです。
焼き上がった磁器は、内部まで緻密に焼き締まり、水や空気をまったく通しません。そのため、薄くても割れにくく、軽さと耐久性を両立しているのです。
この薄造りの技術は、磁器の透過性とも大きく関係しています。陶器はまったく光を通しませんが、磁器は光に当てるとうっすら向こう側が透けて見えます。美しい透け感と強度を兼ね備えている磁器は、長い間愛用できるでしょう。
磁器は割れにくい性質を持っていますが、強い衝撃が加わると破損する可能性があります。取り扱いには十分に注意しましょう。
(参考: 『一般社団法人 日本化学工業協会 化学の目でみる日本の伝統工芸』)
磁器のメンテナンス性と衛生面
磁器は見た目の美しさだけでなく、メンテナンス性の高さでも優れた素材です。高温で焼き締められることで内部まで固まり、水分や汚れが染み込みにくい構造をしています。そのため、日常使いしても劣化しにくく、清潔な状態を保ちやすいのが特徴です。
ここからは、吸水率の低さや耐久性といった具体的な特徴について、もう少し詳しく見ていきましょう。
吸水率ほぼゼロ
磁器の大きな特徴の一つが、吸水率の低さです。
陶器は粘土を主原料にしており、低温で焼くため内部に細かな隙間が残ります。釉薬で水が浸透しないように対策はしているものの、構造上どうしても吸水率が高くなってしまいます。
磁器は高温でしっかり焼き上げるため、内部に隙間がなく吸水率はほぼゼロです。長く使っても変色やにおい移りが起きにくく、日常使いの食器に適しています。
また、吸水率がほぼゼロであることで、油汚れも洗いやすくなるのも主なメリットです。清潔で扱いやすい磁器なら、毎日の忙しい食卓でも活躍するでしょう。
(参考: 『土岐市 磁器と陶器の違いは』)
カビ・染みへの強さ
磁器は、陶器に比べてカビや染みが付きにくい焼き物です。上述の通り、磁器は陶石などの石を砕いたものを原料とし、表面の強度を高めています。
粘土を主原料とする陶器は焼成温度が低く、微細な穴が発生してしまうため、水分を吸い込みやすい性質を持っています。そのため、使い続けるうちに染みやにおいが残りやすく、保管方法によってはカビが発生するケースもあるのです。
磁器は高温焼成で素地の内部をしっかり焼き上げるため、吸水による汚れのリスクが少なく、衛生面でも優れています。洗い物もしやすいため、家事効率の向上にもつながるでしょう。
食洗機・電子レンジ対応
食洗機や電子レンジに対応可能な磁器なら、忙しい家庭にもぴったりです。
陶器には微細な穴が開いており、繊細な作りであるため、基本的に食洗器・電子レンジは不可となっています。食洗機の高温水流や電子レンジの加熱によって膨張し、割れてしまう可能性があるため、手洗いで優しく扱うのが望ましいです。
一方、磁器は表面が硬くて丈夫なため、食洗器や電池レンジに入れても問題ありません。ただし、金や銀などの豪華な装飾が施されているものは、高温によって変色や剥がれが起こる可能性があります。放電の危険性も考えられるため、豪華な装飾のある磁器は手洗いをおすすめします。
磁器のデザイン性とトレンド
均質で滑らかな白いキャンバスを持つ磁器は、デザインの自由度が高い素材です。形状も比較的自由に変えられることから、幅広いバリエーションの磁器が生産されています。近年では、伝統技法を生かしつつ、現代的な感性を取り入れた作品も増えています。
以下で、磁器の代表的な装飾方法や形状の特徴、近年のデザイン傾向を押さえましょう。
上絵付け
上絵付け(うわえつけ)とは、釉薬でコーティングして本焼きを終えた磁器の表面に、さらに絵や模様を描く技法です。
具体的には、絵付けの後に再度800度~900度の低温で焼き付けることで、顔料を釉薬の上に定着させます。透明感のある釉薬の上に色鮮やかな装飾を施せるため、磁器の美しさが一層際立つのが特徴です。
上絵付けの大きな魅力は、発色の良さと表現の幅広さです。使用できる顔料の種類が豊富で、赤・青・緑・金彩など、華やかで繊細な色彩を自由に表現できます。細かなデザインからはっきりとした絵柄のデザインまで、幅広く対応できます。
形状の多様性
磁器は、他の焼き物に比べて幅広い形状を実現しやすい素材です。原料に石を多く含むため、陶器よりも硬く緻密で、成形には「鋳込み」と呼ばれる製法がよく用いられます。そのため、シャープなものから薄い器、複雑な形のデザインなどの多様なフォルムを表現できるのです。
例えば、磁器の産地として知られる有田焼では、この鋳込み技法が多く採用されています。茶碗や湯呑、花瓶、置物などの多くが石膏型を使って成形されており、細部まで精密に仕上げることが可能です。
このような自由な造形性が、磁器ならではの美しさを引き立て、日常の食卓や空間をを美しく彩ってくれます。
現代のトレンド
近年では、伝統的な白磁や染付だけでなく、マットな質感の釉薬を使ったものやニュアンスのあるカラーリングの磁器も人気が高い傾向です。
例えば、美濃焼では口元がすぼんだスタイリッシュなマグカップが作られています。波佐見焼では北欧風の絵柄をあしらったデザインなど、現代の暮らしに溶け込むアイテムが続々と登場しています。
さらに、縁を彩った軽量オーバルプレートや、高台を広く取ったツートンカラーのお茶碗なども登場しているようです。陶器のような風合いをした急須などもあり、ライフスタイルや好みに合わせてお気に入りの磁器を選べます。
また、ポーセラーツと呼ばれる技法を使えば、真っ白な磁器に自分の好きな絵柄を描いて楽しめます。
陶器と磁器の最大の違い(原料)

ここまで見てきたように、陶器と磁器にはさまざまな違いがありますが、最終的には原料の性質に行き届きます。
本項では、これまで触れてきた陶器の原料の土と磁器の原料である石を、もう少し掘り下げて見ていきましょう。原料の特徴を把握することで、仕上がりの質感や用途の違いがより明確に理解できるようになります。
原料の化学組成比較
陶器の原料「陶土」の主成分は、カオリナイトと呼ばれる粘土鉱物です。カオリナイトは白色を基調とした鉱物で、吸水性を持っています。中国・江西省景徳鎮近くの「高嶺(カオリン)」で採掘されたことからこの名が付きました。日本ではほとんど採掘できないため、主に韓国やニュージーランドから輸入しています。
カオリナイトは水と結び付きやすい性質を持ち、鉄分などの不純物を多く含むため、焼き上げたときに柔らかい色味や質感が生まれます。これが、陶器特有の温かみのある色合いや風合いを形づくる要因です。
一方、磁器の原料である陶石は、主に石英と長石を中心に構成されています。石英はガラスのような硬さを生み、長石は磁器を高温で焼くときに一部が溶け、接着剤として働く役割を果たしています。不純物が少ないため、純白の素地を作れるのが特徴です。
熊本県で採れる天草陶石には、石英の他にもセリサイトや少量のカオリン鉱物が含まれています。
簡単にいえば、陶器は自然の土の性質を生かした焼き物、磁器は石を精製・調合して人工的に作り上げたセラミック、といったイメージです。
(参考: 『日本セラミックス協会 日本のやきもの 陶磁器の主な原料』)
原料コストと供給性
原料コストは、陶器・磁器それぞれの共有性と連動している点も確認しておきましょう。
陶土(陶器の原料)は比較的広い地域で採掘されていますが、場所によって性質が大きく異なります。そのため、特定の風合いを生み出す土は希少で、価値が高くなる場合があるのです。さらに陶土は不純物が多いため、精製工程に手間がかかる点もコストに影響します。
代表的な採掘地として、岐阜県恵那市の丸原鉱山が知られています。平成5年(1993年)時点では59の鉱山が稼働していましたが、平成26年(2014年)ではわずか8鉱山にまで減少しており、陶器の採掘は限られた地域でしか行われなくなっているのが実情です。
一方で、磁器の原料である陶石は、採掘できる場所が限られています。例えば、有田焼ではかつて、国指定史跡にも登録された佐賀県の泉山磁石場で陶石が採掘されていました。現在は採掘されておらず、主に天草産の陶石を用いて生産されています。
しかし、質の良い陶石が得られれば、均質な原料を安定して大量に供給できるのが特徴です。粉砕・調合といった工業的なプロセスを経るため、大量生産に向いています。
一般的に、日常使いの量産品は磁器の方が安価な傾向にありますが、作家物やブランド品となると、陶器も磁器もその手間や芸術性によって価格は大きく変わります。
(参考: 『有田観光協会 ありたさんぽ 泉山磁石場 (国指定史跡)』)
(参考: 『Visit Deep JAPAN KEINAN SPOT 恵南文化遺産・観光情報 陶土採掘地 (丸原鉱山)』)
陶磁器とは?総称の意味と範囲

陶磁器と聞くと「陶器や磁器とどう違うのだろう」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論からいえば、陶磁器とは陶器・磁器を含む焼き物全般を指す総称です。つまり、最初に紹介した土器や炻器も陶磁器の範囲に含まれ、陶器と磁器もその一部に当たります。中には窯器(ようき)と呼ぶ場合もありますが、陶磁器と意味はほぼ変わりません。
陶器は土を主原料とし、温かみや素朴さが魅力の焼き物です。磁器は石を原料としており、硬くて光沢のある仕上がりが特徴となっています。これらの違いは、原料の組成や比率、成形方法などによって生まれます。
また、陶器は長く使い込むうちに独特な風合いが出てくるため、自分で器を育てる楽しさを感じられるのが魅力です。磁器は硬くて頑丈かつ、お手入れが簡単で衛生的といった機能性に魅力があります。
どちらを選ぶかは人によって異なるため、陶器の方が良いなどとは一概にはいえません。それぞれの個性を理解し、自分のライフスタイルや気分、料理に合わせて使い分けることが大切です。
陶器と磁器を理解して価値ある食器は福ちゃんへ
陶器と磁器は、どちらも長い歴史の中で育まれてきた日本の伝統工芸です。原料や質感、作り方の違いを理解することで、お手持ちの器の価値をより深く感じられるようになります。
ご家庭で使用されている陶磁器の中には、作家の作品や昔から伝わる名品など、高い価値を持つものが含まれている可能性があります。陶磁器をより高い価格で手放したい場合は、確かな査定技術や買取実績を持つ業者に相談することが大切です。
陶磁器の買取を検討している方は、ぜひ福ちゃんにご相談ください。経験と知識が豊富な査定士が、お持ちいただいた陶磁器を丁寧に査定します。作家の作品だけでなく、お茶碗や花瓶、皿など幅広い種類の陶磁器の査定に対応しています。
価値ある陶磁器を新たな形で生かしたい方は、福ちゃんの無料査定を活用してみてください。