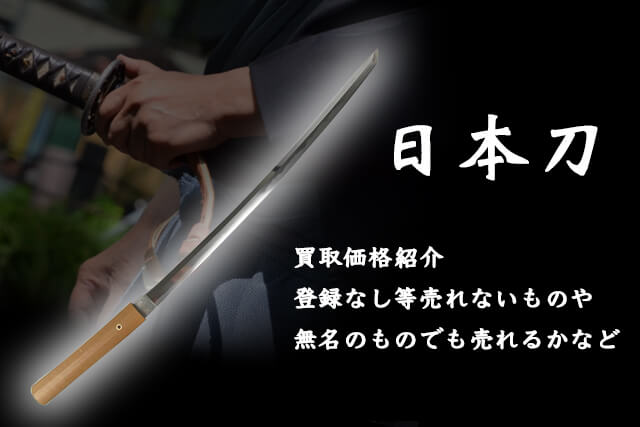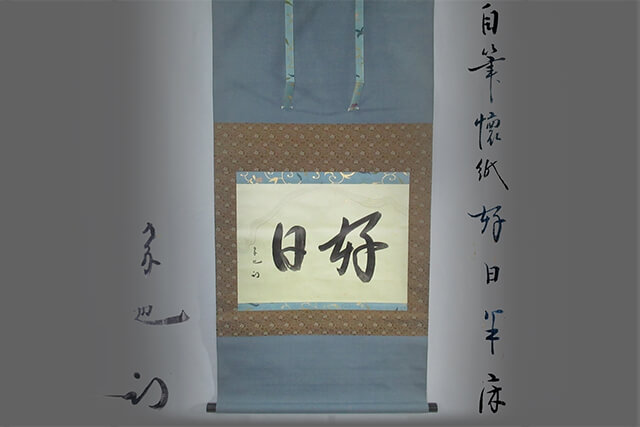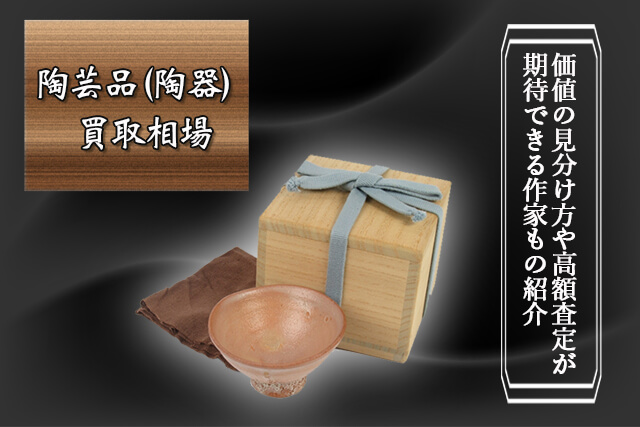- 骨董品
- 2025.11.22
【刀の名前一覧】天下五剣など有名な日本刀のかっこいい名前の由来・種類を徹底解説

日本の刀の名前は難しく、「どのような意味や由来があるのだろう」と気になる方もいるのではないでしょうか。
刀の名前は、作り手の銘や持ち主、伝説、刃文の美しさなどから生まれています。その背景を知ることで、日本刀の価値や奥深さを理解しやすくなるでしょう。
この記事では、天下五剣のような日本刀のかっこいい名前を取り上げ、その由来や特徴を分かりやすく紹介します。刀の基礎知識や見分け方も紹介しているため、ぜひ最後まで読んでみてください。
【記事のポイント】
- ✅刀の名前は、刀工の銘や持ち主の逸話など4つの要素から物語のように生まれています
- ✅太刀と打刀は反りの深さだけでなく、茎(なかご)に切られる銘の向きで見分けられます
- ✅蔵で眠る刀も、福ちゃんの専門査定士が無料で丁寧に価値を見極めますのでご安心ください
刀の名前はどう決まる?物語が宿る4つの由来

刀の名前には、作り手の銘や武将の名を冠したものなど、さまざまな由来があります。一つとして同じものはなく、その名の背景には歴史や信仰などが込められています。
ここでは、刀の名前を決める要素を4つ見ていきましょう。名前の由来を知ることで、名刀と呼ばれる理由がより鮮明に見えてくるでしょう。
①刀工:作り手の銘がそのまま名になる
刀の名付けで多く見られるのは、その刀を作った刀工の名をそのまま冠するケースです。刀工は、別名で刀鍛冶や刀匠とも呼ばれています。
例えば、天下五剣の一つとして知られる「鬼丸国綱(おにまるくにつな)」は、刀工・国綱から名を付けています。三重県桑名市の刀工・村正による「村正」も、名工の名を冠した刀として有名です。
刀工の名前がそのまま刻まれるだけでなく、刀の特徴や逸話と結び付けて名付けられる場合もあります。例えば、国宝に指定されている「童子切安綱(どうじぎりやすつな)」はその代表例です。「安綱」は刀工から取ったものですが、「童子切」は大江山の鬼の頭領「酒呑童子」の首を切ったという伝説に由来しています。
②持ち主:歴史上の所有者にちなんで名付けられる
刀の中には、持ち主である歴史上の人物にちなんで名付けられたものもあります。これらの刀は、所有者の生涯や功績と結び付き、名そのものが歴史を語る存在となっています。
代表的なのが、石田正宗です。名匠・正宗が鍛えた刀を、戦国武将の石田三成が所持したことからこの名が付けられました。石田正宗は重要文化財に指定されており、現在は東京国立博物館に保管されています。
また、脇差「石田貞宗」も同様に、刀工・貞宗による作品を石田三成が所有していたことに由来しています。豊臣秀吉から拝領したと伝えられており、重要文化財に指定されてるのが特徴です。
持ち主の名前にちなんで名付けられた刀は、特定の人物のために鍛えられたオーダーメイドの作品であるケースが多く見られます。
③特徴:見た目や刃文の美しさから名付けられる
刀の名前には、持ち主や刀工の名前だけでなく、見た目の印象や刃文の美しさに由来するものも多くあります。刃文とは、刀の製造過程で生まれる模様のことで、刀ごとに異なる表情を見せるのが特徴です。
例えば、天下五剣の一つに数えられる「三日月宗近(みかづきむねちか)」は、刃文が三日月のように見えることからそのように名付けられました。
刃文は三日月だけでなく、波紋や小沸などさまざまな形や輝きを見せます。天下三作で知られる「粟田口吉光(通称:藤四郎)」が作った短刀「乱藤四郎(みだれとうしろう)は、刃文が激しく乱れていることから名付けられています。
刃文の種類は、記事の後半で解説しているため、ぜひそちらもチェックしてみてください。
④逸話:伝説や物語から生まれる「号」
刀の中には、歴史上の伝説や物語から名付けられたものもあります。このような刀は「号(ごう)」と呼ばれ、刀そのものにまつわる逸話や持ち主の生涯を表しています。
例えば、童子切安綱は、源頼光が大江山の鬼・酒呑童子を斬ったと伝えられることから「童子切安綱」と名付けられました。
にっかり青江は、近江国の武士に関する逸話から名付けられた刀として有名です。逸話の内容は、夜道を歩いていたときに若い女性がにっかり微笑んだため、不気味に感じた武士が刀で斬り捨てたところ、翌朝石灯籠が真っ二つに割れていたというものです。
また、「蛍丸(ほたるまる)」も伝説的な名刀の一つとされています。戦で刃こぼれした際、欠け落ちた破片がひとりでに集まり、刀が元の姿に戻ったといわれています。その光景がまるで蛍が舞っているように見えたことから「蛍丸」と名付けられました。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

まずは基本から!日本刀の主要な種類と見分け方

日本刀は一種類ではなく、さまざまな種類に分けられます。代表的なのは太刀や打刀、脇差などです。それぞれに歴史的な背景と特徴があり、見た目だけでなく使われ方にも違いがあります。
これらを正しく理解することで、日本刀の魅力をより深く理解できるでしょう。ここでは、代表的な日本刀の種類とその見分け方を分かりやすく解説します。
太刀(たち):優美な反りを持つ騎馬戦の主役
太刀(たち)は、平安時代末期に登場した、流れるような反りが美しい日本刀です。長さは約60センチメートル以上と長く、刀身に深い反りを持つのが特徴です。斬撃の際に相手に向かって刀を振り落としやすいとされたため、主に騎馬戦で重宝されました。戦場では、刃を下にしてひもで吊り、腰から下げて携行していました。
太刀には、大太刀(おおだち)と小太刀(こだち)の2種類があります。刃長が約90センチメートル以上の大太刀は、上流の武士が所有する格式高い武器とされるもので、主に騎馬戦で使用されていました。
小太刀は、刃長が約60センチメートル未満の刀です。脇差と見た目は似ていますが、反りの角度が異なるため太刀に該当します。合戦ではなく、儀式や祝いの席で使用されていたのが大きな特徴です。
打刀(うちがたな):武士の魂、腰に「差す」刀
打刀(うちがたな)は、太刀とは異なり刃を上に向けて腰に差すのが特徴です。室町時代の後期、騎馬戦から徒歩での合戦へと戦い方が変化したことにより、武士の間で主流となりました。
太刀が馬上から振り下ろして斬るのに適していたのに対し、打刀は地上で素早く抜き、相手を切り上げるように使うことが想定されています。
刀身は約60センチメートル以上と太刀とそう変わりませんが、反りの角度がやや浅めなのが主な違いです。武士の腰に差す刀として、日本の武士にまつわる歴史が深く刻まれています。
打刀の代表的な例として、徳川家康の次男・結城秀康が佩用した「朱漆打刀拵(しゅうるしのうちがたな)」があります。国宝に指定されており、現在は東京国立博物館に所蔵されています。
(参考:『e国宝 朱漆打刀拵』)
脇差(わきざし)・短刀(たんとう):打刀に添える護身の刃
脇差(わきざし)とは、刀身の長さが約30センチメートル以上60センチメートル未満の刀です。腰の脇に差していたことから、そのままの意味で脇差と呼ばれるようになったといわれています。
戦国時代には、主に打刀と併せて腰に装着し、打刀に折れ・欠けが生じた際の予備の刃として使われました。打刀と同じく刃を上にして腰に差す点が特徴で、騎馬戦よりも接近戦が中心となった時代に重宝されました。
短刀は、さらに小ぶりな刀身約30センチメートル以下の刀を指し、「腰刀(こしがたな)」とも呼ばれます。元々は戦闘用の武器でしたが、桃山時代を過ぎると徐々に実戦では使われなくなっていきます。江戸時代には、主に武家の女性が護身用として持ち歩くことが多くなりました。
一度は聞きたい!有名な「かっこいい刀の名前」一覧

日本刀の世界には、見る者を魅了する名刀が数多く存在します。その中でも、名工の技術と歴史的背景が結び付いた刀は、まさに芸術品ともいえる存在です。
ここでは、日本刀の歴史を語る上で欠かせないかっこいい名前の刀を、3つのカテゴリーに分けて紹介します。刀の名前を知り、その背後にある物語や美意識を理解しましょう。
【天下五剣】日本刀の最高傑作と称される五振り
天下五剣とは、日本の刀の中でも特に歴史的価値が高いことで知られている五振りの名刀です。まさに刀の最高傑作と呼ばれており、名工たちの卓越した技術が高く評価されています。
以下は、天下五剣に数えられる五振りの概要です。
| 名称 | 鑑定区分 | 時代 | 刀工 | 種類 | 特徴・由来 |
| 童子切安綱(どうじぎりやすつな) | 国宝 | 平安 | 大原安綱 | 太刀 | 源頼光が鬼・酒呑童子を斬った伝説で知られている |
| 三日月宗近(みかづきむねちか) | 国宝 | 平安 | 三条宗近 | 三日月に見える刀文と刀工「宗近」の名前を組み合わせている | |
| 鬼丸国綱(おにまるくにつな) | 御物 | 鎌倉 | 粟田口国綱 | 北条家伝来の霊刀で、夢の中の鬼を斬った逸話が由来 | |
| 大典太光世(おおでんたみつよ) | 国宝 | 平安 | 三池典太光世 | 前田家伝来の刀で、病や妖かしを追い払う逸話を持つ | |
| 数珠丸恒次(じゅずまるつねつぐ) | 重要文化財 | 平安〜鎌倉 | 青江恒次 | 日蓮宗を開いた「日蓮」の所有物で、柄に数珠を巻いて魔除けにしていた逸話が由来 |
※鑑定区分は2025年10月26日時点の情報です。
【天下三作・三名匠】伝説の刀工が生んだ名刀
天下三作とは、刀工として名をはせた「粟田口吉光(あわたぐちよしみつ)」「正宗(まさむね)」「郷
義弘(ごうよしひろ)」が手掛けた刀のことです。
以下に、3人の名匠の代表作とその特徴をまとめています。
| 天下三作の代表作 | 刀工 |
| 厚藤四郎(あつとうしろう) | 粟田口吉光 |
| 一期一振(いちごひとふり) | |
| 中務正宗(なかつかさまさむね) | 正宗 |
| 日向正宗(ひゅうがまさむね) | |
| 稲葉江(いなばごう) | 郷義弘 |
| 富田江(とみたごう) |
三名匠は、日本刀史において卓越した技術と芸術性を誇る3人の刀工の呼び名です。平安時代に活躍した名匠「三条宗近(さんじょうむねちか)」「大原安綱(おおはらやすつな)」「友成(ともなり)」の3名で構成され、それぞれが独自の作風を築き上げました。
以下に、天下三作の概要と代表作をまとめます。
| 名匠 | 代表作 |
| 三条宗近 | 小狐丸(こぎつねまる) |
| 銘三条(めいさんじょう) | |
| 大原安綱 | 鬼切安綱(おにきりやすつな) |
| 無銘 伝安綱(むめい でんやすつな) | |
| 友成 | 鶯丸(うぐいすまる) |
| 朱銘 友成(しゅめい ともなり) |
【戦国武将の愛刀】歴史を動かした名刀
戦国時代の武将たちの刀も、歴史を動かした名刀として後に国宝や重要文化財に指定されています。特に「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」の三英傑が所有した刀は、歴史を動かした名刀として今も語り継がれています。
以下は、3人の武将の愛刀とその特徴をまとめたものです。
| 武将 | 愛刀の名称 | 鑑定区分 | 刀工 | 特徴・由来 |
| 織田信長 | へし切長谷部 | 国宝 | 長谷部国重(はせべくにしげ) | 信長が茶坊主の失態を咎め、棚ごと圧し切った逸話に由来している |
| 薬研藤四郎(やげんとうしろう) | 未鑑定 | 粟田口吉光」(あわたぐちよしみつ) | 室町幕府管領の畠山政長が刀を放り投げた際に、薬研を調合する器具に刀が突き刺さったという逸話から名付けられた織田信長に献上された後は本能寺の変で行方不明になる | |
| 豊臣秀吉 | 骨喰藤四郎(ほねばみとうしろう) | 重要文化財 | 骨まで断ち切る切れ味から名付けられた | |
| 一期一振(いちごひとふり) | 御物 | 短刀を作る技術に優れていた吉光の最高傑作と言われている毛利家から秀吉に献上された刀として知られる | ||
| 徳川家康 | 日光助真(にっこうすけざね) | 国宝 | 助真(すけざね) | 家康没後に日光東照宮に奉納したことに由来している |
| 物吉貞宗(ものよしさだむね) | 重要文化財 | 貞宗(さだむね) | 家康が「この刀で戦えば必ず勝利を得た」という逸話に由来している |
※鑑定区分は2025年10月26日時点の情報です。
その他、織田信長の「鬼丸(おにまる)」、豊臣秀吉の「太閤左文字(たいこうさもんじ)」、徳川家康の「ソハヤノツルキ」も、それぞれの生きざまと信念を映し出している刀として有名です。
ゲーム・アニメで人気!実在する刀剣たち

日本の刀は、ゲームやアニメの世界でも数多く登場しています。中でも話題となったのが、実在する名刀をモチーフにしたキャラクターが戦闘を繰り広げる「刀剣乱舞ONLINE」です。
刀剣乱舞ONLINEとは、実在した日本刀を擬人化し、刀剣男子として育成・収集して楽しむシミュレーションゲームです。以下に、ゲーム内で実在しているキャラクターを一部抜粋してまとめています。
| 刀のカテゴリー | キャラクター名 |
| 天下五剣 | 三日月宗近 |
| 大典太光世 | |
| 童子切安綱 剥落 | |
| 鬼丸国綱 | |
| 数珠丸恒次 | |
| 天下三作 | 日向正宗 |
| 厚藤四郎 | |
| 一期一振 | |
| 稲葉江 | |
| 富田江 | |
| 日本三名匠 | 小狐丸 |
| 鶯丸 | |
| 戦国武将ゆかりの刀 | へし切長谷部 |
| 骨喰藤四郎 | |
| 物吉貞宗 | |
| 鬼丸国綱 | |
| ソハヤノツルキ |
このように、天下五剣をはじめ、日向正宗や厚藤四郎など天下三作の名刀もキャラクター名として登場します。キャラクターは名前にちなんだ風貌をしており、性格や能力もそれぞれ異なります。
日本の刀は、歴史的な価値だけでなく、ゲームやアニメなどポップカルチャーの題材としても高い人気を集めているのです。
もっと刀を知るために:刃文(はもん)の種類と見方

日本刀の魅力を語る上で欠かせないのが、刃の表面に現れる模様「刃文(はもん)」です。刃文とは、刀を鍛える際に行う焼き入れによって生まれる模様を指しています。
刃文の形にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると「直刃(すぐは)」と「乱れ刃(みだれば)」の2つです。直刃といっても一種類ではなく、焼き幅が細めの糸直刃(いとすぐは)や細直刃(ほそすぐは)、中くらいの中直刃(ちゅうすぐは)、広めの広直刃(ひろすぐは)の4つに分けられます。
一方の乱れ刃は、波のように揺らめいている刃文です。代表的なものに、丁子の実の形に似た「丁子(ちょうじ)」、それを複雑に重ねた「重花丁子(じゅうかちょうじ)」、波の目のような「互の目(ぐのめ)」などがあります。
また、刃文の内部には「沸(にえ)」と「匂(におい)」と呼ばれる光の粒が現れます。沸は肉眼でも粒状に光って見えますが、匂はより細かな粒子のため肉眼では確認できません。
刀の名前に関するQ&A

刀の名前には、刀工の銘や持ち主の名前、伝説などさまざまな由来があります。名前の意味を知ることは、その刀がどのように生まれ、どのような歴史を歩んできたのかを理解する手がかりになるのです。
ここでは、刀の名前に関してよく寄せられる質問を2つピックアップしています。気になる質問があれば、ぜひ参考にしてみてください。
Q. 日本で最も有名な刀は何ですか?
日本で有名な刀としてまず挙げられるのが、天下五剣です。天下五剣とは、日本刀の中でも特に名工の技と伝説が結び付いた五振りの刀を指しています。
その五振りとは、以下の5つの刀を意味します。
- 童子切安綱
- 三日月宗近
- 鬼丸国綱
- 大典太光世
- 数珠丸恒次
「童子切安綱」は、源頼光が大江山の鬼・酒呑童子を斬ったとされる伝説の刀で、「三日月宗近」は刃文が三日月に見える美しい刀です。
鬼丸国綱は皇室が所有する刀(御物)として知られており、鋒(きっさき)に向かって刀が細くなっているのが特徴です。大典太光世は加賀前田家に伝わる霊刀、数珠丸恒次は、日蓮が数珠を巻いて使用したことで知られています。
いずれも国宝や重要文化財、御物に指定され、高く評価されています。
Q. 国宝に指定されている刀にはどんなものがありますか?
以下では、国宝に指定されている刀の名称とその刀工をカテゴリー別にまとめています。(※2025年10月26日時点の情報です)
| カテゴリー | 刀の名前 | 刀工 |
| 天下五剣 | 童子切安綱 | 大原安綱 |
| 三日月宗近 | 三条宗近 | |
| 大典太光世 | 三池光世 | |
| 天下三作 | 厚藤四郎 | 粟田口吉光 |
| 稲葉江 | 郷義弘 | |
| 富田江 | ||
| 観世正宗 | 正宗 | |
| 中務正宗 | ||
| 日向正宗 | ||
| 日本三名匠 | 銘三条 | 三条宗近 |
| 鬼切安綱 | 安綱 | |
| 戦国武将ゆかりの刀 | へし切長谷部 | 長谷部国重 |
| 日光助真 | 助真 |
天下五剣は全部で五振りですが、上記以外の鬼丸国綱は宮内庁が所蔵しており、皇室御物として厳重に管理されています。数珠丸恒次は国宝ではなく、重要文化財に指定されている刀です。(※2025年10月26日時点)
知名度で言うと、妖刀村正が有名です。村正は、室町時代後期から江戸時代初期にかけて伊勢国(現在の三重県鈴鹿市周辺)で活動した刀工で、鋭い切れ味の刀を大量に鍛えたことで知られています。
村正作の刀は徳川家康の祖父・松平清康の暗殺や、父・松平広忠が刺された事件に関わったと伝えられており、徳川家に災いをもたらす刀と恐れられました。このような逸話から「妖刀」と呼ばれるようになり、今では妖刀村正伝説として知れ渡っています。
その他、天下三作や日本三名匠、戦国武将ゆかりの刀も、いくつか国宝に指定されています。
物語を知れば、刀はもっと面白い
日本刀の名前には、作り手の技だけでなく、持ち主の人生や伝説、逸話などが映し出されています。天下五剣のような名刀や戦国武将が愛した刀には、それぞれに語り継がれてきたドラマがあります。その背景や由来を知ることで、刀が日本の文化や信仰と結び付いた特別な存在だと感じられるでしょう。
ご自宅に古い刀が保管されている場合、刀剣の買取実績が豊富な福ちゃんにご相談ください。福ちゃんでは、全国各地のお客さまから刀剣の査定依頼をいただいております。どのような状態の刀でも丁寧に査定し、価値を正しく見極めます。
「蔵や倉庫で刀が見つかった」「状態が悪くて売れないかもしれない」と悩んでいる方は、まずは福ちゃんの無料査定にお申し込みください。