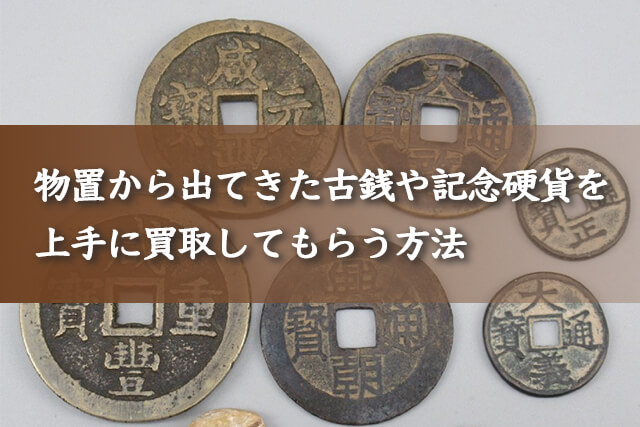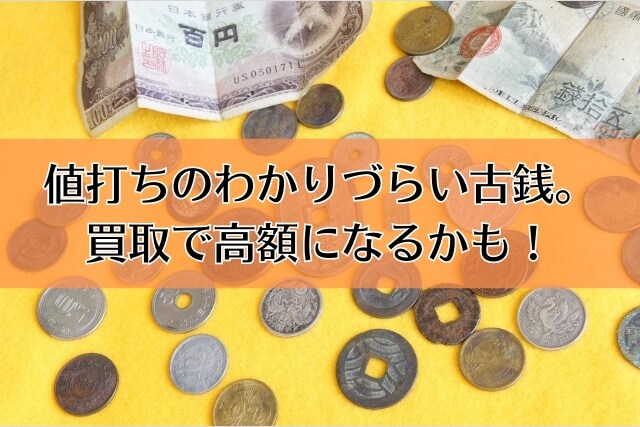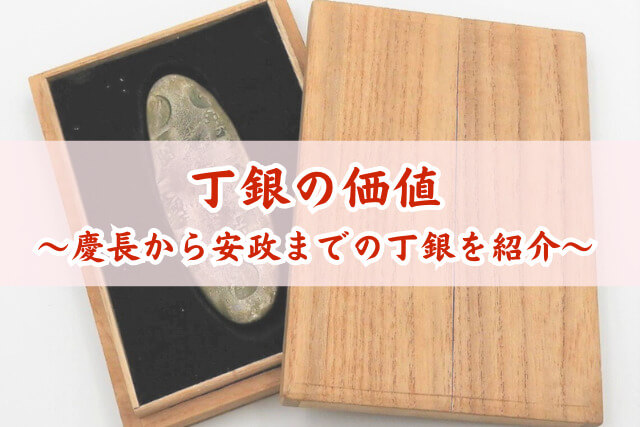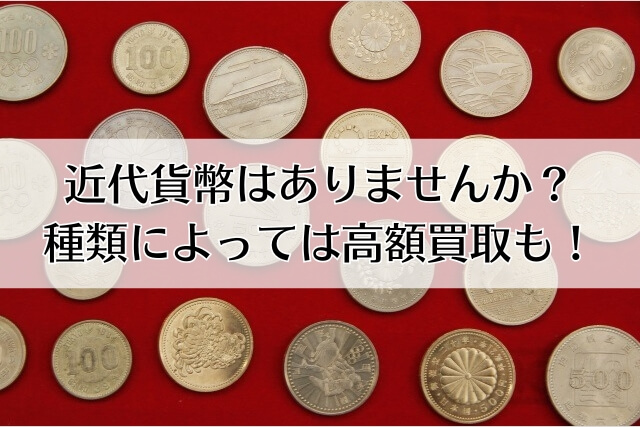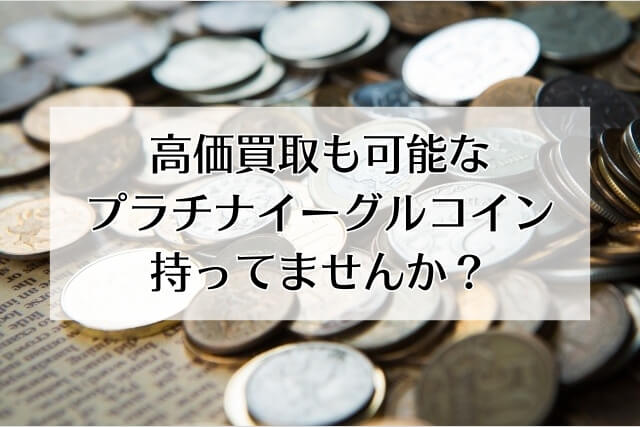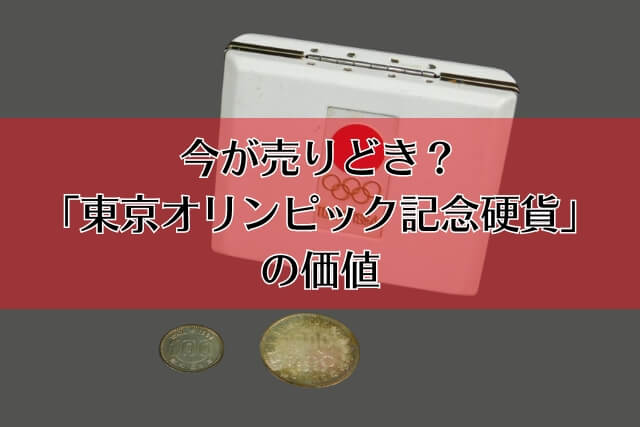- 古銭/記念硬貨
- 2025.11.17
寛永通宝の価値と見分け方は?種類別相場の目安・高く売る手順を解説

寛永通宝は江戸時代に広く流通した穴銭の一種です。歴史的な価値がある品として収集しているコレクターも数多く存在しますが、発行年や鋳造場所によってさまざまな種類に分かれており、それぞれ価値が異なります。
中には驚くほどの高値で取引されるものもあるので、もし「寛永通寶」と刻印された古銭を見つけたら専門業者に査定を依頼してみましょう。
この記事では、寛永通宝の価値や種類ごとの特徴と相場情報、見分け方のコツ、高く売るための手順を初心者にも分かりやすく解説いたします。「寛永通宝の価値を知りたい」「高く売りたいけどどうすれば良いの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。
【記事のポイント】
- ✅寛永通宝は発行時期や鋳造場所により古寛永と新寛永に分かれ、価値が異なります
- ✅二水永や島屋文、母銭の可能性があるものは、特に高い市場価値がつく可能性があります
- ✅専門知識が必要な種類判別も、福ちゃんでは古銭専門の査定士が無料査定いたします
寛永通宝の価値はどう決まる?

寛永通宝の価値を決める基準は大きく分けて3つあります。
- 発行時期
- 鋳造場所
- 保存状態
寛永通宝は発行された時期によって古寛永と新寛永の2つに区分されますが、一般的に古寛永の方が高値で取引される傾向にあります。
また、寛永通宝は各所で製造されましたが、鋳造所ごとに彫りや銅の質などに違いがあるため、特定の鋳造所で発行されたものは高値が付くことがあります。さらに傷や摩耗が少ない美品ほどコレクター需要が高いため、並品に比べると査定額が高くなりやすいでしょう。
ここからは寛永通宝の価値に深く関わる歴史や、古寛永と新寛永の違いについて詳しく見ていきましょう。
寛永通宝の始まり
寛永通宝は、1626年(寛永3年)、常陸水戸の豪商である佐藤新助によって作られた二水永が始まりとされています。
二水永は幕府と水戸藩の許可を得て私的に鋳造したものですが、1636年(寛永13年)には幕府が江戸や近江坂本、浅草橋場に銭座を設置し、公的な鋳造を開始しました。このときに製造された寛永通宝は芝銭、浅草銭、坂本銭などと呼ばれ、大量生産されたこともあって広く市場に流通したといわれています。
その翌年の1637年(寛永14年)には各地で水戸銭、仙台銭といった地方銭が鋳造されるようになり、多種多様な名前の寛永通宝が生まれました。
1668年(寛文8年)からは、江戸の亀戸で鋳造された島屋文を皮切りに、通称「新寛永」と呼ばれる寛永通宝が鋳造されはじめ、古寛永同様、さまざまな種類が発行されました。
寛永通宝は江戸時代を通じて長期間にわたって鋳造され、貨幣の単位が改められた1953年(昭和28年)に失効するまで、有効な通貨として流通していた経歴があります。
【関連記事】
寛永通宝の価値と見分け方は?種類別相場の目安・高く売る手順を解説
古寛永と新寛永の違い
寛永通宝は1668年(寛文8年)を境に、「古寛永」と「新寛永」に分けられます。両者の違いは大きく分けて3つあります。
- 鋳造地
- 書体
- 品質
古寛永は幕府が設置した江戸や近江坂本の鋳造場の他、水戸や仙台など地方に設置された鋳造場でも鋳造・発行されていました。
一方、新寛永は貨幣の鋳造体制を見直し、幕府が新たに設置した江戸の亀戸を中心に鋳造されたものです。幕府の管理下で鋳造されるようになった結果、貨幣の品質は飛躍的に向上したといいます。
また、古寛永は鋳造場所によって書体や品質にかなりの違いが見られましたが、鋳造体制を再整備した後に発行された新寛永は書体が比較的均一になっているところが特徴です。以下ではそれぞれの特徴についてより詳しく深掘りしていきます。
古寛永の特徴
古寛永は鋳造技術がまだ発達していないころに製造されたため、品質にばらつきがある他、書体にも手書き感がうかがえるところが特徴です。そのぶん鋳造地ごとの特色が強く、同じ古寛永でも、どこで製造されたものかによって価値が変動する傾向にあります。
中でも、寛永通宝の試作品ともされる「二水泳」のように、現存数が極めて少なく、非常に高い価値を持つレアコインはコレクター人気が高く、高値で取引されるケースが多くなっています。
新寛永との見分け方のポイントは、表面に刻印された「寛永通寶」の「寶」の貝の下部分が片仮名の「ス」に見えるかどうかです。
また、古寛永の一部には裏面に小さな点があったり、「三」や「十三」といった文字が刻印されたりしているものもあります。
新寛永の特徴
新寛永は江戸の亀戸などに設けられた巨大な銭座の下で、より規格化された銭貨が大量生産されるようになったことに伴い、書体や品質が均一化されているところが特徴です。
また、裏面に文・仙・足といった鋳造地を示す文字(背字)が刻印されるようになった点や、価値を示す波模様が刻まれているところも新寛永ならではの特徴です。
銭そのもののサイズや重量、縁幅などもほぼ統一されていますが、一部の銭の中には他のものより明らかに縁幅が広くなっているものもあります。
前述した古寛永との見分け方は、背字や波線以外にも、「寛永通寶」の「寶」の貝の下部分が片仮名のハの字に見えるかどうか、字体が全体的に細いかどうかによって判別可能です。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

寛永通宝の種類別価値と相場の目安
寛永通宝は種類によって市場での価値に差が出ます。ここでは主な種類とそれぞれの相場を一覧にまとめました。
| 種類 | 相場 |
| 二水永 | 1,000円~数万円 |
| 芝銭 | 数十円~数百円 |
| 浅草銭 | 数百円~1,000円程度 |
| 水戸銭 | 数百円~数万円 |
| 松本銭 | 数百円~1万円程度 |
| 仙台銭/吉田銭/高田銭/岡山銭/長門銭 | 数百円程度 |
| 島屋文 | 数万円~数十万円 |
| 正字文・正字背文 | 数十円~数百円 |
| 退点文 | 数百円~数千円 |
| 正字入文 | 数百円~数千円 |
| 日光御用銭 | 数万円~数十万円 |
| 足尾銭 | 数百円程度 |
| 背広佐 | 数百円~1,000円程度 |
| 耳白銭 | 数百円程度 |
| 石ノ巻銭 | 数百円~1万円程度 |
| 小梅銭 | 数百円~数千円 |
| 白目小字・白目中字 | 数千円~数万円 |
| 一ノ瀬 | 数千円~数万円 |
| 長尾寛 | 数万円~10万円程度 |
※製品の状態によっては買い取れない場合がございます、予めご了承ください。
ここからはそれぞれの種類の特徴について詳しく説明します。
二水永
二水永は、初代寛永通宝として1626年(寛永3年)に鋳造されたものです。表面に漢字の「二」と「水」を組み合わせたような「永」の字が刻印されているところから二水永と呼ばれています。
常陸水戸の豪商である佐藤新助が最初に鋳造した1626年(寛永3年)のものは裏面に「三」の刻印がありますが、新助の没後、その息子である庄兵衛が鋳造を再開した際の二水永には、1636年(寛永13年)に鋳造したことを意味する「十三」という文字が刻まれているのが特徴です。
寛永通宝の中でも特に歴史が古く、かつ私人による鋳造であったという事情から発行枚数はさほど多くなく、そのぶん残存数も少ない傾向にあります。そのせいかコレクター市場では希少性が高く評価され、状態が良ければ1枚あたり数万円の買取価格が付くでしょう。
芝銭
芝銭は、1636年(寛永13年)に江戸の芝綱縄手で鋳造されたものです。前述した二水永とは異なり、こちらは江戸幕府が設置した銭座で鋳造された公的な寛永通宝となります。「通」のしんにょうや「永」の上の点などが草書体(草点)になっているものが多いところが特徴です。
当時、市場で広く流通したことから残存数も多く、希少性があまりないぶん、コレクター間では
数十円~数百円程度で取引されるケースが一般的です。ただし、鋳型を作るために利用された母銭の場合はより高値が付くこともあります。
浅草銭
芝銭と同じく、江戸幕府が浅草に設置した鋳造場で製造された公的な寛永通宝です。別名「志津磨百手」と呼ばれるほど多様な書体が用いられているところが特徴で、一枚ごとに違うのではないかという説もあるほどです。
浅草銭はその書体の多さ故に、特定の書体のものはコレクター人気が高く、高値で取引される事例も少なくありません。一般的な浅草銭は数百円程度が相場ですが、人気のある書体なら1,000円以上の値が付くこともあるでしょう。
ただし、書体の違いは微々たるもので、一見しただけでは判断が付かないため、専門業者に査定を依頼することをおすすめします。
水戸銭
水戸銭は常陸水戸に設けられた銭座で1637年(寛永14年)から発行されたものです。他の種類に比べると、寛永通宝の「通」のしんにょうの左端が中央の穴に密着している、しんにょうのはらいが美しい、「永」の字の中心線に傾きがあるなどが特徴です。
古寛永の地方銭の中では、後述する仙台銭と並んで発行枚数が多いことから、希少性はさほど高くなく、市場での相場も数百円程度となっています。
ただし、水戸銭は書体にばらつきがあることから、コレクター人気の高い書体のものは数万円で取引されるケースもあります。書体の違いは専門知識がないと判断が難しいため、正確な価値が知りたい場合は専門業者に査定を依頼しましょう。
松本銭
松本銭は、1637年(寛永14年)に現在の長野県松本市で発行された寛永通宝です。「寛永通寶」の「寶」の字の左半分が、斜めになっている「斜宝」という字体になっているところが大きな特徴です。
寛永通宝の中では発行枚数が少ないこともあり、一般的な相場は数百円程度ですが、保存状態が良いものは1万円程度で取引されるケースもあります。
ただし、松本銭は過去に大量の偽造品が流通したことがあります。精巧に作られた偽物はぱっと見ただけでは本物と区別が付きにくいため、もし手元に松本銭があるのなら、専門知識を持った査定士に見てもらいましょう。
仙台銭/吉田銭/高田銭/岡山銭/長門銭
仙台銭や吉田銭、高田銭、岡山銭、長門銭は、いずれも地方の鋳造場で製造された古寛永の一種です。全て1637年(寛永14年)に作られたもので、古寛永の中でも初期のものに分類されます。
地方銭は鋳造場所によって書体などに違いが見られることから、じっくり観察すればどの地方で作られたものか分かるでしょう。例えば仙台銭は「寛永通宝」の文字が小さめ、吉田銭は「永」の字の横線が長く伸びて見える、などの特徴があります。
いずれも残存数は比較的多めなので1枚あたりの価値は数百円程度が相場ですが、状態が良ければより高値が付くこともあるでしょう。
島屋文
島屋文は、1668年(寛文8年)に鋳造された寛永通宝です。新寛永通宝の初代に当たるもので、当時、江戸に新たに設置された亀戸の鋳造場で製造されました。
名前にもある「島屋」という書体が使われているのが大きな特徴で、全体的に丸みを帯びており、「通」の右上部分が片仮名の「ユ」に見えるところが他の種類との違いです。裏面は「文」の字があるものとないものがあり、後者は島屋文の中でも「無背」と呼ばれます。
市場では無背よりも通常の島屋文の方が価値が高く、無背は数万円~であるのに対し、通常のものは数十万円程度の高値が付く場合が多くなっています。
島屋文は数ある寛永通宝の中でも特に高く評価される部類に入るので、ご自宅やご実家で島屋文を見つけたら、専門業者に査定してもらうのがおすすめです。
正字文・正字背文
正字文は、1668年(寛文8年)に鋳造された新寛永の一種です。「寛永通宝」の字が標準的な書体(正字)で刻印されているところが特徴で、裏面に「文」の文字が彫られているものは正字背文と呼ばれています。
前述した島屋文と似ているため見分けが付きにくいですが、島屋文は全体の彫りが深めであるのに対し、正字文は彫りが浅めという違いがあります。また、正字文は「通」の右上が片仮名のコの字に見える、「永」の右がわのハネが小さい、「寶」の頭の点が短いなどが特徴です。
正字文は発行枚数が多いため、相場は数十円~数百円となっていますが、珍しい書体のものは高値が付くこともあります。
退点文
退点文は、1668年(寛文8年)に鋳造されたものです。裏面に刻印されている「文」の点が右に寄っている「退点」という字体が用いられていることが名前の由来です。
新寛永の一種ですが、裏面に「文」が刻印されている文銭の中では最も古寛永の要素を備えた貨幣とされています。
退点の他にも、「寛永通寶」の「寛」の字の前足が短く斜めに出ている点や、裏面の「文」の字が太く、横線にうねりがあるといった特徴が見られます。なお、同じ退点文でも字体には差があり、文の字画が太いもの、文の横線のうねりがないもの、文の点が小さいものなど、さまざまなバリエーションがあります。
特定の字体は高く評価され、数千円以上の値が付くこともある一方、評価が低い字体は数百円程度に留まるのが一般的です。
正字入文
正字入文は島屋文などと同じく、1668年(寛文8年)に江戸の亀戸で鋳造された新寛永の一種です。「寛永通寶」が正字で刻印されているところは前述した正字文と共通していますが、裏面に刻まれた「文」の字の下半分が漢字の「入」に似ているところが大きな違いで、「入文」という名の由来にもなっています。
発行枚数が多く、残存しているものも少なくないことから、市場での相場は数百円程度です。
ただし、保存状態の良いものは数千円程度の高値が付く場合もあります。
他の種類と比較的見分けやすい貨幣ですが、書体のレア度などは専門家が見ないと判断しにくいので、専門業者に査定してもらった方が良いでしょう。
日光御用銭
日光御用銭は、1714年(正徳4年)に鋳造された新寛永の一種です。同時期に佐渡で鋳造された「正徳佐」と字体が似ていますが、こちらの方が流通数が少なく、高値で取引されています。
他の種類との見分け方は、表面に刻印されている「寛永通寳」の「寳」の左上にある「尓」のハネの有無で、ハネがなければ日光御用銭と判断できるでしょう。
発行の背景については諸説ありますが、一説によると徳川家の日光参拝に用いられたという説が有力視されており、歴史的な価値がある品としてコレクター市場でも高く評価されています。
残存数も少ないことから希少性も高く、通常品なら数万円程度、美品であれば数十万円程度の高値で取引されることもあります。
足尾銭
足尾銭は、栃木にある足尾銅山由来の銅を原料とした新寛永の一種で、下野国足尾銭と呼ばれることもあります。裏面に「足」の文字が刻印されているため、他の種類とは一目で区別できます。
また、サイズが均一でないところも足尾銭の特徴で、一般的には大きいものほど評価も高くなりやすいです。字体にも違いがあり、「寛永通寶」の「寛」の字の尾が縁の右端付近まで延びているものや、逆に縁よりもかなり内側に収まっているものなどがあります。
足尾銭自体は発行枚数が多いことから数百円が相場となっていますが、このような書体の違いによって評価が左右されることもあるため、「高く売れないだろう」と自己判断せず、専門業者に査定してもらうことをおすすめします。
背広佐
背広佐は1717年(享保2年)に佐渡の銭座で鋳造された新寛永の一種です。佐渡で鋳造された寛永通宝の裏面には「佐」の字が刻印されている「背佐」という様式が用いられていますが、背広佐はその中でも「佐」の文字が大きく、はっきりと刻まれているところが大きな特徴です。
なお、享保期の背広佐は多種多様な書体が用いられており、書体によって評価に差が出ます。一般的な背広佐の相場は数百円~1,000円程度ですが、書体や保存状態によってはそれ以上の高値が付くこともあります。
ただし、書体ごとの評価の違いは専門家でないと分からないため、裏面に「佐」の字がある寛永通宝が手元にある場合はプロに査定してもらいましょう。
耳白銭
耳白銭は、1714年(正徳4年)に亀戸で鋳造された新寛永の一種とされています。貨幣の外輪を示す「耳」が「シロイ(江戸弁で広いの意)」ことから「耳白銭」と呼ばれるようになったという説が一般的ですが、縁取りが白っぽい色をしているからという説もあるようです。
当時は、江戸幕府の側用人である新井白石が行った「正徳の治」により、貨幣の信頼精を回復させるための良質な正徳小判金が発行された時期にあたります。その影響で、寛永通宝も銅銭としての価値の改善が求められたことから、良質な銅が使われているところが特徴です。
市場の相場としては数百円程度が主流ですが、寛永通宝の中では比較的希少性の高い銅銭と認識されていることから、保存状態によっては高値が付けられる事例もあります。
石ノ巻銭
石ノ巻銭は、陸奥国石巻で1728年(享保13年)に鋳造された新寛永の一種です。裏面に「仙」の字が刻印されているところが特徴ですが、「通」の上部分が片仮名のコの字になっているコ頭と、マの字になっているマ頭の2種類があります。
裏面に「仙」の文字がある背仙は元々数が少ないですが、その中でもマ頭はより希少性が高いため、ものによっては1万円程度の高額査定が提示されることもあります。ただし、一般的な相場は数百円程度です。
なお、石ノ巻銭には裏面に「仙」の字がない無背のものもありますが、仙の字がある通常のものに比べると相場は下がる傾向にあります。
小梅銭
小梅銭は、1737年(元文2年)に現在の東京都墨田区に当たる江戸の小梅村で発行された新寛永です。裏面には小梅村鋳造を意味する「小」の文字が打たれているため、他の種類と簡単に見分けが付きます。また、他よりもやや軽量に作られているところも特徴の一つです。
ただし、小梅銭は穴のサイズや字体などによって複数の種類に分かれており、それぞれ評価に差があります。例えば、中央の穴が小さくなっている「狭穿背小」と呼ばれるものは、中央の穴が広い「広穿背小」よりも高値が付きやすいでしょう。
また、広穿背小のうち、「小」の字の右点が真ん中の縦線に近く、かつ縦線のはねがない「広穿狭背小」という種類もあります。
小梅銭の相場は数百円程度ですが、上記のような作りや書体の違いによっては数千円程度の値が付くこともあります。
白目小字・白目中字
白目とは、白銅を主原料として鋳造された寛永通宝のことです。寛永通宝の多くは赤みを帯びた茶色をしているため、全体的に白っぽい色をしている場合は白目と判断できます。
白目は書体によってさらに白目小字と白目中字の2種類に分かれています。小字は「寛」の前足が上に跳ね上がっており、中字は文字の横幅が広いところが主な特徴です。
一般的な相場は数千円程度ですが、特に小字の方は希少性が高いため、状態によっては数万円の査定額が付くこともあります。中字の方も状態が良ければ1万円程度の高値が付く可能性があるでしょう。
一ノ瀬
一ノ瀬は、1740年(元文5年)以降に鋳造されたといわれている寛永通宝です。裏面に鋳造地である「一ノ瀬」を示す漢字の「一」が刻印されているのが大きな特徴です。
また、他の種類に比べると文字が細く、中央の穴が比較的大きめに作られているのも特徴です。一ノ瀬は書体によってさらに細かく分類されており、「寛」の字の足が高くなっているものは「高寛」、低いものは「低寛」と呼ばれています。
さらに、裏面に一の字があるかないかによって「背一」と「無背」の2種類に分かれています。特に、高寛背一は非常に希少性が高く、数万円以上の高値が付くケースもあるでしょう。一般的な相場は数千円程度です。
長尾寛
長尾寛は、1768年(明和5年)に製造された寛永通宝です。裏面に21の波紋が刻まれていることから、21波と呼ばれることもあります。また、「寛」のはねが長く延びているところも特徴で、そのはねが短いものは「短尾寛」と区別されます。
型抜けが悪かったため、すぐに改良版である短尾寛に変更されたことから、残存数は非常に少なく、コレクター市場ではプレミア品として扱われることが多いです。そのぶん高額査定になりやすく、状態の良いものであれば数万円~10万円程度の高値が付くことも期待できます。
レア判定チェックリスト

手元にある寛永通宝がレア品かどうか判定するには、以下3つのポイントをチェックするのが基本です。
- 表面書体
- 背文字と縁幅
- 大ぶり・エッジ立ち
表面書体は「寛永通寶」に用いられている書体、背文字は裏面に刻まれた文字、縁幅は貨幣の縁の幅の大きさを指します。
また、サイズが大ぶりのものや、エッジ(縁)が立っているものは鋳造の基準となる母銭の可能性があり、プレミアが付く可能性が高くなります。
ここからはそれぞれのチェックポイントについて詳しく説明しましょう。
表面書体
寛永通宝の表面には「寛永通寶」という文字が彫られていますが、鋳造場所や製造時期によって書体に違いが見られます。鋳造技術が未発達だった古寛永の初期は、手彫り感が強く、書体にもばらつきが見られるところが特徴です。
例えば古寛永の中でも特に高値が付きやすい二水永は、「永」の字が漢字の「二」と「水」に見えるという特徴があります。また、ものによっては数万円の値が付くこともある松本銭は、「寶」の足が片仮名のスの字に見えるところが特徴です。
このように、表面書体の違いをチェックすれば、高値が期待できる寛永通宝かどうかを判断できます。ただし、書体の違いは複雑であり、専門知識がないと正確に判断するのは困難です。
「高値で売れないだろう」と思っていた寛永通宝が実はレア品だったという可能性もゼロではないので、自己判断で終わらせず、専門業者に査定を依頼してみましょう。
背文字(佐/仙/小/一)と縁幅(蛇ノ目/耳白)
寛永通宝の裏面には、鋳造場所を表す「佐」や「仙」「小」「一」といった背文字が刻印されているものがあります。
一般的に、背文字があるものは背文字のないもの(無背)よりも希少価値が高くなるため、市場でも高値が付きやすい傾向にあります。また、銅銭の縁幅にも注目してみましょう。縁幅が明らかに大きいもの(大濶縁)は、当時流行した蛇の目傘に似ているとして「蛇ノ目」と呼ばれ、コレクターから高い人気を誇っています。
また、同じく縁幅が広く、色が白っぽいものは耳白と呼ばれ、こちらも希少性が高いレア品として高値が付けられることがあります。縁幅については他のものと比較すれば分かりますが、手元に他の種類の寛永通宝がないと判断しにくいため、プロに査定してもらった方が良いでしょう。
大ぶり・エッジ立ち=母銭疑い
鋳造の基準となる母銭は、そこから作った鋳型で製造される子銭よりも数が少ないぶん、レア品として扱われます。
母銭は子銭に比べて全体的にサイズが大きく、かつエッジが立っている(縁が鋭い)ところが特徴です。一般的な寛永通宝と明らかに造りが異なるものは母銭である可能性があるので、専門業者に査定してもらいましょう。
なお、母銭は子銭に比べて以下のような特徴もあります。
- 彫りが深い
- 穴の四角がきれい
- 銅の質が高い
模様がはっきりしているものや、穴の角が鋭角でしっかりしているものなどは母銭の可能性があります。また、母銭は子銭よりも質の良い銅を使っており、かつ子銭のように市場に広く出回っていないことから、比較的劣化が進んでいないという特徴もあります。
ただし、これらの違いを見分けるのは専門家でないと難しいでしょう。
高く売る手順
寛永通宝を売る方法は複数ありますが、安心かつ高値で売却したいのなら買取専門業者を利用するのがおすすめです。
買取専門業者には古銭に関する専門知識を備えた査定士が在籍しており、寛永通宝の種類や保存状態などを丁寧に査定した上で、適正な買取価格を提示してくれます。買取専門業者に査定を依頼する際の具体的な流れは以下の通りです。
- 買取専門業者のWebサイトなどから査定の相談・依頼を申し込む
- 好きな買取方法を選んで査定してもらう
- 査定額に納得できたら必要な手続きを行い、売却金を受け取る
買取方法は業者によって異なりますが、出張買取や宅配買取に対応しているところなら、自宅にいながら寛永通宝の査定を依頼できます。出張査定の場合は問い合わせの際に都合の良い査定日時を決めれば、当日に査定士が自宅を訪問してくれます。
一方、宅配買取の場合は電話やWebサイトなどから査定申し込みを行った後、段ボールなどに査定してもらいたいものを梱包し、宅配業者に渡せばOKです。
なお、寛永通宝をはじめとする古銭は、古くなるほど劣化が進行するため、なるべく早く売却するのがおすすめです。また、寛永通宝以外の古銭も手元にある場合は、複数個をセットにして買取に出すと査定額が高くなる可能性があります。
寛永通宝の買取は「福ちゃん」へ
寛永通宝は江戸時代に広く流通し、数百年にわたって価値を保っていた貨幣です。中には希少性の高いものもあり、コレクター市場で高値で取引されているものも少なくありません。
ただし、寛永通宝は鋳造期間や鋳造場所などによってさまざまな種類に分かれていることから、手元にある寛永通宝がどの種類で、どのくらいの価値があるのか正確に見極めるのは困難です。
もしご自宅やご実家で寛永通宝を見つけたら、専門知識が豊富な買取業者に価値を査定してもらってみてはいかがでしょうか。
福ちゃんでは寛永通宝をはじめとする穴銭買取に精通しているプロが在籍しているため、古銭に適正な価格を付けることが可能です。買取方法も店舗買取の他、便利な出張買取や宅配買取にも対応しており、都合に合わせて好きな方法を選択できます。
査定料や出張料は無料ですので、お手元に寛永通宝や古銭がある型は、ぜひ福ちゃんにお任せください。