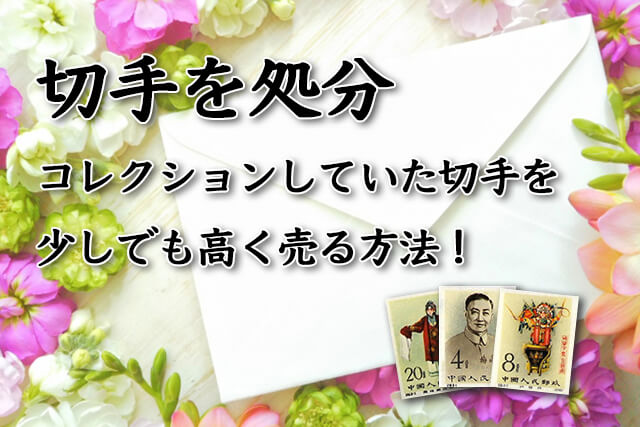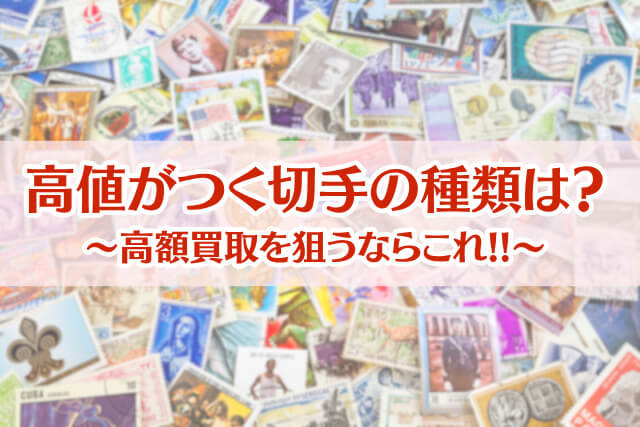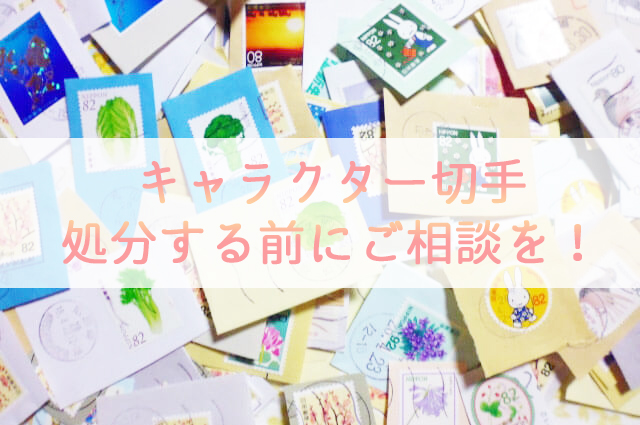- 切手
- 2025.11.18
簡易書留は切手で支払い可能!合計料金や窓口での送り方、一般書留との違いを解説

「大切な書類を送りたいけれど、簡易書留の支払いって切手でできるの?」そのような疑問をお持ちではありませんか。実は、郵便局で扱うサービスの多くは、切手で支払えます。なお、現金との併用も可能なため、少量の切手が余っているときにもよいでしょう。
この記事では、切手で簡易書留を送る際の合計料金から、郵便窓口での送り方の手順、他の郵送方法との違いまで分かりやすく解説します。なお、大量の切手が余っているなら、高額査定も期待できる買取を依頼するのもおすすめです。
【記事のポイント】
- ✅簡易書留の支払いは郵便局窓口で切手と現金を併用できます
- ✅料金は基本料金+350円で、一般書留とは補償額などが異なります
- ✅大量の切手は福ちゃんの無料査定で高額価値を丁寧に判断いたします
結論:簡易書留は切手で支払いできます

結論として、簡易書留の料金は郵便局の窓口であれば切手で支払えます。なお、簡易書留以外にも、郵便局の窓口で扱うサービスの中には原則として切手払いが可能です。ただし、コンビニ支払いやポスト投函では、切手で簡易書留の支払いはできません。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

簡易書留の合計料金はいくら?【2025年10月最新】

簡易書留の合計料金は、定形郵便や定形外郵便など種類や重さ別に適用される「基本料金」と、簡易書留の「加算料金」の2つの要素から成り立っています。なお、郵便料金は2024年10月1日から改正されたため、最新の情報を元に合計料金を紹介します。(2025年10月現在)
「基本郵便料金」 + 「簡易書留の加算料金(350円)」
簡易書留の料金がいくらかかるのかは、以下の式により求められます。
「基本郵便料金」 + 「簡易書留の加算料金」
基本郵便料金は郵便物の種類や重さにより異なります。2024年10月1日より、基本料金は新料金に変更になっており、2025年10月現在改定はありません。計算する時は間違えないように注意しましょう。
また、簡易書留の加算料金は一律350円です。こちらは、2024年10月1日の改定時も旧料金から変更はありません。
【早見表】手紙・荷物の重さ別の合計料金
手紙や荷物の重さ別の簡易書留の合計料金は以下の通りです。(2025年10月現在)
| 種類 | 重量 | 基本郵便料金 | 簡易書留の加算料金 | 合計料金 |
| 通常はがき | – | 85円 | 350円 | 435円 |
| 定形郵便物 | 50g以内 | 110円 | 460円 | |
| 定形外郵便物規格内※ | 50g以内 | 140円 | 490円 | |
| 100g以内 | 180円 | 530円 | ||
| 150g以内 | 270円 | 620円 | ||
| 250g以内 | 320円 | 670円 | ||
| 500g以内 | 510円 | 860円 | ||
| 1kg以内 | 750円 | 1,100円 |
※「規格内」は、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内です。
【簡単3ステップ】切手を使って簡易書留を送る手順

簡易書留を切手で支払って送る方法は、以下の通りです。
ステップ①:荷物を準備して郵便局の窓口へ
ステップ②:窓口で「簡易書留で」と依頼し、料金を確定
ステップ③:切手で支払い、控えを受け取る
ステップ①:荷物を準備して郵便局の窓口へ
簡易書留で郵送したい荷物や手紙などを用意し、封筒に入れましょう。なお、このときに所定の料金の切手を貼る必要はありません。また、簡易書留の差出に必要な書類は郵便局の窓口に用意してあるため、封筒と支払い用の切手、必要であれば現金を持参するだけで問題ありません。
ステップ②:窓口で「簡易書留で」と依頼し、料金を確定
郵便局についたら、窓口で簡易書留で送付したい旨を説明し、「書留・特定記録郵便物等差出票(2枚複写)」を受け取り住所・氏名など必要事項を記入しましょう。備え付けてあるものを記載し、窓口に持っていっても問題ありません。
窓口で書き終わった差出票と荷物を預けると、サイズや重さを計り、最終的な料金を確認できます。
ステップ③:切手で支払い、控えを受け取る
料金を切手で支払いたいことを伝えて支払いましょう。手続きが終わると「書留・特定記録郵便物等受領証」が渡されます。郵便物の追跡時などに必要になるので、なくさないように大切に保管しましょう。
簡易書留・一般書留・特定記録の違いとは?【徹底比較】

簡易書留、一般書留、特定記録はそれぞれ料金や補償額、追跡サービスが異なります。
料金・補償額・追跡サービスの違いがわかる比較表
| 項目 | 簡易書留 | 一般書留 | 特定記録 |
| 料金 | 基本料金+350円 | 郵便物:基本料金+480円ゆうメール:基本運賃+420円 | 郵便物:基本料金+210円ゆうメール:基本運賃+160円 |
| 損害補償の有無 | あり(5万円まで) | あり(10万円まで)※5万円ごとに+23円加算し上限500万円まで可 | なし |
| 配達方法 | 原則対面での手渡し(一戸建て住宅の場合、設置した宅配ボックスへ配達) | 原則対面での手渡し(一戸建て住宅の場合、設置した宅配ボックスへ配達) | 郵便受箱に配達 |
| 追跡の有無 | あり(引受けと配達のみを記録) | あり(引受けから配達までの送達過程を記録) | あり(引受けのみ記録) |
簡易書留は、料金を抑えながら損害補償を付けたいときにおすすめの方法です。ただし、限度額は5万円のため、高額の商品を送るのには適していません。
一般書留は万が一郵便物が破損した際、実損額の補償を受けられます。しかし、料金は上記3つの中で最も高額なため、安価なものを送るのであれば、他の方法が良いでしょう。
特定記録は、郵便を差し出した記録は残るものの、破損時の補償はありません。このため、請求書などの送付に適しています。
切手での簡易書留支払いに関するQ&A

ここでは、簡易書留の料金を切手で支払うときにありがちな、以下の悩みにQ&A形式で回答します。
- 古い記念切手や海外の切手は使えますか?
- 切手は封筒のどこに貼ればいいですか?
- 料金分の切手がない場合、現金と併用できますか?
古い記念切手や海外の切手は使えますか?
日本の切手であれば、古い記念切手や料金改定前の切手でも支払いに利用できます。一方、海外の切手は日本国内の郵便物の料金支払いに使用できません。
【関連記事】
外国切手(海外切手)とは?切手の種類や魅力を解説
切手は封筒のどこに貼ればいいですか?
縦長の封筒なら左上、横長の封筒なら右上に貼るのが一般的です。しかし、料金分の切手であれば直接貼らずに窓口に持参し、最終的な料金を確認してもらった方が確実です。
料金分の切手がない場合、現金と併用できますか?
支払時は現金とも併用できます。切手の枚数が少ないときは、現金も持参して支払うとよいでしょう。また、切手支払いではおつりがでないため、料金を超過しそうであれば現金と併用するのがおすすめです。
大量の切手が余っているなら「買取」という選択肢も
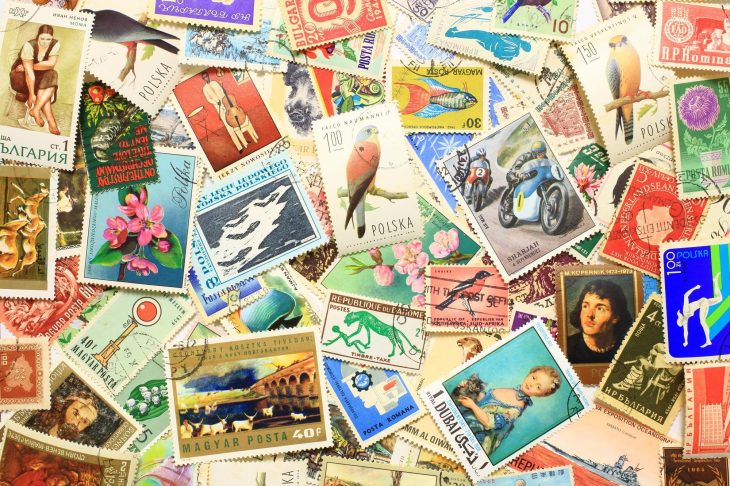
記念切手や旧料金の切手など、切手が使いきれないほど余っているなら買取サービスを活用するのもおすすめです。買取であれば使っていない切手を現金化できるだけでなく、希少価値の高い切手は高額査定の可能性もあります。
余った切手の買取は福ちゃんへ
「シートで多くの記念切手を保管している」「昔集めていたコレクションがあるけれど価値が分からない」などのお困りごとがあるときは、買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。買取業者では、切手専門の査定士が切手の価値を正確に査定し買取金額を決定します。
一口に切手といっても「普通切手」や「記念切手」、「特殊切手」など、種類は多岐に渡ります。また、同じように見える切手であっても、発行年度や枚数によって価値が大きく異なることも少なくありません。また、買取では汚れのある切手や古い切手も査定が可能なため、希少価値が高ければ高額査定も期待できます。
福ちゃんでは、どのようなジャンルの切手であっても、経験豊富な査定士の丁寧な査定が可能です。査定額にご納得いただけないときは、買取をお断りいただけます。査定料やキャンセル料などの手数料は一切無料のため、大量の切手にお困りのお客様は、ぜひ福ちゃんまで査定をご依頼ください。