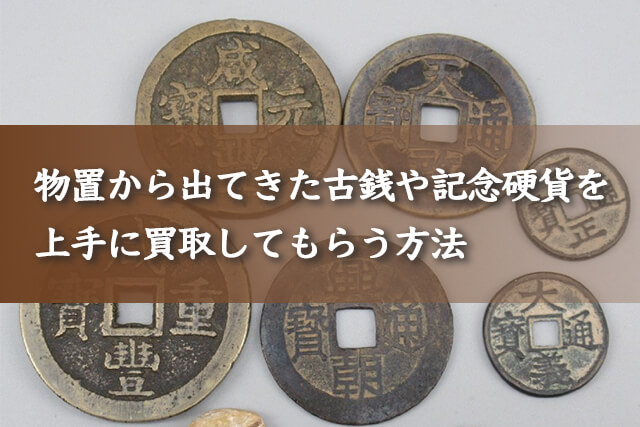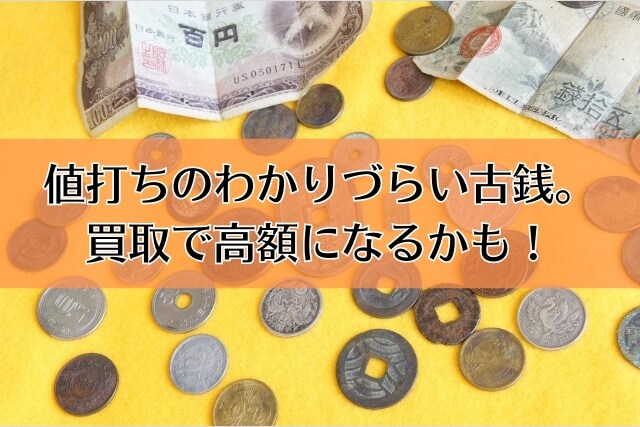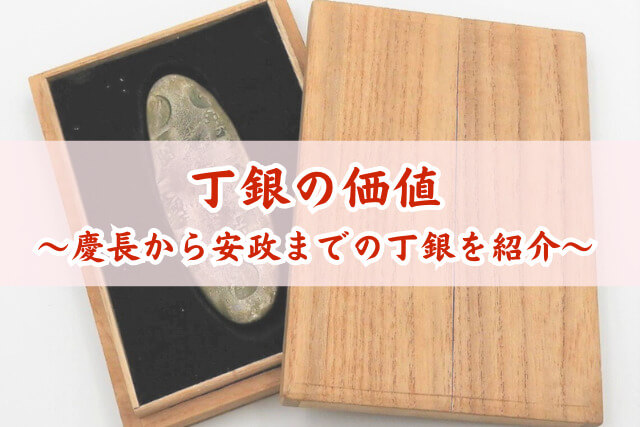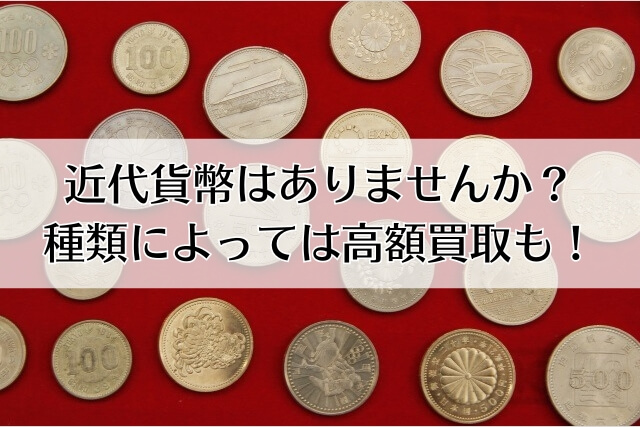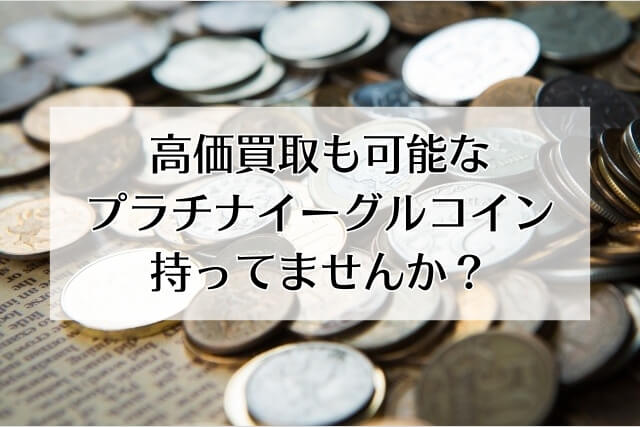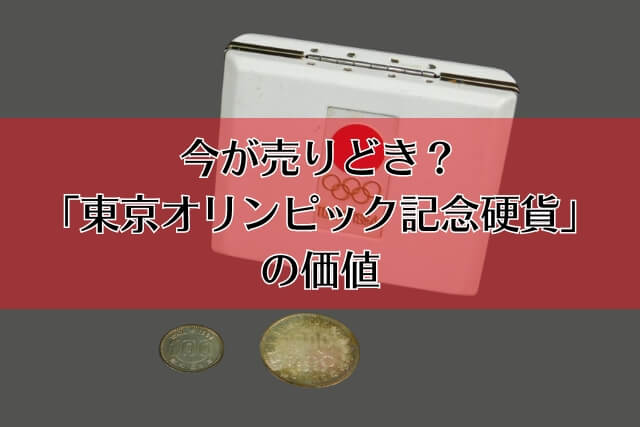- 古銭/記念硬貨
- 2025.11.12
100円札の価値はいくら?歴代百円札の種類・相場と高く売る方法まとめ

現代は貨幣になっている100円ですが、かつては百円札として流通していた歴史があります。現在製造されていない百円札は歴史的な価値があるため、専門店で鑑定してもらえれば高値が付くかもしれません。
なお、百円札の価値は種類や保管状態などによって異なるため、査定に出す前におおよその相場を把握しておきましょう。
本記事では歴代百円札の種類やそれぞれの相場、昔の百円札を交換・買取に出す方法をまとめました。ご自宅やご実家で百円札を見つけて取り扱いに困っている方はぜひご覧ください。
【記事のポイント】
- ✅現在も使える100円札(聖徳太子・板垣退助)でも、額面以上の価値がつく可能性がある
- ✅明治時代の「めがね100円」など、種類によっては数百万円以上の価値を持つ幻の百円札も存在する
- ✅正確な価値を知るには専門家の査定が不可欠。福ちゃんなら手数料無料でプロが価値をしっかり見極めます
今でも使える100円札とその価値【A号券・B号券】

日本で初めて百円札が発行されたのは1872年(明治5年)で、現代に至るまで8種類が製造・発行
されています。
ただし、その全てが現在も有効というわけではなく、法律上現在も有効とされている紙幣はA号券とB号券の2種類のみです。これらは現在も店頭の決済などに使えますが、各種ATMや自動販売機、セルフレジ、釣り銭機などでは百円札は利用できないケースがほとんどなのであらかじめ注意が必要です。
なお、店頭での決済に用いる際は額面(100円)のままですが、専門業者の査定に出せば数百円〜数千円の高値が付く場合があるので、買い取りに出した方がお得でしょう。
ここでは、この2種類の100円札について詳しくご紹介します。
日本銀行券A号100円(聖徳太子)
日本銀行券A号100円(聖徳太子4次100円)は、第二次世界大戦後の新円切替に伴い、1946年(昭和21年)から1956年(昭和31年)まで発行された百円札です。
当時の日本は、終戦による戦時補償や退役軍人に支払う退職金などによって銀行券の発行高が大幅に増加し、インフレが加速しました。そこで日本銀行は、1円以下を除く全ての紙幣を無効とし、新しい紙幣を発行する新円切り替えを実施しました。
このA号100円は、かつて存在した「い100円」のデザインをそのまま流用していますが、旧円と新円を区別するため、中央にある「百圓」の文字の下に、新円であることを表す赤い標識が印刷されています。
A号100円は法的には有効な銀行券とされているため、実際に支払いに使用することも可能と説明しましたが、この赤色標識がない旧円は法的な効力を失っており、支払いには使えないので要注意です。
デザインとしては、表面には聖徳太子の肖像と法隆寺夢殿が描かれ、裏面には法隆寺伽藍が美しく配置されているのが特徴といえるでしょう。現在も有効な紙幣なので、より古い百円札に比べると相場はやや下がりますが、それでも額面以上の数百円~数千円程度で取引されています。
日本銀行券B号100円(板垣退助)
日本銀行券B号100円(板垣退助100円)は、1953年(昭和28年)から1974年(昭和49年)まで発行された、いわゆる「最後の100円紙幣」として知られています。
緊急経済政策であるドッジラインの実施によってインフレが集結し、物価変動も落ち着いてきた頃、前述したA号100円紙幣の偽物が流通するようになりました。そこで日本銀行は紙質の改良や精巧な透かしなど、それまでより進化した偽造防止技術が取り入れられたB号100円を発行したという経緯があります。
表面には自由民権運動の志士として名高い板垣退助の肖像、裏面には国会議事堂の威厳ある姿がデザインされているところが特徴です。なお、B号100円は発行された年代によって最初期・前期・後期の3つに分類されています。
最初期はお札の記番号のアルファベットが一桁、前期はアルファベットが二桁で中央近くに印字、後期はアルファベットが二桁で前期よりも右寄りに印字されているのが特徴です。また、最初期と前期は紙幣の色が茶褐色ですが、後期になると白っぽい色になっているため、色で識別することも可能です。
気になる相場ですが、最初期のものは高値が付きやすく、前期や後期は数百円~であるのに対し、数千円~の高値で取引されています。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

歴代百円札の種類と価値【種類別一覧】

先ほどご紹介したA号券・B号券以外にも、日本の歴史の中ではさまざまな種類の百円札が発行されてきました。現在ではA号券・B号券以外の百円札は失効しており、法定通貨としての使用はできませんが、歴史的な価値のある紙幣としてコレクター間で高値で取引されています。
具体的な価値は発行年や保管状態などによって異なりますが、専門業者に査定してもらった場合のおおよその相場は以下の通りです。
| 種類 | 相場 |
| 明治通宝100円 | 数千円~数万円 |
| 旧兌換銀行券100円(大黒) | 数千円前後 |
| 改造兌換銀行券100円(めがね) | 数百万円以上 |
| 甲号兌換銀行券100円(裏紫) | 数十万円~数百万円 |
| 兌換券100円(聖徳太子1次・乙号券) | 数千円~数万円 |
| 不換紙幣100円(聖徳太子2次・い号券) | 数千円~数万円 |
| 改正不換紙幣100円(聖徳太子3次・ろ号券) | 数千円~数万円 |
以下、7種類の失効した百円札についてご紹介します。
明治通宝100円
明治通宝100円は、1872年(明治5年)から1899年(明治32年)まで発行された、明治新政府による黎明期の政府紙幣です。縦型の優雅なデザインが特徴で、表面には「鳳凰と龍」の神秘的な図柄とともに、中央に「金百圓」「明治通宝」の文字が鮮やかな赤字で記されています。
裏面には伝統的な青海波やトンボ、千鳥の繊細な模様が織り込まれていますが、明治通宝100円は日本の印刷技術が未発達である頃に、ドイツの工場で製造されたという経緯があるため、全体的なデザインがやや西洋寄りになっているところも大きな特徴といえるでしょう。
明治通宝は百円札を含めて計9種発行されましたが、いずれもデザインが共通していたため、額面を変える不正や偽造が横行しました。さらに、西洋の用紙が高温多湿の日本の環境に合わず、短期間で劣化するなどのトラブルが多発したことから、1881年(明治14年)には改造紙幣に切り替わることになりました。
全体的な発行枚数が少なく、かつ日本初の円紙幣であることから、日本の貨幣史において歴史的価値の高い古紙幣として位置づけられており、市場では高値で取引される傾向にあります。
相場は数千円~数万円ですが、状態の良いものでは100万円以上の価値が付く場合もあります。
【関連記事】
明治通宝の買取価格一覧!全種類の特徴や価値、偽物の見分け方等
旧兌換銀行券100円(大黒)
旧兌換銀行券100円は、1885年(明治18年)から1939年(昭和14年)まで発行された紙幣です。表面に縁起が良い七福神の一人「大黒天」の姿が描かれていることが最大の特徴で、「大黒100円」とも呼ばれています。
明治通宝で不正や偽造が横行したことを受け、大黒100円には偽造防止のための青インクが用いられているところも特徴の一つです。ただし、鉛白が使われており、硫化水素と化学反応を起こすと黒色に変色することから、偽造は容易になってしまいました。
デザインは経済の安定と紙幣の信頼向上を目的として発行された紙幣ということもあり、当時としては最先端の技術が採用されていて、特に大黒天の描写は非常に緻密で繊細です。
1939年(昭和14年)に正式に通用停止となり、現在では法定通貨としては使用できませんが、大黒天の福をもたらすイメージや独特の風合いを持つデザインから、今でも根強い人気を誇っています。
また、同じ大黒札である1円、5円、10円に比べると、100円は主に銀行間での取引に用いられる高額紙幣ということで、発行枚数がかなり少なめです。そのため、現存している枚数も少なく、取引事例も見当たらないというのが実状です。
もし現物が見つかったとしたら、数百万円以上の価値を期待できるでしょう。
【関連記事】
日本銀行兌換銀券(旧兌換銀行券)の買取相場や種類を解説!高額査定のポイントも
改造兌換銀行券100円(めがね)
改造兌換銀行券100円は、1891年(明治24年)から1939年(昭和14年)まで発行された紙幣です。「めがね100円」とも呼ばれ、この愛称は中央に配置された藤原鎌足の肖像部分を囲む2つの楕円形デザインが、眼鏡のように見えることに由来しています。
大型サイズ(縦130mm × 横210mm)で迫力があり、記番号が赤色で印刷されているのが特徴的です。
めがね100円は前述した大黒100円の改訂版として導入されたものですが、その背景には偽造の横行や耐久性の問題があります。変色による偽造が横行したことは前項で説明しましたが、紙幣の強度を高めるために用いられたコンニャク粉の影響により、ネズミや虫に紙幣を食べられるというトラブルが多発したのです。
このような問題を克服するために発行されためがね100円は偽造防止インクの品質改良や紙質の向上など、セキュリティ技術が大きく進歩した紙幣でもありました。
1891年(明治24年)から50年近くにわたって発行された息の長い紙幣ですが、残存枚数は極めて少なく、数十年前の時点での未回収は93枚程度しかないといわれています。現代はさらに枚数が少なくなっていると想定すると、非常に希少価値の高い紙幣であり、保管状態によっては数百万円以上の価値が付く可能性もあるとされています。
【関連記事】
改造兌換銀行券の買取|価値や種類、通称名など解説
甲号兌換銀行券100円(裏紫)
甲号兌換銀行券100円は、1900年(明治33年)から1939年(昭和14年)まで発行された金兌換紙幣です。表面の右側には藤原鎌足の肖像、左側には奈良の歴史ある談山神社の風景が描かれています。
一方、裏面には美しい紫色のインクを用いて日本銀行本店の建物が印刷されていたことから「裏紫100円」という親しみある愛称で呼ばれるようになりました。また、発行の途中で記番号の表記が伝統的な漢数字から近代的なアラビア数字へと変更された点も特徴です。
裏紫100円は、通し番号がアラビア数字に変更される前と後で前期と後期の2つに区分されており、前期は変体仮名の組番号と漢数字(万葉記号)、後期は組番号とアラビア数字の組み合わせが採用されています。万葉記号かアラビア記号かは、談山神社の風景の下部を見れば分かるので、比較的見分けやすいでしょう。
気になる価値については、一般的に後期よりも前期の方が査定額が高くなりやすいといわれており、保管状態が良ければ百万円以上の高値が付く可能性があります。
一方、後期は前期ほどの値は付きにくいですが、美品や未使用品であれば数十万円の値が付くこともあるので、裏紫100円を見つけたら専門店に持ち込んで鑑定を依頼しましょう。
【関連記事】
甲号・乙号兌換銀行券は買取可能?種類別の価値やその他兌換紙幣
兌換券100円(聖徳太子1次・乙号券)
兌換券100円は、1930年(昭和5年)から1946年(昭和21年)にかけて発行された紙幣です。表面には日本の歴史上の偉人である聖徳太子の肖像(右側)と法隆寺夢殿の姿(左側)が描かれ、裏面には法隆寺西院伽藍の全景が表現されています。
表面に聖徳太子が描かれた100円紙幣は全部で4種類あるため、区別するために別名が付けられており、初めて聖徳太子が描かれたこの紙幣は聖徳太子1次100円あるいは乙号券とも呼ばれています。
他のパターンの紙幣に比べると、裏面の中央が茶色で、その周辺が淡い緑色になっているところが特徴です。この紙幣は関東大震災後の経済混乱とインフレへ対応するために発行され、専用の印刷機によって多色凸版の地模様印刷が施されました。そのぶん偽造防止の効果も高く、偽札の横行を防ごうという当時の工夫がうかがえます。
1946年(昭和21年)の新円切替により失効し、現在では使用できませんが、聖徳太子をモチーフにした「太子券」シリーズの記念すべき第1弾でもあることから、価値の高い古紙幣として扱われています。
そのため、専門店で査定してもらえば数千円~数万円の値が付くことも期待できるでしょう。さらに証紙付きならプラス査定になり、より高値での取引が期待できます。
聖徳太子1次100円は発行枚数も多かったため、ご自宅やご実家を探せばもしかしたら状態の良い兌換券100円が見つかるかもしれません。
不換紙幣100円(聖徳太子2次・い号券)
不換紙幣100円は、1944年(昭和19年)から1946年(昭和21年)頃にかけて、戦時体制下の逼迫した状況の中で発行された紙幣です。前述した聖徳太子1次100円の次に発行された100円紙幣であることから、「聖徳太子2次100円」や「い号券」の呼び名でも知られています。
基本的なデザイン構成は先行する乙号券を踏襲しており、聖徳太子の肖像と法隆寺夢殿の図柄が引き続き採用されましたが、1次100円に比べると聖徳太子の表情や全体の彩色などに違いがあり、2次100円の裏面は全体的に赤みの強い色合いになっています。また、表記が「日本銀行兌換券」から「日本銀行券」に変化しているところも1次100円との大きな違いです。
前述した1次100円よりも発行枚数がさらに多かったため、希少性の面から買取相場はやや低くなりますが、それでも数千円~数万円の値が付く可能性があります。証紙付きであれば、さらに価値がアップし、より高額査定を提示されることもあるでしょう。
また、残存数が多いということは、それだけ現代で発見されやすいということにもつながるため、他の希少な紙幣に比べれば、身近なところで見つかる確率も高いかもしれません。
改正不換紙幣100円(聖徳太子3次・ろ号券)
改正不換紙幣100円は、1945年(昭和20年)から1946年(昭和21年)と、わずか1年ほどの短い期間に発行された緊急対応型の紙幣です。聖徳太子が描かれた3番目の100円紙幣であることから、「聖徳太子3次100円」や「ろ号券」とも呼ばれています。
発行年である1945年(昭和20年)は戦後の混乱期に当たり、資源の枯渇と経済の混迷に悩まされた時期でもありました。その影響は紙幣のデザインや作りにも及んでおり、聖徳太子シリーズ第3弾でありながら、聖徳太子の描写や全体の色彩はかなり簡素化されています。
また、それまでの紙幣に施されていた偽造防止策も極力削減されているところも時代を象徴しているといえるでしょう。
3次100円が発行された翌年、政府は金融緊急措置および日本銀行兼預入令を交付し、5円以上の日本銀行券を強制的に預入させるとともに、生活費や事業費などに限って新銀券による払い出しを認めるという新円切り替えを実施しました。
これにより、3次100円はわずか1年未満で発行が中止され、同じ聖徳太子シリーズの中では特に残存数の少ない紙幣となっています。そのため、並品でも数千円、美品や未使用品なら数万円の高値が付くこともあるでしょう。
昔の百円札を交換・買取に出す方法

A号券やB号券のように法的効力を現在も保持している紙幣であれば、理論上は店舗での支払いや金融機関への預け入れが認められます。
紙幣の引換は、日本銀行の本店と全ての支店において受け付けていますが、引換に当たっては法令等に定める基準に照らし合わせ、引換可能か否かを判断する手続きが必要になるため、ある程度の時間がかかります。
特に事前に予約を行っていない場合は当日中に引換できない可能性があるため、引換を申し込む際は本支店で事前に予約を取るのがおすすめです。ただし、百円札はそのまま使用したり、引き換えたりした場合、額面通り(100円)の価値しかありません。
一方、専門店に買い取ってもらえば、その歴史的・文化的価値が評価され、額面を大きく上回る高値が付く可能性があります。特に保管状態が良好なものや、特徴的なシリアルナンバーが記されたものなどは、高額な査定結果になるケースもあるでしょう。
以上の点から、百円札はそのまま決済に使ったり、日本銀行の本支店で引き換えたりせず、古紙幣に詳しい買取業者に相談し、適正な査定額を確認するのがおすすめです。
百円札は額面以上の価値が期待できる専門店に持ち込もう
百円札の中には、A号券やB号券など現在でも決済に使用できるものがありますが、普通に使うと額面以上の価値はありません。
一方、すでに製造が中止された百円札は希少性が高いことから、コレクター間で高く取引されています。専門店に査定を依頼すれば、額面の数倍以上の高値で買い取ってもらえる可能性が高いので、手元に百円札がある場合は決済や引換に使わず、専門店に鑑定を依頼するのがおすすめです。
買取専門店の「福ちゃん」では、定期的に社内研修を受けているプロの査定士が、古紙幣が持つ歴史的価値と市場価値を適正に評価し、丁寧に査定いたします。
買取方法は店舗持ち込みの他、出張買取や宅配買取にも対応していますので、「忙しくてなかなか店舗に行けない」という方もご利用可能です。
もちろん、査定手数料や出張料などの手数料は無料です。お手元にある百円札の価値を知りたい方や、高値での買い取りを希望されている方は、ぜひ福ちゃんまでお気軽にご相談ください。