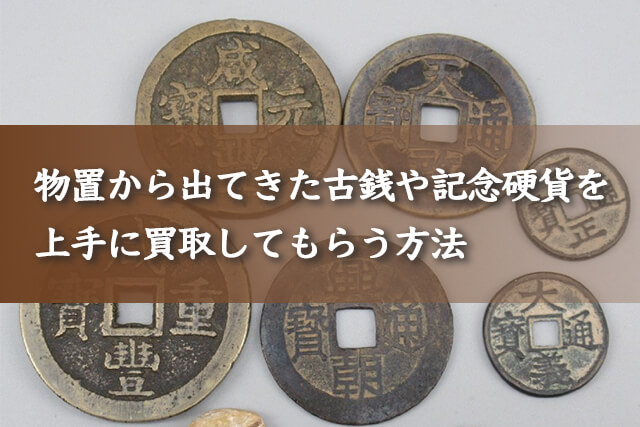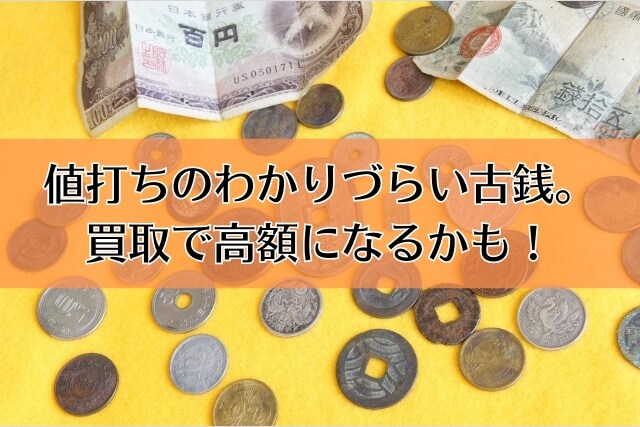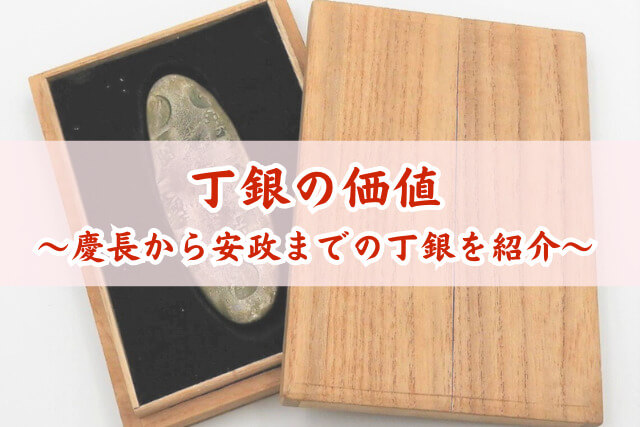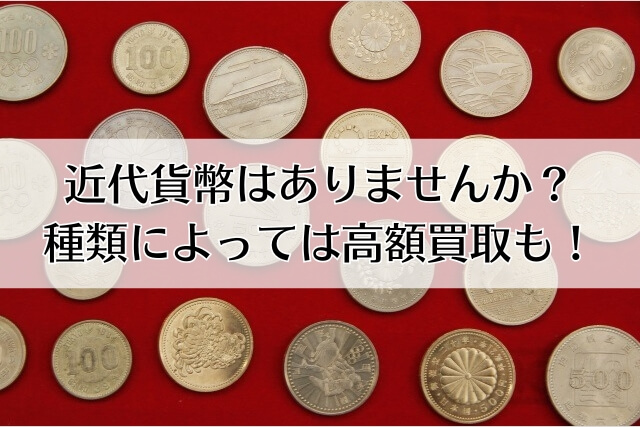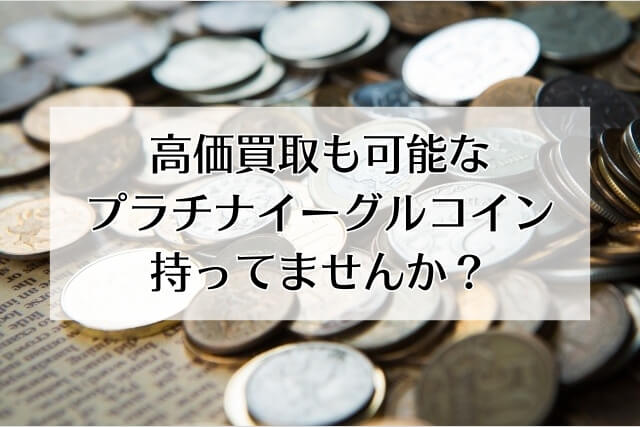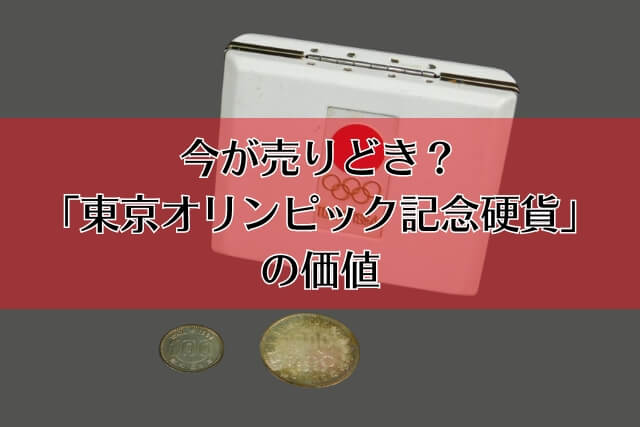- 古銭/記念硬貨
- 2025.11.14
ギザ10の価値は?価値のある10円玉の年号と高く売る方法まとめ

縁がギザギザになっている10円玉、略してギザ10は、時折見かけるなじみのある硬貨です。「子どもの頃に集めていた」という方もいるのではないでしょうか。実はギザ10にもさまざまな種類があり、中には高値で取引されているものもあります。
この記事では、ギザ10を含む価値のある10円玉の年号を相場目安付きでご紹介するとともに、ギザ10や10円玉の価値が上がる理由、ギザ10が製造されなくなった理由、レアな10円玉の保管方法などについてまとめました。
ギザ10や価値ある10円玉を高値で売る方法も解説しているので、ギザ10が手元にある方はぜひご覧ください。
【記事のポイント】
- ✅昭和32・33年銘は数万円の価値も?!
- ✅昭和61年後期や影打ちエラー・ヘゲエラーなどのエラー硬貨も高価値
- ✅ギザ10を含む価値のある10円玉の買取なら買取実績が豊富な福ちゃんにお任せください!
ギザ10を含む価値のある10円玉の年号はいつ?【相場目安付き】

ギザ10は1951年(昭和26年)から1958年(昭和33年)にかけて鋳造された10円玉ですが、その価値は発行年によって異なります。以下では発行年ごとのギザ10の相場目安をまとめました。
| 発行年 | 相場 |
| 1951年(昭和26年) | 10円~数千円程度 |
| 1952年(昭和27年) | 10円~15円前後 |
| 1953年(昭和28年) | 10円~100円程度 |
| 1954年(昭和29年) | 10円~300円程度 |
| 1955年(昭和30年) | 10円~700円程度 |
| 1957年(昭和32年) | 10円~数万円程度 |
| 1958年(昭和33年) | 10円~数万円程度 |
※昭和31年は発行枚数が0枚だったため、除外してあります。
※福ちゃんでは状況により査定をお断りする場合もございます。
以下では、特に収集家やコイン愛好家の間で注目を集めている1951年(昭和26年)、1957年(昭和32年)・1958年(昭和33年)に発行されたギザ10について説明します。
また、ギザ10とは別に価値ある10円玉として知られている昭和61年後期発行の10円玉についても解説します。
昭和26年発行のギザ10の特徴と価値
1951年(昭和26年)に製造された10円玉は、新デザインの硬貨として初めて世に送り出された年という特別な歴史的価値を持っています。この年から、現在も使われている平等院鳳凰堂のデザインが採用されました。
なお、ギザ10の正式名称は十円青銅貨幣で、名前の通り、銅95%、亜鉛4~3%、錫1~2%の構成となっています。直径は23.5mm、量目は4.5gです。
発行枚数は1957年(昭和32年)、1958年(昭和33年)に次いで少なく、かつ記念すべきギザ10発行の初年度でもあることから、長年にわたって収集家からの需要が高く、特に状態の良いコインは数百円~数千円程度と高額で取引されることもあります。中でも未使用品はコレクターからの評価が高いため、高値が付きやすいでしょう。
さらに、平等院鳳凰堂の屋根の上にいる鳳凰(鳥)の形にも注意が必要です。小さいので分かりにくいですが、鳳凰の尾が上を向いているギザ10は、同じ昭和26年銘の十円玉の中でも特に希少性が高く、査定でプラス評価になる可能性があります。
ただし、微妙なデザインの違いは判定しにくいため、昭和26年銘のギザ10をお持ちなら専門店で鑑定してもらうと良いでしょう。
昭和32・33年発行のギザ10は希少価値が高い
1957年(昭和32)・1958年(昭和33年)は、ギザ10の製造が中止される最後の2年間に当たる年です。
1955年(昭和30年)までは毎年1億枚以上発行されていたギザ10ですが、1枚も発行されなかった1956年(昭和31年)を挟んだ1957年(昭和32年)は5,000万枚、1958年(昭和33年)は前年の半分に当たる2,500万枚しか発行されませんでした。
元々の発行枚数が少ないことに加え、発行からかなりの年月を経っていることから、現存枚数は他の発行年より極めて少ないと考えられています。そのため、この時期に発行されたギザ十は独特の希少価値を持ち、使用感が少ない未使用品や美品は、熱心なコレクターから高額で取引されています。
具体的な価値は保管状態によって異なりますが、未使用品や美品(溝がはっきり残ったものや摩耗が少ないもの)であれば数千円~数万円の高額査定が付くこともあるでしょう。
昭和61年後期10円玉のプレミア価値とギザ10との違い
昭和61年銘の10円玉は発行時期によって前期と後期の2つに区分されますが、このうち高値が付くのは後期の方です。なぜ発行年が同じなのに後期の方に価値が付くのかというと、昭和61年後期はエラー銭の一種だからです。
エラー銭とは、何らかのトラブルによって、本来とは異なる不良品になってしまった硬貨のことです。昭和61年後期の場合、その翌年の1987年(昭和62年)に採用されるはずだったデザインが誤って昭和61年銘の10円玉に刻印されてしまったという特殊な経緯があります。
前期とのデザインの違いは平等院鳳凰堂にあり、以下3点の見た目が異なります。
- 屋根の先端が鋭い(前期は緩やか)
- 屋根に切れ目がない(前期は切れ目がある)
- 階段の縦線が横線と結合している(前期は縦線と横線が離れている)
なお、この時代には既にギザ10の製造は中止されているため、昭和61年後期10円玉とギザ10の違いは縁のギザの有無で容易に確認可能です。
昭和61年後期10円玉は、美品であれば数万円の高値で取引されるため、昭和61年銘の10円玉をお持ちの方は専門店に査定を依頼してみましょう。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

ギザ10や10円玉の価値が上がる理由

なぜ一部の10円玉がレア硬貨として高値で取引されるのでしょうか。その理由は、「発行枚数の少なさ」と「製造エラーの存在」にあるといわれています。
この2点に共通しているのは希少価値の高さです。古銭の価値は希少性の高さに比例しており、市場に出回っていないものほどコレクターからの需要が高く、高値が付く傾向にあります。
ここではギザ10を含む10円玉の価値が上がる2つの理由について深掘りしていきましょう。
発行枚数が少なくてレアなため
硬貨の価値が高騰するもっとも一般的な理由は、その発行枚数の少なさにあります。市場に出回る数が限られていることで希少性が高まり、コレクターや投資家からの関心を集めるようになるのです。
特に、特定の年号や限定タイプのコインは、流通量が極端に少ないためプレミア価格も付きやすい傾向にあります。10円玉でいえば、他の発行年よりも枚数が少ない昭和32年・33年銘のものにプレミア価値が付いています。
これは、経済の基本原理である需要と供給のバランスが価値を大きく左右する典型的な例です。
また、現在製造が中止されている古銭は、発行からある程度の年数が経過しているため、適切な方法で保管されていない場合、汚れや緑青と呼ばれる変色が起こっています。
そのため、製造当時の状態を維持したまま残存している古銭は少なく、美品に絞るとさらに希少性が高くなります。その結果、同じ年号の硬貨でも状態が良いものほど高い査定額に期待できるというわけです。
このように、歴史的価値と物理的な希少性が組み合わさることで、1枚の小さな硬貨が大きな価値を持つことになります。なお、コインのレア度は発行年だけに左右されるものではなく、後述する製造エラーも希少価値を上げる要因となります。
「この10円玉は発行枚数が多い年のものだから、あまり価値はないだろう」と思っていたら、実はエラーコインで額面を遥かに上回る価値があった、というケースも考えられるので、発行枚数が多い年のギザ10でも諦めずに査定を依頼することがおすすめです。
製造エラーがあるため
製造エラーとは、貨幣を製造する過程で何らかのエラーが生じ、不良品になってしまうことです。このような通常の製造工程では起こりえないミスによって生まれた「エラーコイン」は、極めて限られた数しか存在しないため、非常に高値で取引されることがあります。
エラーコインの種類は複数ありますが、10円玉の場合は刻印の位置がずれる刻印ずれや、表裏の角度が通常と異なっている角度ずれ、硬貨の両面が同じ模様のように見える影打ちエラー、コインの縁部分にバリ(不要な突起)やギザギザが残ってしまうヘゲエラーなどがあります。
このようなエラーは通常、検品の段階で弾かれるため、市場に流通することはありませんが、まれに検品をすり抜けるものもあります。検品洩れもめったに起こることはないため、エラーコインの流通量は非常に少なく、レア度が高くなる要因となっています。
また、ちょっとした不具合のある10円玉は見た目にもユニークなので、コレクターの心を強く惹きつける魅力的な要素となっているのでしょう。
なお、エラーコインは、年号自体の希少性にかかわらず高値が付くことが多く、専門のオークションなどでも特に人気を集めています。中には数十万円以上という驚くべき高額で落札されることも珍しくなく、「欠点」が「価値」に変わる面白い例といえるでしょう。
ただし、エラーコインはエラーの度合いが微小の場合、一見しただけでは判断が付かない場合があります。影打ちエラーやヘゲエラーは比較的分かりやすいですが、刻印ずれや角度ずれの程度が少ない場合、エラーコインかどうか判定するのは困難です。
ぱっと見た感じは普通のコインだけれど、よく見たらエラーコインだったという可能性は十分あるので、専門的な知識や観察眼に長けた査定士に鑑定してもらうことをおすすめします。
プルーフ加工の10円玉も価値が高い

プルーフ加工とは、鏡のように美しく輝く特別な製造工程で仕上げられた硬貨のことです。初めて製造されたのは1987年(昭和62年)のことで、コレクションのための貨幣として作られたのが始まりです。
通常の流通用10円玉との違いは、製造工程にあります。プルーフ加工では専用の極印と呼ばれる特別に磨き上げられた金型を使用し、鏡面研磨を施した専用の円形で圧印する仕組みになっています。
圧印の回数も、通常の貨幣では1工程につき1回ですが、プルーフ加工では鏡面や刷り込みをより美しく転写するため、複数回以上の連続圧印するところが大きな違いです。
こうして出来上がったプルーフコインは、表面に細かな傷や曇りがなく、デザインの細部までくっきりと深みのある刻印に仕上がります。
見た目の美しさもさることながら、これらは一般の流通用としてではなく、記念硬貨セットなど限定的な形でしか入手できないことが多いため、市場に出回る数も極めて限られています。
そのため、コレクターズアイテムとしての需要が非常に高く、特に美しい状態を保っているコインはプレミア価格が付くことも珍しくありません。
プルーフ加工が施された貨幣セットはこれまで複数回発行されていますが、特にプルーフコインが初めて流通された1987年(昭和62年)プルーフ貨幣セットや、東京オリンピックの開催を記念して発行された東京2020オリンピック競技大会記念プルーフ貨幣セット、明仁上皇の平成天皇即位を記念して発行された天皇陛下御即位記念プルーフ貨幣セットなどは、特に希少価値が高いセットとして高値で取引されています。
上記の他にもさまざまなセットが発行されてきた歴史があるため、ご自宅やご実家でプルーフ貨幣セットが見つかったら、専門店に査定を依頼して価値を確かめてもらうと良いでしょう。
ギザ10が製造されなくなった理由

ギザ10が製造されなくなった理由は、1957年(昭和32年)に発行された100円銀貨によって最高額面が変わったことです。
そもそもギザ10が発行されたのは、10円が当時の硬貨の最高額面であることを示すためだったといわれています。また、10円の原材料である銅そのものの価値が高騰したため、10円玉の外縁を削って転用するなどの不正を防止しようという考えもあったようです。
しかし、100円銀貨の誕生によって10円玉は最高額面ではなくなったため、象徴としてのギザ10を作る理由がなくなりました。また、100円玉にも縁にギザギザが付いていることから、触れただけで10円玉と100円玉を識別するのが難しくなったというのも理由の一つです。
折しも、硬貨製造技術自体の向上により、ギザギザ加工がなくても識別しやすくなったことから、ギザ10の必要性が失われ、1958年(昭和33年)に各界有識者によって設置された「臨時補助貨幣懇談会」にて貨幣形式の統一が図られた際、正式にギザ10の廃止が決まりました。
ギザ10を含むレアな10円玉の保管方法

ここまで説明してきた通り、ギザ10を含むレアな10円玉は、保管状態が良いものほど価値が上がる傾向にあります。
逆にいうと、保管状態の悪いコインは美品よりもかなり価値が下がるので、レアな10円玉は適切な方法で保管することが大切です。
ここでは、コインの価値を守るための正しい保管方法をご紹介します。
素手で直接触らない
人の皮膚には、汗や皮脂、雑菌などさまざまな物質が付着しています。10円玉の主原料である銅は、空気中の酸素や湿気などと反応すると緑青と呼ばれる変色を起こす性質を持っているため、汗や皮脂が付着した手で直接触れるとコインが劣化する原因となります。
特に、鏡面仕上げのプルーフコインやエラーコインなど表面の状態が重視される硬貨は、指紋や皮脂の付着によって査定額も大きく下がってしまうことがあるため、素手で直接触るのは避けるべきでしょう。
どうしても10円玉に触れなければならないときは、綿の手袋をはめることで汗や皮脂の付着を防げます。絹製の手袋が手元にない場合は、清潔な布かティッシュでコインを挟むようにして取り扱うようにしましょう。
うっかり素手で触って指紋や油分などが付いてしまったときは、柔らかい布でさっとから拭きすればOKです。なお、10円玉をあらかじめ「コインホルダー」にセットしておけば、次回以降はコインに直接触らずに出し入れできるようになります。
直射日光と湿気を避ける
コインの天敵は光・湿気・空気の3つといわれています。直射日光に長時間さらされると、表面の変色や退色が進んでしまう恐れがありますし、湿度の高い場所に保管していると、硬貨がさびたり酸化したりする原因になります。
できれば密閉性の高いケースを使用したり、シリカゲルなどの防湿剤を一緒に入れたりと工夫をし、室内でも直射日光が当たらない場所を選んで保管しましょう。
なお、棚や引き出しに保管する場合は、温度や湿度が安定している場所を選ぶことが大切です。棚や引き出しに入れておけば、コインそのものへの直射日光は防げますが、棚自体が日当たりの良い場所に置かれていると、内部に熱がこもって高温多湿の原因になります。
また、風通しの悪い場所も湿度が上がる原因になるので、物置や押し入れ、クローゼットなど通気性の悪い場所に保管する場合はあらかじめ注意が必要です。
特に梅雨時期は屋内全体に湿気がこもりやすくなるので、定期的にコインの保管場所をチェックし、湿度が高くなっていないかどうか確認することをおすすめします。
もし湿度が高いと感じたら、乾燥剤を増やしたり、換気をしたりして湿気を逃がすようにしましょう。
洗浄や研磨はしない
保管状態が悪いと、10円玉が汚れたり、変色したりしてしまいますが、自分で洗浄や研磨を行うのはNGです。硬貨に付いた汚れを落とすために市販の洗剤や研磨剤でこすってしまうと、表面に細かな傷が付いたり、大切な刻印が薄れたりする恐れがあります。
コインは美品の方が価値があると説明しましたが、それはあくまで自然な状態で残存している場合の話です。コレクター市場では、硬貨本来の状態や風合いが損なわれると、査定額が大幅に下がることも珍しくありません。汚れが気になる場合でも、自己判断で洗浄を行うのではなく、コイン専門店などで専門家のアドバイスを受けるか、極力摩擦を与えないような優しい洗浄方法を検討しましょう。
なお、一般的な中古品では汚れやサビなどが浮いていると買い取りを拒否される場合が多いですが、こと古銭に限っては汚れや変色があっても買い取ってもらえる可能性が高いです。そもそも古銭は発行からかなり年月が経過しているものが多く、汚れや変色が発生しているものも珍しくないためです。
柔らかい布でさっと拭いただけで落とせるような汚れであれば、ある程度お手入れしておいてもよいですが、洗剤や研磨剤などを使わなければ落とせないような汚れには手を付けず、そのまま査定に出しましょう。
ギザ10や価値のある10円玉はどこで売れる?

ギザ10や価値のある10円玉を買い取ってもらう方法は複数ありますが、それぞれメリットや特徴に違いがあります。
売る方法を誤ると、本来の価値よりも大幅に低い価格で買い取られる可能性もあるので、売却先は慎重に選びましょう。
ここでは主な売却方法と、それぞれのメリットや特徴、売るときの注意点をまとめました。
ネットオークションで販売
ネットオークションは、自身が希望する価格を設定して出品でき、全国各地のコレクターや購入希望者に向けてアピールできるという大きな魅力があります。
また、オークションは価格の上限が決められていないため、入札者同士が競り合った場合、価格がどんどん上がっていくところがオークション形式ならではの魅力です。また、オークションは個人間のやり取りになるため、業者を間に挟まないぶん、余計なマージンを取られないというのもメリットの一つでしょう。
一方で、落札者とのやり取りや発送手続きなど、意外に手間と時間がかかる点や、必ずしも希望通りの高値で売れる保証はないといった不確実性もあります。また、オークションでは出品時に最低落札価格を決められますが、相場観を持っていないと本来の価値よりも安い価格で落札されるケースもあるため注意が必要です。
さらに、オークションは個人間の取引故に、トラブルのリスクも尽きません。特にネットオークションの場合、入札者は現物を直接見ないまま取引することになるため、現物が手元に届いてから「思ったものと違う」「偽物ではないか」とクレームを付けられる可能性もゼロではありません。
このようなトラブルを避けたいのなら、ネットオークション以外の方法を検討した方が良いでしょう。
買取専門店への売却
買取専門店に売却するメリットは、コインについての専門知識を持った鑑定士が状態や希少性を正確に評価してくれるところです。
前述の通り、ギザ10を含む価値あるコインは、種類や発行年、保管状態、希少性、エラーの有無などによって価値が大きく左右されます。これらの条件を加味して正確な価値を見極めるには、古銭に関する専門的な知識や優れた観察眼が欠かせません。
硬貨についての深い専門知識を持つお店や、長年の実績があり信頼できる店舗を選べば、古銭の価値を適正に判断してくれるため、より安心した取引が進められるでしょう。
なお、近年では店頭での買い取りだけでなく、自宅に居ながら利用できる宅配買取や、自宅まで専門家が訪問する出張買取のサービスを行っている業者も増えています。そのため、遠方に住んでいる方や、まとまった量のコインを売りたい方も非常に便利です。
ただし、古銭買取専門店といっても、査定士の技量や実績は店舗によってまちまちです。どの業者を選べば良いか迷ったときは、以下のポイントを基準に信頼できる専門店を絞り込んでいきましょう。
- 古銭の買取実績は豊富か
- 査定・買取にかかる手数料は無料か
- 買取方法の種類が多彩か
- 売りたい古銭の買い取りに対応しているか
- 利用者の口コミ・評判は良いか
フリマアプリでは売却できない
フリマアプリは、個人間で気軽に物品を取引できる便利なプラットフォームとして人気がありますが、日本国内のサービスでは、現金や硬貨の売買は利用規約によって禁止されているケースがほとんどです。
理由は、フリマアプリで貨幣を購入することによるマネーロンダリング(資金洗浄)や、ショッピング枠を利用したクレジットカードの現金化を防ぐためです。このような行為は貸金業に該当するため、貸金業者の登録を行っていない者がこれらの行為を行った場合、貸金業法違反に抵触する恐れがあります。
そのため、フリマアプリでは現金、金券類、カード類などの出品を全面的に禁止しています。なお、ここでいう「現金」とは、現在有効な国内の銀行券・貨幣、記念貨幣などです。そのため、既に通貨としての通用ができない古銭については出品できるケースもあります。
ただし、失効している古銭は希少価値の高いものであるため、フリマアプリで個人間取引するよりも、正規の取引ルートを通じて売却する方が本来の価値に見合った高い評価を得られる可能性がありますし、思わぬトラブルも避けられるでしょう。
レアコインを高く売るなら福ちゃん!

「福ちゃん」は、長年の経験を積んだ熟練の古銭鑑定士が多数在籍しており、レア硬貨の真贋判定や状態評価を的確に行います。
査定士は査定技術の向上を目的とした定期的な社内研修を受けており、古銭の持つ本来の価値や微小なエラーをしっかり見極めることができるので、ぜひ価値のあるコインの鑑定をお任せください。
買取方法もニーズに合わせて3種類ラインナップしており、店舗での買い取りはもちろん、ご自宅に居ながら利用できる宅配買取や、専門スタッフがお客様のもとへ伺う出張買取へも対応しているため、お忙しい方や遠方にお住まいの方でも気軽にご利用いただけます。
もちろん、出張料や査定料、買取成立時の手数料などは一切無料です。査定額をそのまま受け取れるため、中間マージンなどで損をする心配はありません。さらに、査定後に納得がいかない場合のキャンセル料もかからないなど、利用者に優しいサービスが充実している点も大きな魅力の一つです。
古銭の買い取りに関するご相談やご依頼はお電話で受け付けている他、公式ホームページのお申し込みフォームやお問い合わせフォームもご利用いただけます。また、LINEで「友だち追加」すれば、より気軽に買い取りの相談をできる上、お得情報や買取方法診断も受けられるので、非常に便利です。
大切に保管してきたレアコインの価値を正当に評価した高価買取なら、ぜひ「福ちゃん」をご検討ください。
価値ある硬貨の査定は福ちゃんへ
価値のある年号の10円玉には1951年(昭和26年)の新デザイン初期発行品や、1957年(昭和32)・1958年(昭和33年)のギザ十(縁がギザギザの10円玉)、そして昭和61年後期発行の10円玉などが挙げられます。
それぞれ発行枚数の違いや、製造工程の歴史的な変遷によって希少性の高いコインが存在します。
さらに、刻印ずれや角度ずれといった製造エラーが見られるコイン、あるいは特別なプルーフ加工が施された記念硬貨なども、高額取引が期待できる重要な要素です。
これらのレア硬貨を扱う際にもっとも大切なのは、その価値を損なわないよう保管状態を良好に保ち、信頼できる正規のルートを通じて適正な査定を受けることです。
買取専門店の中でも「福ちゃん」は、豊富な知識と実績を持ち合わせているため、大切なレア硬貨も安心してお任せください。ギザ10の買取はお断りすることもありますが、その他の古銭や記念コインについては多数の買取実績がございます。
まずは無料査定サービスにて、お手元にある古いコインや記念硬貨の価値をチェックしてみてはいかがでしょうか。