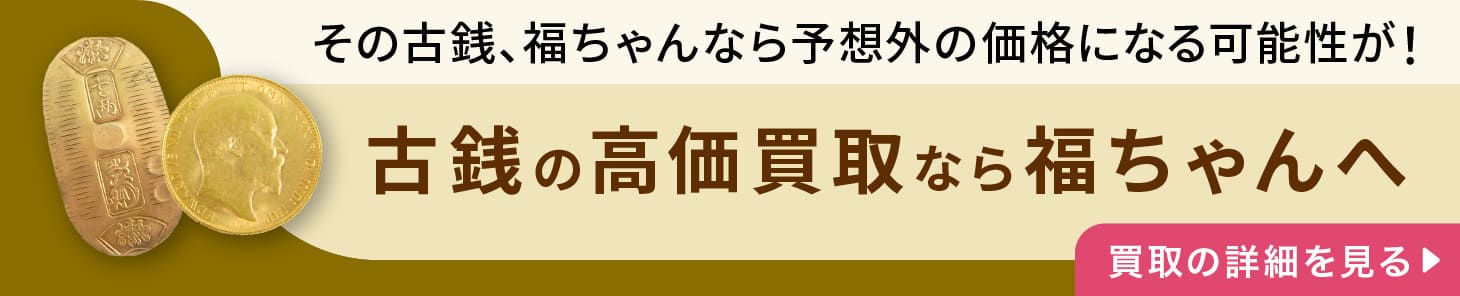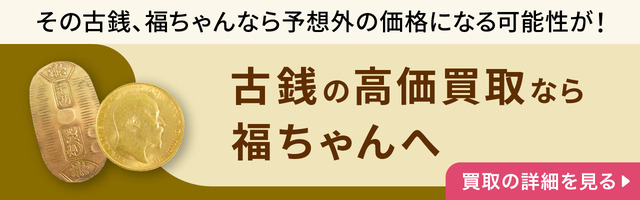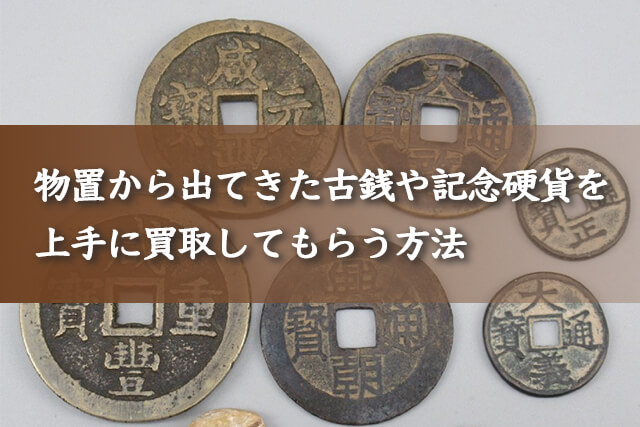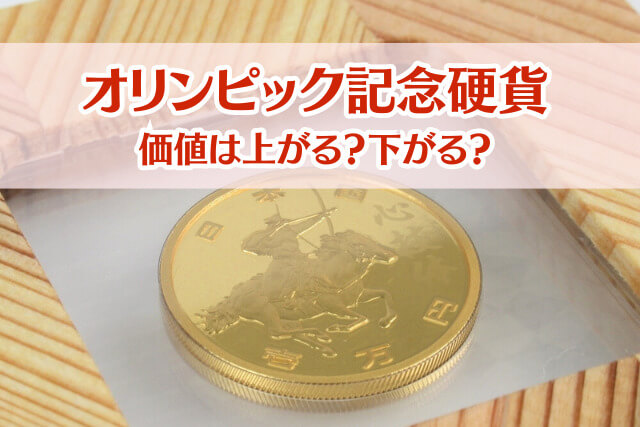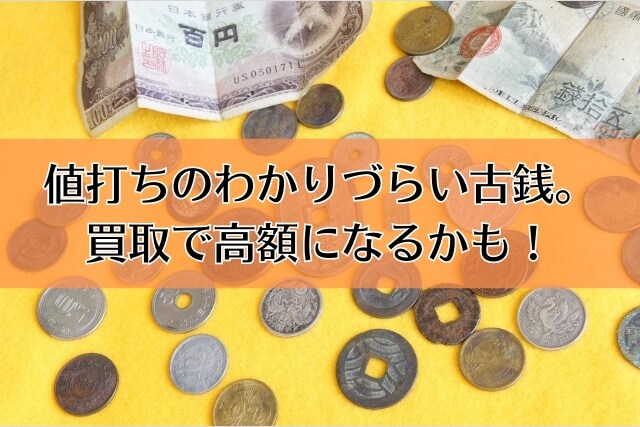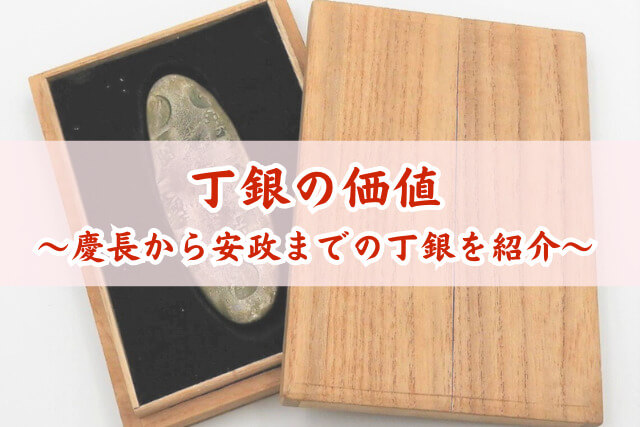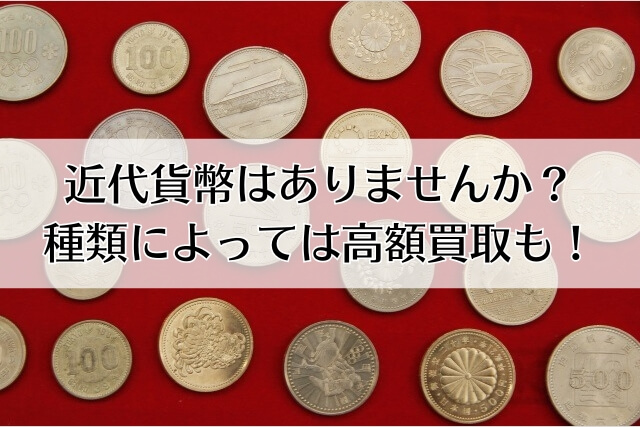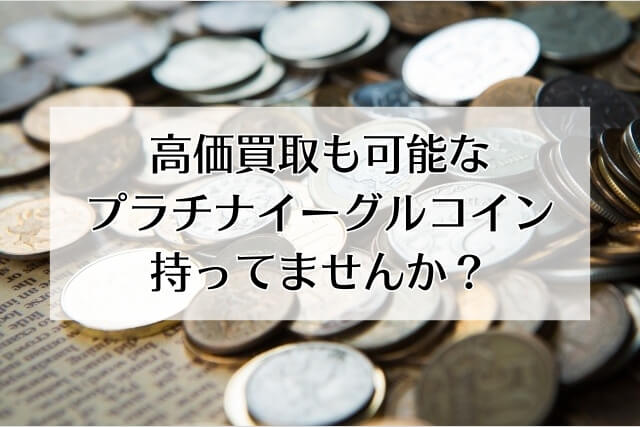- 古銭/記念硬貨
- 2025.08.02
寛永通宝の買取価格!種類別価値やレアものの見分け方、高額査定のポイントも
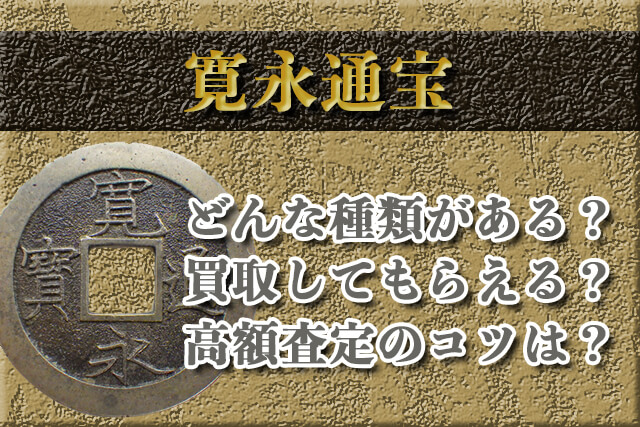
「寛永通宝って書いてある古銭を持っているけど使い道ある?」
「寛永通宝が家にあるけどこれ何?」
など、寛永通宝を持て余している方のために、寛永通宝についてご紹介します。
寛永通宝といえば、香川県観音寺市にある寛永通宝を模した巨大な砂絵が有名です。古銭としてはどのような価値があるのでしょうか。
本記事では、寛永通宝の価値や種類ごとの見分け方を、初心者にもわかりやすく解説いたします。ご自身の寛永通宝がどの種類に当てはまるのか、ぜひ確かめながらお読みください。
寛永通宝とは?いつ使われたお金?簡単に説明
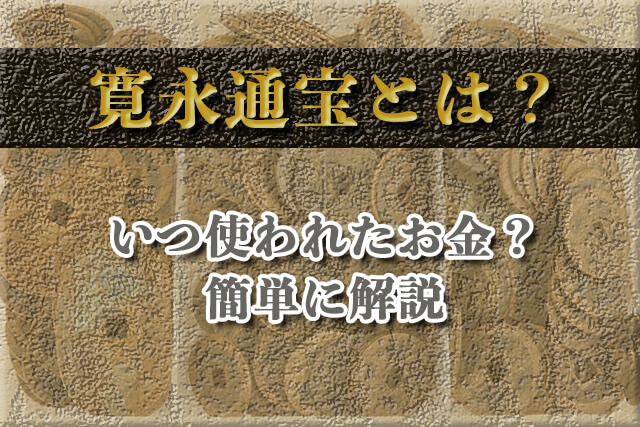
「寛永通宝」は江戸時代に流通した古銭で、真ん中に穴が空いた穴銭の一種です。
具体的には1626年(寛永3年)から江戸時代末期にかけて使用されていました。
まずは、寛永通宝がどのようなお金だったのか、基本的な情報から見ていきましょう
寛永通宝の始まり
寛永通宝は、1626年に水戸の「佐藤新助」によって寛永通宝「二水永」が作られたのが始まりとされています。
しかし、徳川幕府によって寛永通宝「芝銭」や「浅草銭」などの種類が生まれながら全国に広まったとされるのは、1636年です。
寛永通宝の始まりに関して「1626年から」「1636年から」と表記が異なる場合があるのは、このような経緯が理由と考えられています 。
なお、造幣局内の年表には、公鋳銭として広まった「1636年」が寛永通宝の始まりと記載されています。
1626年に私鋳銭として始まり、1636年に公鋳銭として広まっていった背景を楽しめるのも寛永通宝の魅力のひとつです。
当時の日本は、金貨(小判など)・銀貨(丁銀など)・銭貨(寛永通宝)がそれぞれの役割を担う「三貨制度」が確立されていました。
高額取引には金貨や銀貨、そして庶民の日常的な買い物には寛永通宝が使われ、江戸時代の経済を根底から支える重要な役割を果たしたのです。
驚くべきことに、法律上は昭和28年(1953年)まで通貨として有効でした。
古寛永と新寛永に分類される
寛永通宝には、大きく分けて「古寛永」と「新寛永」に分けられます。
1659年までに作られたものが「古寛永」で、その後鋳造されなかった期間を経て1668年以降に作られたものが「新寛永」です。
古寛永(~1659年)の特徴と代表的種類
古寛永は、江戸幕府が寛永通宝の鋳造を始めた1636年から、一度鋳造が中断される1659年ごろまでに作られたものを指します。
この時期は、江戸だけでなく水戸や仙台、松本など全国各地の銭座で鋳造されていたため、書体や品質にばらつきがあるのが大きな特徴です。
職人の手作業による風合いが強く、1枚1枚に個性が見られます。中には、寛永通宝の試作品ともされる「二水泳」のように、現存数が極めて少なく、非常に高い価値を持つレアコインも存在するのです。
そのほか、江戸の浅草や芝で作られた「浅草銭」「芝銭」なども古寛永に含まれます。
新寛永(1668年~)の誕生背景と代表的種類
新寛永は、鋳造が再開された1668年から明治初期にかけて作られたものを指します。
この時代になると、江戸の亀戸などに幕府直轄の巨大な銭座が設けられ、より規格化された銭貨が大量生産されるようになりました。
新寛永は古寛永に比べて品質が均一で、銭の裏に鋳造地を示す文字(文・仙・足など)や、価値を示す波模様が刻まれているのが特徴です。
これを「古背文字銭」や「波銭」と呼びます。流通量は非常に多いですが、書体や背文字の種類によっては高値で取引されるものもあります。
査定・出張費・手数料はすべて無料。

寛永通宝の買取価格を種類別に紹介
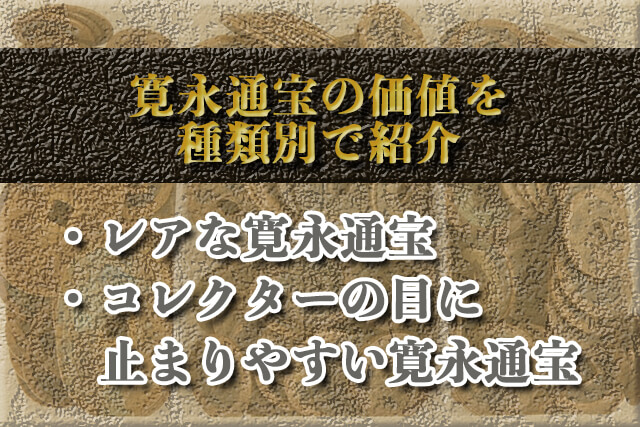
| 古寛永 | 二水永(にすいえい) |
| 浅草銭(あさくさせん) | |
| 芝銭(しばせん) | |
| 水戸銭(みとせん) | |
| 松本銭(まつもとせん) | |
| 新寛永 | 島屋文(しまやぶん) |
| 正字背文(せいじはいぶん) | |
| 退点文(たいてんぶん) | |
| 正字入文(せいじいりぶん) | |
| 日光御用銭(にっこうごようせん) | |
| 下野国足尾銭(しもつけのくにあしおせん) | |
| 背広佐(せびろさ) | |
| 耳白銭(みみじろせん) | |
| 石ノ巻銭(いしのまきせん) | |
| 小梅銭(こうめせん) |
上記のように寛永通宝には実に多くの種類があります。
中にはコレクターにも注目されている有名な種類もあるため、買取価格を見てみましょう。
二水永(にすいえい)
二水永は、寛永通宝を最初に製造した佐藤新助が江戸幕府と水戸藩の許可を得て1626年に鋳造した寛永通宝です。
初代寛永通宝として、古寛永の中でも歴史的価値が高いものとされています。
漢字の「二」と「水」を組み合わせたような「永」の字が刻印されているのが特徴です。
寛永通宝の中ではレアな種類に分別され、状態が良ければ1枚数万円の買取価格が付くでしょう。
芝銭(しばせん)
1636年、寛永通宝が徳川幕府により公鋳銭として発行される際、製造されたのが芝銭です。
表面には「寛永通寶」と刻印されており、裏面には何も刻印されていません。
発行枚数が多いため、あまり高い価値は付きませんが、数百円が買取相場といわれています。
浅草銭(あさくさせん)
1636年、浅草に銭座が設置された際に寛永通宝の「浅草銭」が発行されました。
「御蔵銭(おくらせん)」や「志津磨百手」といった呼び方もあります。
また、浅草銭はそれ以外にもさまざまな呼び方があり、書体によって異なる名を持つといわれているのです。
書体や状態によって買取価格は異なり、数百円のものや千円前後のものもあります。
水戸銭(みとせん)
水戸銭は古寛永の一種で、常陸水戸に銭座が設けられた1637年から発行された寛永通宝です。
水戸銭は顕著な特徴がないため、見分けるには専門的知識が必要でしょう。
大量に発行されたことから、数百円で取引されることがほとんどですが、まれに数万円となるものも見られます。
買取業者に持って行き、種類や価値の判断をしてもらいましょう。
松本銭(まつもとせん)
松本銭は、1637年に現在の長野県松本市で発行された寛永通宝です。
発行枚数が少なく、希少価値が高い種類といわれています。
数千円から数万円で取引されることが多く、博物館に展示されるほど重宝されています。
偽物やレプリカが大量に流通するほど注目されているため、注意しましょう。
島屋文(しまやぶん)
レアな寛永通宝として知られている種類のひとつに、1668年に発行された「島屋文」があります。
島屋文は、新寛永初期に鋳造された寛永通宝で希少価値が高いといわれています。
表面に刻まれている「寛永通寶」の文字にある「通」の右上部分がカタカナの「ユ」のようになっていることが大きな特徴です。
裏面に「文」の字があるものや、ないものが存在します。
造り、状態などによって価値は異なりますが、数十万円で取引されることが多いでしょう。
正字背文(せいじはいぶん)
正字背文は1688年に亀戸銭座で発行された新寛永の一種です。
裏面に「文」の字が彫られている文銭の一種で、寛文の元号を表しているといわれています。
発行枚数が多いため、相場は数百円となっていますが、書体によっては高い価値が付くものもあります。
退点文(たいてんぶん)
退点文は、1668年に鋳造された新寛永で、裏面に「文」が刻印されている文銭の一種です。
「文」の1角目である点が右に寄っていることから「退点文」と呼ばれるようになりました。
寛永通宝の中でも比較的希少性があり、買取相場は数百円から数十万円といわれています。
正字入文(せいじいりぶん)
正字入文は退点文と同年の1668年に発行され、裏面に「文」の字が彫られています。
正字入文の特徴は「文」の2画目が「入」に似ていることが特徴です。
数百円が相場ですが、まれに数万円のものも見られます。
日光御用銭(にっこうごようせん)
日光御用銭は、将軍家が日光東照宮に参拝する際に使用するために1714年に発行されました。
当時の元号にちなんで、「正徳御用銭」と呼ばれることもあります。
表面に刻印されている「寛永通寳」の「寳」にある左上の「尓」のハネがないのが特徴です。
希少価値が高く、状態などが良ければ数十万円という査定額も期待できます。
下野国足尾銭(しもつけのくにあしおせん)
1714年に発行された下野国足尾銭は、裏面に「足」の文字が刻印されているのが特徴です。
「足字銭」という異名も持ち、大きさが均一されておらず、さまざまなサイズで作られています。
当時、足尾銅山は経営難に陥っており、それを救うために寛永通宝が鋳造されたといわれています。
査定額は大きさに比例しますが、発行枚数が多いことから数百円が相場です。
背広佐(せびろさ)
背広佐は1717年に発行された新寛永のひとつで、佐渡の銭座で鋳造された佐渡銭の一種です。
佐渡銭には佐渡鋳造の印である「佐」が刻印されているのが特徴で、背広佐は「佐」の4画目が大きく目立っています。
数百円で取引されることが多いものの、寛永通宝の中でも希少価値が高いため、条件がそろえば数十万円になる可能性もあるでしょう。
耳白銭(みみじろせん)
耳白銭は、1714年に亀戸で鋳造された寛永通宝で、外輪が広いのが特徴です。
当時、貨幣の外輪を「耳」と呼んでおり、江戸弁では「広い」を「シロイ」と発音したことから、「みみひろ」が変化して「耳白銭」になったという説があります。
また、外輪が白いことから「耳白銭」と呼ばれるようになった説もあります。
数百円から数万円が相場となっており、コレクターにも注目されている種類です。
石ノ巻銭(いしのまきせん)
石ノ巻銭は、1728年に現在の宮城県石巻市で鋳造されました。
裏面に「仙」の字が刻印されており、比較的希少価値が高いため、数千円が相場です。
書体によっては一万円前後になるものもあるといわれています。
小梅銭(こうめせん)
小梅銭は、1737年に江戸の小梅村というところで発行されました。
発行場所の小梅村にちなんで、裏面に「小」の文字が打たれているのが特徴です。
また、ほかの寛永通宝と比べると軽量であることも小梅銭を見極めるポイントとなります。
多くの書体が確認されており、書体によって価値は変わりますが、500円前後が相場といわれています。
寛永通宝を高価買取してもらうポイント
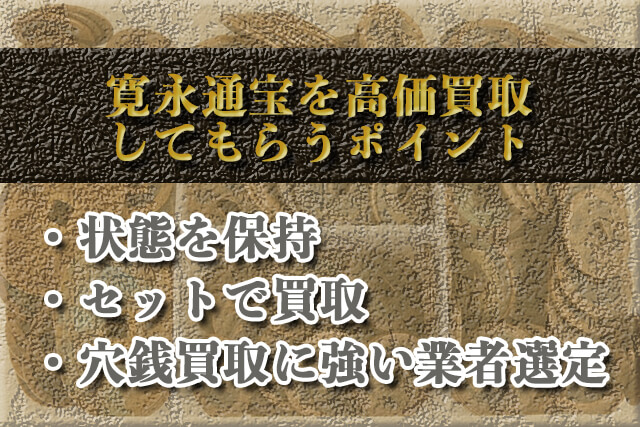
・状態を保持して早めに買取してもらう
・セットで買取してもらう
・穴銭買取に強い業者を選ぶ
寛永通宝をなるべく高価買取してもらうには、状態・セット買取・買取業者の選定がポイントです。
状態を保持して早めに買取してもらう
古銭は非常にデリケートで、査定に出すまでの保管方法が価値を左右するといっても過言ではありません。古くなれば古くなるほど劣化が進行するため、なるべく早く売却するのがオススメです。
状態がそれ以上悪くならないように、手袋などを使って素手で触るのを避け、ケースに入れるなどの保管方法で状態を保持しましょう。
セットで買取してもらう
寛永通宝は大量に出回っているため、希少価値が付きにくく、買取してもらえないことも少なくありません。
しかし、1個で価格が付かなくても、複数個をセットにして買取に出すと査定額が高くなる可能性があります。
もし寛永通宝が大量にある場合は、仕分けずにまとめて査定に出すことをオススメします。付属品(古い箱や由来の書付など)があれば、それらも一緒に査定してもらいましょう。
穴銭買取に強い業者を選ぶ
穴銭はその価値を知る専門知識がなければ的確な査定がされず、相応の価格を付けてもらえません。
少しでも高額取引をするためには、穴銭買取に優れた買取業者を選ぶ必要があります。
業者選びは慎重に行いましょう。
寛永通宝などの穴銭買取は福ちゃんへ

寛永通宝は流通量の多い穴線で、価値が付きにくいものが多いですが、高額査定されるレアな種類もあります。
状態の保持やセットで査定に出すなどで、高額買取が期待できるでしょう。
また、買取業者選びも重要になります。
福ちゃんには穴銭買取に精通しているプロが在籍しているため、古銭に適正な価格を付けることが可能です。
寛永通宝など穴銭買取をお考えなら、ぜひ福ちゃんにお任せください。
穴銭について詳しくはこちら↓↓
穴銭買取!価値ある古銭の種類一覧や鑑定額が高いレアものも紹介
お電話が混雑しており繋がらない場合は、大変申し訳ございませんが時間を空けてお問合せください。