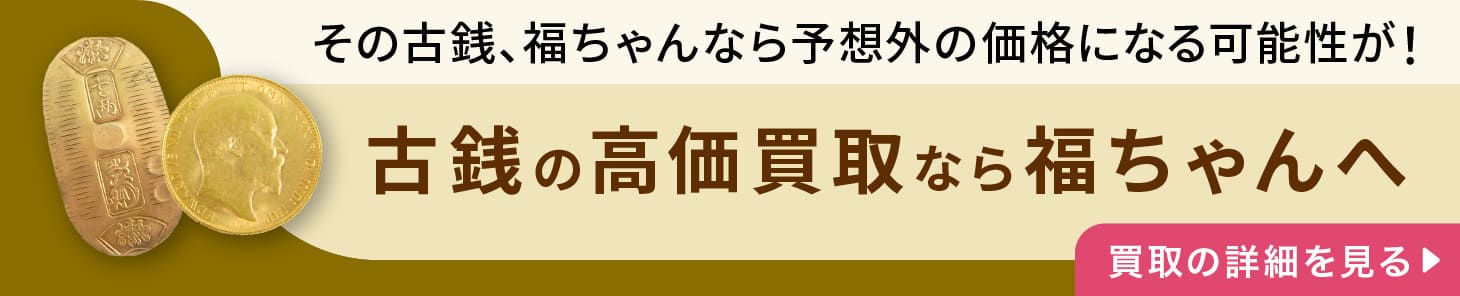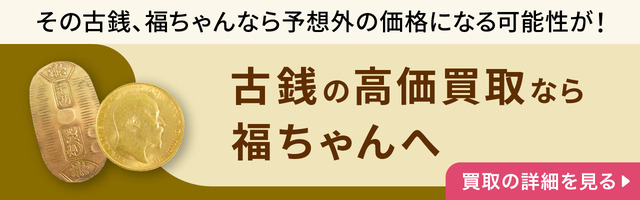一圓(一円)銀貨の買取相場紹介!価値や種類・本物と偽物の見分け方や特年も

「一圓銀貨って今も価値あるの?」
「一圓銀貨を持ってるけど本物かどうか知りたい」
など、一圓銀貨の情報を求めている人のために一圓銀貨についてまとめました。
一圓銀貨の買取相場や種類に加えて、真贋の見分け方や特年なども紹介しています。参考にしてください。
目次
一圓銀貨とは?明治3年発行開始の硬貨

一圓銀貨とは、1870年の明治3年に発行が開始され、当初は貿易用として使われていた貨幣です。
主に台湾や朝鮮で流通していましたが、1871年の明治4年に日本の貨幣単位を「圓(円)」とする新貨幣制度が制定された後、1878年から国内でも流通し始めました。
日本では1897年に通用停止とされましたが、台湾や朝鮮では流通が盛んだったため、停止することができず、製造自体は1914年まで行われたといわれています。
一圓銀貨の種類別買取相場

一圓銀貨は表面は中央に龍が彫られており、縁に額面や発行年数、「大日本」といった言葉などが彫られているのが特徴です。
龍の刻印が印象深いことから、「龍一圓銀貨」と呼ばれることもあります。
しかし、発行年数によってデザインや使用目的に違いがみられ、価値も変わってきます。
一圓銀貨の種類別に現在の価値を見てみましょう。
旧一圓銀貨

旧一圓銀貨は最初に発行された一圓銀貨で、使用用途を貿易に限定していたため、日本では流通していません。
裏面中央には太陽を象った意匠が彫られ、縁に桐紋や菊紋などがあります。
約2年間しか発行されておらず、希少価値が高いことから、現在は数万円で売買されることが多いでしょう。
また、表面にある「圓」の9画目が欠けているものは「欠貝圓」と呼ばれる種類でさらに価値が上がり、数十万円することもあります。
新一圓銀貨

- ✔︎ 新一圓大型銀貨
- ✔︎ 新一圓小型銀貨
新一圓銀貨には、新一圓大型銀貨と新一圓小型銀貨の2種類があり、文字通り新一圓大型銀貨の方が直径が数mm大きく縁に厚みがあるのが特徴です。
新一圓大型銀貨は1874年の明治7年から発行が開始され、当初は貿易専用でしたが、1878年の明治11年から国内での使用が許可されました。
新一圓小型銀貨は1887年の明治20年に発行開始となり、貿易と国内の両方で使用されています。
新一圓大型銀貨も新一圓小型銀貨もデザインはほぼ同じで、表面中央に龍が刻印され、縁は「大日本」と発行年数に加えて重さや額面・銀位を表す「416 ONE YEN 900」と彫られています。
裏面は「一圓」や菊紋が刻印されています。
新一圓大型銀貨は1万円以上の買取価格が期待できますが、新一圓小型銀貨は数千円で取引されることが多い種類です。
貿易銀

1875年の明治8年、諸外国と貿易する際に使用するためだけに貿易銀が製造され始めました。
当時、東洋市場で多大な力を奮っていたメキシコが使用していた8リアル銀貨に習い、純銀の含有量を向上させた貿易銀を国際通貨として発行したといわれています。
表面のデザインは新一圓銀貨とほとんど同じですが、縁に重さや銀位を表す「420 GRAINS.TRADE DOLLAR.900 FINE」とあるのが特徴です。
また、裏面には「貿易銀」と彫られています。
発行枚数が少ないため、数十万円で取引されることも少なくありません。
貿易銀について詳しくはこちら↓
貿易銀とは?年代別の価値や偽物の見分け方・その他の外交用硬貨紹介
丸銀

丸銀は一圓銀貨の裏面に丸で囲った「銀」の字が刻印されている種類です。
一時は国内でも通用可となった一圓銀貨ですが、1897年の明治30年に金本位制を基本とした貨幣法制定により、再度通用停止が決まりました。
しかし、台湾や朝鮮では圧倒的な流通量となっていたため、即座に通用停止とするのが難しく、当面の間は外地用に丸銀を製造していたといわれています。
丸銀の刻印の有無によって通用の可否が混乱し、市場が荒れたことで丸銀の製造や通用の実施は停止されました。
円形銀塊

明治34年以降に発行された一圓銀貨を「台湾銀行兌換引換用圓銀」や「円形銀塊」と呼ぶことがあります。
一圓銀貨が国内で通用禁止されたことから、明治34年銘以降の一圓銀貨は国内で貨幣として使用できませんでした。
そのため、明治34年以降の一圓銀貨は、一圓銀貨ではなく「円形銀塊」と表されることがあります。
国内では貨幣として流通していませんでしたが、日清戦争後に日本領となった台湾では一圓銀貨が流通し続けていました。
明治34年からは台湾銀行用に「台湾銀行兌換引換用圓銀」として一圓銀貨が発行され、1914年の大正3年まで製造が続いたといわれています。
円形銀塊は他の一圓銀貨と表裏が違い、大きな特徴である龍の刻印がある方が裏面とされています。
現存数は少ないとされているため、数万円から数十万円の価値が期待できるでしょう。
一圓銀貨の本物と偽物の見分け方

- ✔︎ 直径や厚み
- ✔︎ 重さ
通用中の貨幣を偽造すると罪に問われますが、一圓銀貨は現在流通している貨幣ではないため、偽物を作っても犯罪にはなりません。
そのため、偽物やレプリカがたくさん出回っています。
しかし、一圓銀貨の本物と偽物は、直径や厚みの数値や重さで見分けられることがあります。
直径や厚み
- ✔︎ 直径:約38.1mm(大型:約38.6mm)
- ✔︎ 厚み:約2.7mm
一圓銀貨の直径は約38.1mm、新一圓大型銀貨は38.6mmとされています。これより大きすぎたり小さすぎたりするものは偽物と考えられるでしょう。
また、厚みは測定する位置によって誤差があるため、基準となる数値はないといわれていますが、3mmを超えるものは偽物の可能性が高いとされています。
重さ
- ✔︎ 約26.96g
一圓銀貨の重さは約26.96gとされており、偽物はこれより軽いものが多いといわれています。
偽物は白銅貨と呼ばれる素材で作られることが多く、直径や厚みを本物に似せて作ると重さが足りなくなるでしょう。
重さを本物に似せて作ると、直径や厚みが本物と違ってくるため、重さやサイズは真贋を見極める指標の一つとなり得ます。
一圓銀貨の特年(特別年号)について

一圓銀貨には特年とされており、高額買取が期待できる種類があります。
一圓銀貨の価値をはかる際に重要となる「特年」について説明します。
特年とは?
特年とは、特別年号といわれ、発行枚数や流通量が少ない特別な年号のことを指します。
一圓銀貨に限らず、年号によって希少価値が高まる硬貨を「特年」と呼び、逆に手に入れやすい硬貨は「並号」です。
硬貨の種類は同じでも、特年であれば査定額が大幅に変わることがあります。
特年とされている発行年数

- ✔︎ 明治3年
- ✔︎ 明治7〜8年
- ✔︎ 明治11〜12年
- ✔︎ 明治19年
- ✔︎ 明治41年
特年としてよく知られている発行年数は、上記の発行年銘です。
特に明治8年は発行枚数が極めて少ない年といわれています。
これらの特年は、数十万円で取引されることが多く、コレクターにも注目されている種類です。
一圓銀貨を買い取ってもらう方法

- ✔︎ ネットオークション
- ✔︎ フリマアプリ
- ✔︎ 買取業者
一圓銀貨を買い取ってもらう方法として代表的なのは、上記の3つです。
ネットオークションやフリマアプリは自宅にいながら出品できるため、手軽な方法として親しまれています。
入札形式のネットオークションは需要があれば高値で落札される可能性があり、フリマアプリは自分で価格が決められる点などがメリットです。
しかし、本物と証明できる術がなければ、どちらでも買手が現れない、安く買い叩かれてしまうなどがあるかもしれません。
また、個人間の取引は、トラブルが発生することも考えられるでしょう。
そのため、銀貨などの古銭に関して取引実績がある買取業者に買い取ってもらう方法がおすすめです。
価値などを見極めて価格に反映するため、損のない売買が可能となります。
福ちゃんの一圓銀貨買取実績はこちら↓
1円銀貨買取なら福ちゃんへ!【銀貨買取】
一圓銀貨の買取は福ちゃんへ
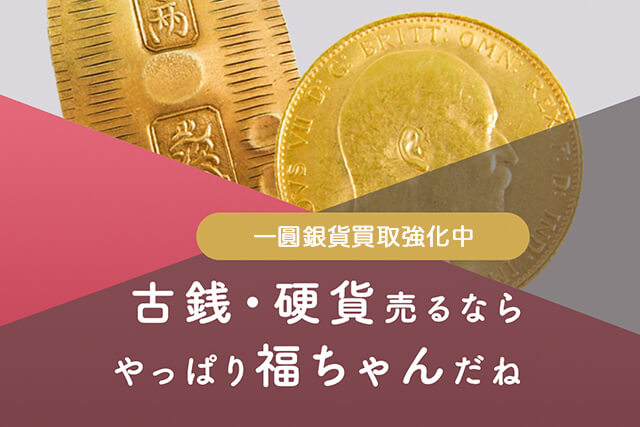
一圓銀貨は明治3年に貿易に特化した硬貨として発行されましたが、後に国内でも使用が開始された硬貨です。
発行年数によって役割が変化し、デザインにも多少の違いがあります。
種類によって査定額も上下するため、適正な価値が知りたい場合は買取業者の査定士に見てもらう方法が一番です。
福ちゃんには、一圓銀貨を含めた古銭に関する知識や売買経験が豊富な査定士が在籍しています。
一圓銀貨の種類や状態などを見極め、査定額を決定することが可能です。
一圓銀貨の買取は、福ちゃんへお任せください。
銀貨について詳しくはこちら↓
人気の銀貨一覧!今の値段や当時の価値、日本が製造した現在の注目銀貨も紹介
お電話受付時間 9:00~20:00 (年中無休※年末年始は除く)